目次
1.平均寿命とは
平均寿命とは、厚生労働省が毎年作成・公表する「簡易生命表」に基づく、0歳児の予測平均余命のことです。
具体的には、調査対象年(1~12月の1年間)の死亡状況が今後も変化しないと仮定したときに、0歳の子どもが平均であと何年生きられるかを表しています。
したがって、「平均寿命=亡くなった人の平均年齢」ではありません。
 将来のことを考えたときに、「自分は何歳頃まで生きられるのだろうか」と、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
将来のことを考えたときに、「自分は何歳頃まで生きられるのだろうか」と、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこで知っておきたいのが、生まれてから亡くなるまでの予測平均余命を表す「平均寿命」です。
今回は、平均寿命の定義や推移、平均寿命に影響を与える因子などについて解説します。
目次
平均寿命とは、厚生労働省が毎年作成・公表する「簡易生命表」に基づく、0歳児の予測平均余命のことです。
具体的には、調査対象年(1~12月の1年間)の死亡状況が今後も変化しないと仮定したときに、0歳の子どもが平均であと何年生きられるかを表しています。
したがって、「平均寿命=亡くなった人の平均年齢」ではありません。
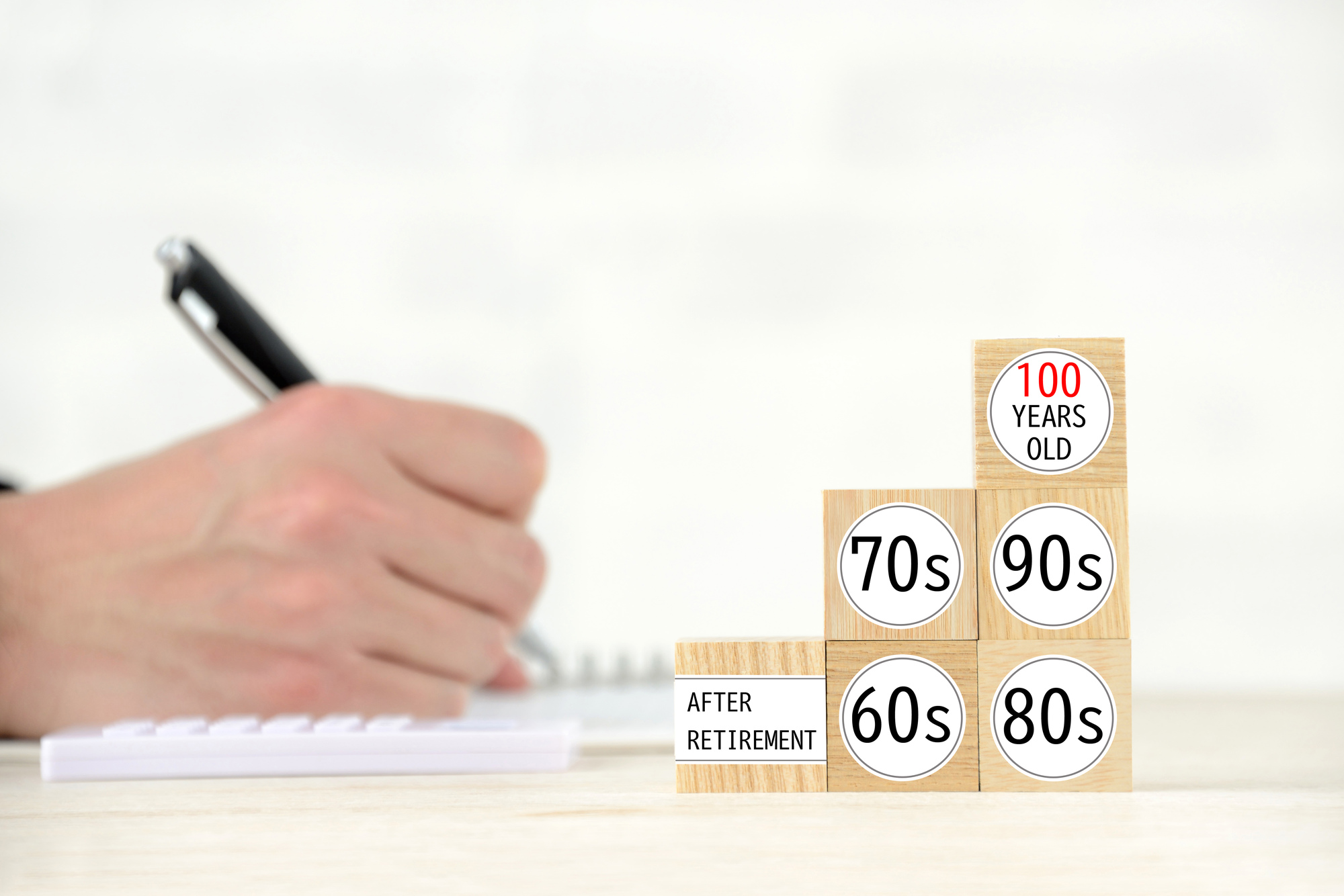 ここでは、平均寿命のこれまでの推移と、平均寿命に影響を与える因子について解説します。
ここでは、平均寿命のこれまでの推移と、平均寿命に影響を与える因子について解説します。
下表のとおり、日本の平均寿命は1947年から2020年まで、男女ともに延び続けていました。
しかし、2021年には男性の平均寿命が81.47年、女性の平均寿命が87.57年となり、それぞれ前年からわずかに縮小しています。
| 西暦 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 1947 | 50.06 | 53.96 |
| 1950~1952 | 59.57 | 62.97 |
| 1955 | 63.60 | 67.75 |
| 1960 | 65.32 | 70.19 |
| 1965 | 67.74 | 72.92 |
| 1970 | 69.31 | 74.66 |
| 1975 | 71.73 | 76.89 |
| 1980 | 73.35 | 78.76 |
| 1985 | 74.78 | 80.48 |
| 1990 | 75.92 | 81.90 |
| 1995 | 76.38 | 82.85 |
| 2000 | 77.72 | 84.60 |
| 2005 | 78.56 | 85.52 |
| 2010 | 79.55 | 86.30 |
| 2015 | 80.75 | 86.99 |
| 2020 | 81.56 | 87.71 |
| 2021 | 81.47 | 87.57 |
(単位:年)
※1 2020年以前は「完全生命表」(厚生労働省が5年ごとに作成・公表するもの)による
※2 1970年以前は、沖縄県を除く値である
参照:厚生労働省「令和3年簡易生命表の概況」
2021年の平均寿命と2020年の平均寿命の差について、どのような因子の影響を受けたか詳しく見てみましょう。
平均寿命を延ばす方向に働いたのは、男女ともに、交通事故や肺炎などの死亡率の変化です。一方で、老衰などの死亡率の変化が平均寿命を縮める方向に働きました。
平均寿命を縮める因子のほうが、延ばす因子よりも影響が強かったため、結果として平均寿命が縮小しています。
 「0歳児の予測平均余命」を表す平均寿命に対し、健康寿命は「健康上の理由で日常生活が制限されない期間」を指します。すなわち、平均寿命と健康寿命の差は「日常生活が制限される(=健康ではない)期間」を意味するため、なるべく差が出ないのが理想的です。
「0歳児の予測平均余命」を表す平均寿命に対し、健康寿命は「健康上の理由で日常生活が制限されない期間」を指します。すなわち、平均寿命と健康寿命の差は「日常生活が制限される(=健康ではない)期間」を意味するため、なるべく差が出ないのが理想的です。
平均寿命と同様に、健康寿命も年々延びていますが、平均寿命と健康寿命の差はあまり縮まっていません。健康寿命は3年ごとに調査されるため、最新の2019年のデータを平均寿命と比較すると、以下のとおりです。
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 平均寿命 | 81.41 | 87.45 |
| 健康寿命 | 72.68 | 75.38 |
| 差(平均寿命-健康寿命) | 8.73 | 12.07 |
(単位:年)
また、世界保健機関(WHO)が公表している世界183カ国の健康寿命を見ると、2016年のデータでは、日本はシンガポールに続き2番目に健康寿命が長い国です。
一方で、平均寿命と健康寿命の差の順位は31位でした。日本は健康寿命が比較的長いものの、そのあとに訪れる健康ではない期間も長い傾向にあるといえるでしょう。
0歳児の予測平均余命を表す平均寿命は、男女ともに80年を超えています。大切なのは、その80年を超える期間を、いかに健康で過ごせるかということです。
健康に過ごせる期間を延ばすためには、食事・運動・休養などの生活習慣の見直しが欠かせません。
平均寿命に興味を持ったのをきっかけに、あらためて生活習慣を振り返ってみてはいかがでしょうか。

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。
身体に関するお悩み

健康診断などの血液検査において中性脂肪の数値が高かった方は、生活習慣をいま一度見つめ直す必要があります。
身体に関するお悩み

自律神経系がきちんと働かなくなると、「食欲が湧かない」「よく眠れなくなった」などの現象がみられることがあります。
身体に関するお悩み

「緊張したら、急に下痢っぽくなってしまった」 「電車のなかなど、トイレに行きづらい状況でいきなりお腹が痛くなってしまった」 このように、不安や緊張を感じると、お腹の調子が悪くなる人は少なくありません。
身体に関するお悩み

日本には、約4,000万人もの高血圧の患者の方がいるといわれています。
身体に関するお悩み

「女性ホルモンが減ると、どのような影響があるのだろう?」 「女性ホルモンを増やす方法はあるの?」このような疑問を持つ女性の方は多いのではないでしょうか。