目次
1.交感神経とは?
交感神経は自律神経と呼ばれる神経の一つです。自律神経は脳から全身の組織に電気信号を伝える「ケーブル」のようなもので、循環器や消化器、筋肉、汗腺のようなさまざまな臓器などの働きを調節しています。
自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があり、この2つの神経は逆の働きを担っています。交感神経と副交感神経がバランス良く働くことで、心身は安定した状態に保たれるのです。
 「自律神経や交感神経などの言葉をよく聞くが、どういうものなのだろう?」
「自律神経や交感神経などの言葉をよく聞くが、どういうものなのだろう?」
「自律神経のバランスが乱れるとどのような不調が出るの?」
健康に関心がある方のなかには、このように自律神経の働きに興味を持っている方もいるかもしれません。
自律神経には、活動時に優位となる交感神経と休息時に優位となる副交感神経があり、交感神経と副交感神経は相反する役割を担っています。
今回は交感神経と副交感神経の違いや、バランスが崩れる原因などを解説します。
目次
交感神経は自律神経と呼ばれる神経の一つです。自律神経は脳から全身の組織に電気信号を伝える「ケーブル」のようなもので、循環器や消化器、筋肉、汗腺のようなさまざまな臓器などの働きを調節しています。
自律神経には交感神経と副交感神経の2種類があり、この2つの神経は逆の働きを担っています。交感神経と副交感神経がバランス良く働くことで、心身は安定した状態に保たれるのです。
 交感神経は活動時によく働き、副交感神経はリラックスしているときによく働くという点が、交感神経と副交感神経の大きな違いです。交感神経はおもに日中に活発に活動していると優位となり、緊張やストレスを感じたときにも活発化します。
交感神経は活動時によく働き、副交感神経はリラックスしているときによく働くという点が、交感神経と副交感神経の大きな違いです。交感神経はおもに日中に活発に活動していると優位となり、緊張やストレスを感じたときにも活発化します。
一方の副交感神経は、夕方頃から夜にかけて少しずつ優位になっていき、夜間に眠気が出て休みやすい状態へと導きます。眠っている間も副交感神経は優位に働いており、体の休息や修復に寄与するのです。
交感神経と副交感神経は一方に大きく傾くのではなく、平衡の状態を維持しながら、状況に合わせてわずかに片方が優位に傾くのが理想的と考えられています。交感神経だけが過剰に高まっていると緊張状態による不調が現れやすく、副交感神経ばかりが高まっていると日中の活動への悪影響につながります。
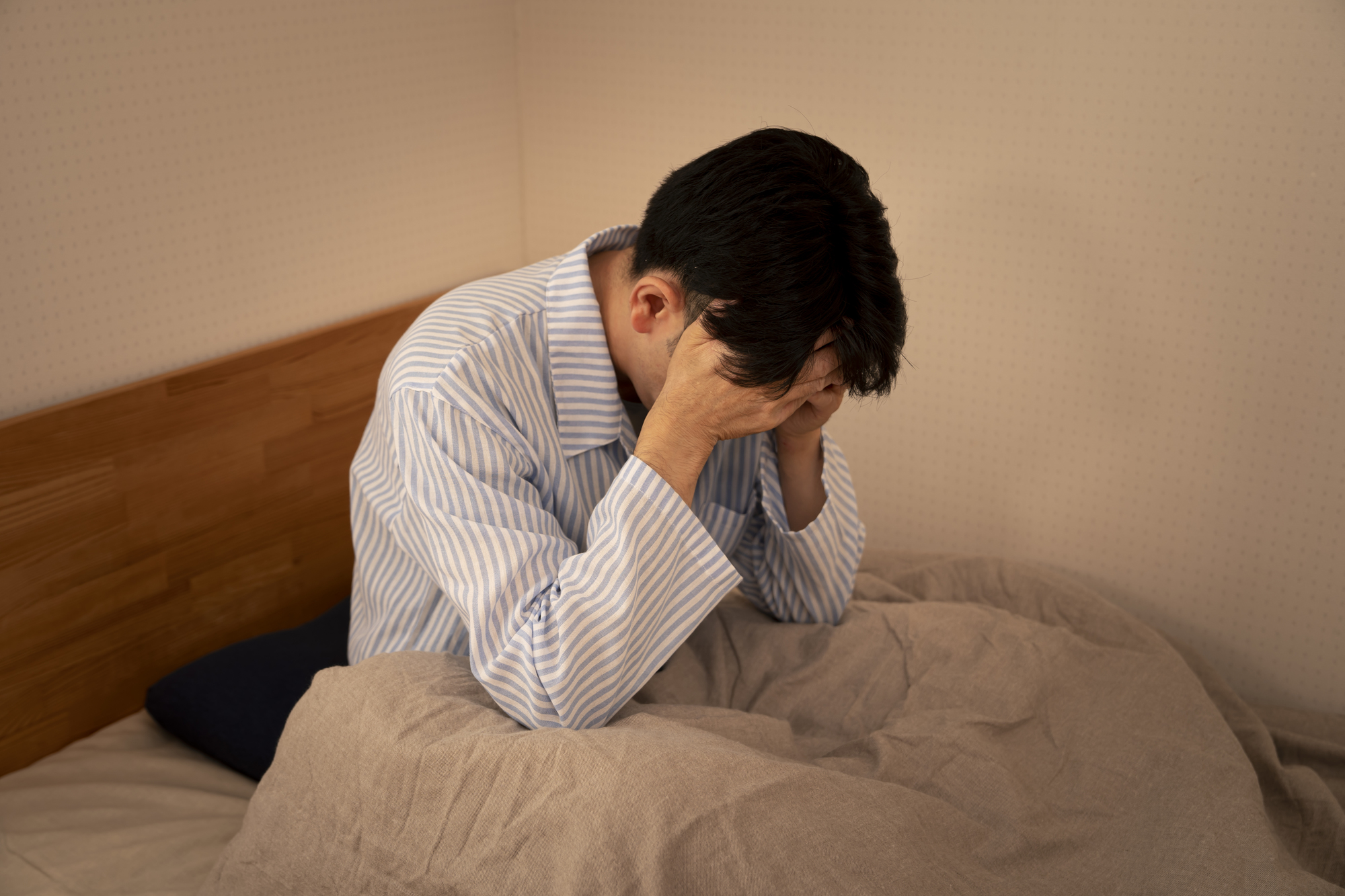 交感神経ばかりが優位でバランスが悪くなった場合に生じる現象や、原因について解説します。
交感神経ばかりが優位でバランスが悪くなった場合に生じる現象や、原因について解説します。
ストレスや緊張などの影響によって交感神経の優位な状態が持続すると、自律神経のバランスが崩れてさまざまな不調が現れます。具体的には、倦怠感や不眠、頭痛、動悸や息切れ、のぼせや冷え、立ち眩みやめまいなどが代表的です。
イライラや気分の落ち込み、不安感などの精神的な不調も多く見られます。自律神経は血管などにも関与しているため、自律神経の乱れが血流などに影響する場合もあります。
ストレスを受けると、交感神経の働きが活発になります。ストレスとは外部からの刺激を受けたときに起こる緊張状態のことで、心理的な悩みや人間関係トラブル、騒音、身辺の変化などさまざまな要因がストレス源になり得ます。不規則な生活リズムや乱れた食生活、運動不足、睡眠不足なども自律神経のバランスを乱す要因です。
また、加齢も交感神経が優位になる原因の一つとして知られています。交感神経の活動性はあまり加齢の影響を受けませんが、副交感神経は年齢とともに働きが低下するため、交感神経が優位になりやすいのです。
交感神経と副交感神経はバランス良く働くのが理想的ですが、ストレスや生活習慣の乱れ、加齢などによってバランスが崩れやすくなるため注意が必要です。
加齢は誰にも避けられないものですが、ストレス対策を意識的に行なったり、規則正しい生活を送ったりすることで副交感神経を高める効果が期待できます。できることから一つずつ、自律神経のバランスを整えるような生活を意識しましょう。

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
身体に関するお悩み

鼻血が出たり、出血後になかなか止まらなかったりして、驚いたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
身体に関するお悩み

肌の調子が良くないと悩んだことがある人は多いのではないでしょうか。
身体に関するお悩み

湿疹や虫刺されなど、特に異常はないけれど「肌がかゆくて仕方ない」という悩みを抱える方は多いでしょう。
身体に関するお悩み

夜型の生活になると、体の成長に影響が出たり集中力や注意力が低下したりすることがあります。
身体に関するお悩み

自分の血液検査データを見て、LDLコレステロールが高すぎたり、HDLコレステロールが低すぎたりして不安に思う人もいるのではないでしょうか。