1.睡眠負債とは?
睡眠負債とは、睡眠不足が慢性化し、“借金”のように蓄積された状態のことです。
適切な睡眠時間は、6~8時間が目安とされています。令和元年に厚生労働省が行なった調査(※1)によると、睡眠時間が6時間に満たない人の割合は、男性37.5%、女性40.6%でした。男性では30~50歳代、女性で40~50歳代に多く、4割以上もの人が該当したのです。
世界的にも日本人の睡眠時間は短く、特に就労者や子どもたちの睡眠時間は世界で最も短い、という調査結果もあります。
※1:
出典:厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」
2.睡眠負債が健康におよぼす影響
 睡眠負債では、体を十分に休めることができないため、心身ともに悪影響を与えます。
睡眠負債では、体を十分に休めることができないため、心身ともに悪影響を与えます。
2-1.思考力の低下
睡眠不足が長期的に続くと、思考力や集中力・記憶力・注意力・活力などが低下して学業や仕事の効率が下がります。その結果、イライラや不安感・疲労感が増幅し、自信喪失する原因となるのです。
こういったヒューマンエラーにより、事故を引き起こす危険性が高まります。
2-2.生活習慣に関連した病気のリスクが高まる
積み重なる睡眠負債により生活習慣に関連した病気のリスクが高まります。乱れた食生活や運動不足・喫煙などにより睡眠の質は悪化するのです。
慢性的な睡眠障害を抱えている人は、以下のような生活習慣病のリスクがあります。
2-3.脳に悪影響がある
国立精神・神経医療研究センターでの実験(※2)により、「睡眠時間が一日4.5時間程度の睡眠不足が5日間続くと、脳の機能に悪影響が現れる」ということが実証されました。脳機能に起こる悪影響として、不安・混乱などが強まることがわかったのです。また、睡眠不足によりネガティブな情報に反応しやすくなることも明らかになりました。
「キレやすい」「気分が沈んだ傾向」が社会的な問題として取り挙げられるニュースの背景には、睡眠不足が隠れている可能性があると研究者たちは指摘しています。
2-4.耳鳴りやめまい
長期間の睡眠障害により、体の機能は低下し、耳鳴りやめまいを引き起こすことがあります。
耳鳴りやめまいをともなう病気の一つである「突発性難聴」も、睡眠不足などのストレスがある状況で起こりやすい疾患です。突然、片方(まれに両方)の耳の聞こえが悪くなることが特徴で、年齢を問わず発症するので睡眠不足には注意しましょう。
※2:
出典:Science Portal「睡眠不足で情動不安定や抑うつに」(2013.02.15)科学技術振興機構(JST)
3.睡眠負債の解消法や予防法
 質の良い睡眠こそ健康への良薬となります。まずは、一日の過ごし方を見直して、睡眠負債と縁遠い毎日を目指しましょう。
質の良い睡眠こそ健康への良薬となります。まずは、一日の過ごし方を見直して、睡眠負債と縁遠い毎日を目指しましょう。
3-1.寝る時間・起きる時間を一定にする
睡眠のリズムは、体内時計で調整されています。休日の前日には夜更かししがちですが、体内時計を狂わせる原因になるので注意が必要です。毎日同じ時間に寝て起きるように習慣づけることで、睡眠のリズムが整います。
3-2.夜の過ごし方をルーティン化する
夜の寝つきが悪い人は、夜スムーズに眠れるように、夜の過ごし方をルーティン化するとよいでしょう。入浴後や夕食後は、代謝が活発になり体は活動モードになっているため、寝床に入るまでに2時間は時間を空けることが大切です。
例えば、入浴と夕食後は、テレビ鑑賞や家族との会話などリラックスタイムを過ごし、歯磨きをしてから寝床に入るとよいでしょう。自分なりの入眠モードにつながる過ごし方をルーティン化するのがおすすめです。
3-3.朝日を浴びる
朝起きたら太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされます。また、太陽の光を浴びてから14時間以降に眠気を誘発することがわかっているのです。朝早くに朝日を浴びることで夜眠気を感じる時間が早まるため、早起きは早寝につながります。
3-4.ストレスをためない
ストレスは眠りの大敵です。自分に合ったストレス解消方法を見つけて、上手に気分転換をしましょう。
3-5.適度な運動習慣をつける
運動による適度な疲れは、心地良い眠りにつながります。反対に、激しい運動は刺激となり、寝つきを悪くするので注意しましょう。集中的な運動を短期間行なうよりも、無理のない程度で長時間の運動をするほうが効果的です。ウォーキングなどの有酸素運動が始めやすいでしょう。
3-6.寝室の環境を整える
眠りやすい環境づくりも大切です。布団や枕は自分に合ったものを選び、温度や湿度・照明の明るさにも配慮しましょう。眠りに適した温度は20度ほど、湿度は40~70%といわれています。
また、日本でよく使われている白っぽい蛍光灯は、体内時計を遅らせる作用があるため、寝室は赤みが強い暖色系の蛍光灯が理想的です。
快眠生活でベストな毎日を目指そう
睡眠負債は、睡眠不足が慢性化し、借金のように蓄積された状態です。心身ともにしっかりと休養できない状態が続くため、健康に悪影響がでます。
睡眠不足は、5日間程度の短期的なものであっても情緒不安定・気分が晴れない状態に脳機能が変化することがわかっているのです。長期的に睡眠不足が続くと精神的な疾患や生活習慣に関連した病気・事故を起こすリスクが高くなります。
夜、寝たくても眠れないという人は、まずは今回紹介した睡眠負債の予防・解消法を試してみてください。ベストな日々を送れるように、毎日快眠を目指しましょう。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。


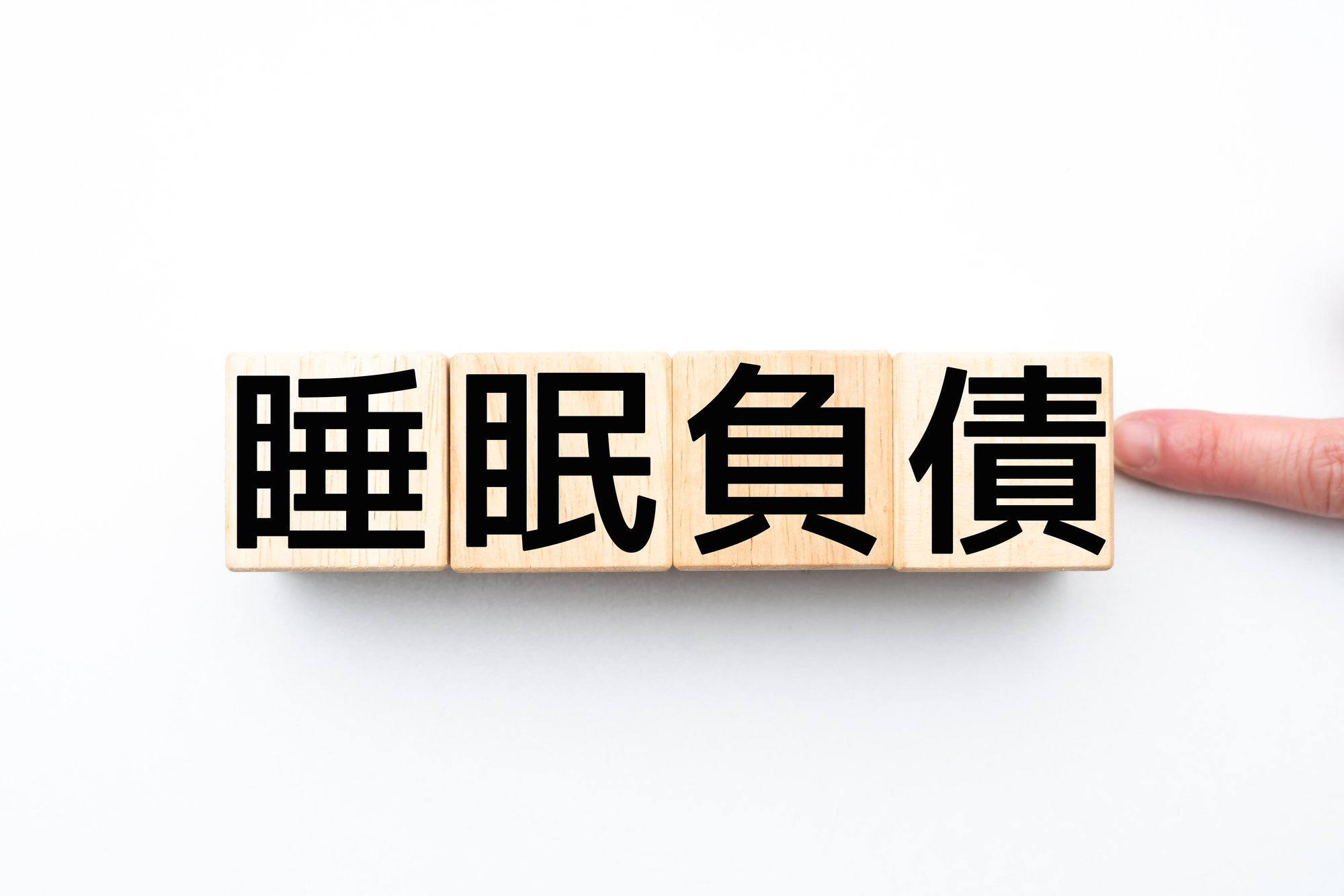 寝不足が続いて毎日疲れていませんか?寝不足の毎日があたり前になると、体は悲鳴を上げ、日常生活に支障をきたします。さらに進行するとさまざまな病気や事故を引き起こしてしまうケースもあるのです。
寝不足が続いて毎日疲れていませんか?寝不足の毎日があたり前になると、体は悲鳴を上げ、日常生活に支障をきたします。さらに進行するとさまざまな病気や事故を引き起こしてしまうケースもあるのです。 睡眠負債では、体を十分に休めることができないため、心身ともに悪影響を与えます。
睡眠負債では、体を十分に休めることができないため、心身ともに悪影響を与えます。
 質の良い睡眠こそ健康への良薬となります。まずは、一日の過ごし方を見直して、睡眠負債と縁遠い毎日を目指しましょう。
質の良い睡眠こそ健康への良薬となります。まずは、一日の過ごし方を見直して、睡眠負債と縁遠い毎日を目指しましょう。







