自然界に広くあらゆるところに存在する黄色、または赤色の色素をカロテノイドといいます。カロテノイドはカロテン類とキサントフィル類の2つに分類されますが、カロテン類の代表的なものがβ-カロテンです。ビタミンAに変わる物質を総称してプロビタミンAといいますが、β-カロテンもその一つです。 ただし、体内に入ったβ-カロテンのすべてがビタミンAに変わるわけではありません。
β-カロテンは成長に関する重要なビタミンで、レチノールとも呼ばれています。
不飽和脂肪酸のうち、炭素間の二重結合を1つ持つのが一価不飽和脂肪酸です。オリーブ油に多く含まるオレイン酸が、一価不飽和脂肪酸として知られています。
ビタミンAの機能以外の働きとして、ビタミンAに変換されず体内に蓄積した、カロテノイドとしての作用があります。
通常の食事をしていれば、基本的にβ-カロテン(ビタミンA)が不足する危険性は低いと考えられています。しかし、無理なダイエットや長期的に下痢をおこしている方は、ビタミンAが不足することもありますので注意してください。
β-カロテン(ビタミンA)の食事摂取基準*1を紹介します。
性別
男性
女性
年齢等
推定平均必要量*2
推奨量*2
目安量*3
上限量*3
推定平均必要量*2
推奨量*2
目安量*3
上限量*3
0~5(月)
–
–
300
600
–
–
300
600
6~11(月)
–
–
400
600
–
–
400
600
1~2(歳)
300
400
–
600
250
350
–
600
3~5(歳)
350
450
–
700
350
500
–
850
6~7(歳)
300
400
–
950
300
400
–
1,200
8~9(歳)
350
500
–
1,200
350
500
–
1,500
10~11(歳)
450
600
–
1,500
400
600
–
1,900
12~14(歳)
550
800
–
2,100
500
700
–
2,500
15~17(歳)
650
900
–
2,500
500
650
–
2,800
18~29(歳)
600
850
–
2,700
450
650
–
2,700
30~49(歳)
650
900
–
2,700
500
700
–
2,700
50~64(歳)
650
900
–
2,700
500
700
–
2,700
65~74(歳)
600
850
–
2,700
500
700
–
2,700
75以上(歳)
550
800
–
2,700
450
650
–
2,700
妊婦初期(付加量)
+0
+0
–
–
妊婦中期(付加量)
+60
+80
–
–
授乳婦
+300
+450
–
–
日本人の食事摂取基準(2020年版) 」
β-カロテンのプロビタミンAとしての過剰摂取による障害報告はないのが現状です。皮膚が黄色くなる柑皮症をまねくこともありますが、健康に有害ではないため障害とは考えられていません。
β-カロテンを多く含む食品は以下のとおりです。日々の食生活に上手に取り入れてみてください。
食品名
含有量(100gあたりg)
あまのり/ほしのり
38000μg
パセリ/乾
28000μg
とうがらし/乾
14000μg
にんじん/冷凍/油いため
11000μg
しそ/葉/生
11000μg
(文部科学省「食品成分データベース 」をもとに作成)
カロテノイドの一種であるβ-カロテンについて紹介しました。
監修者情報
氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)


 たんぱく質・糖質・脂質・ビタミン・ミネラルはヒトの体に欠かせない成分であり、5大栄養素と呼ばれます。
たんぱく質・糖質・脂質・ビタミン・ミネラルはヒトの体に欠かせない成分であり、5大栄養素と呼ばれます。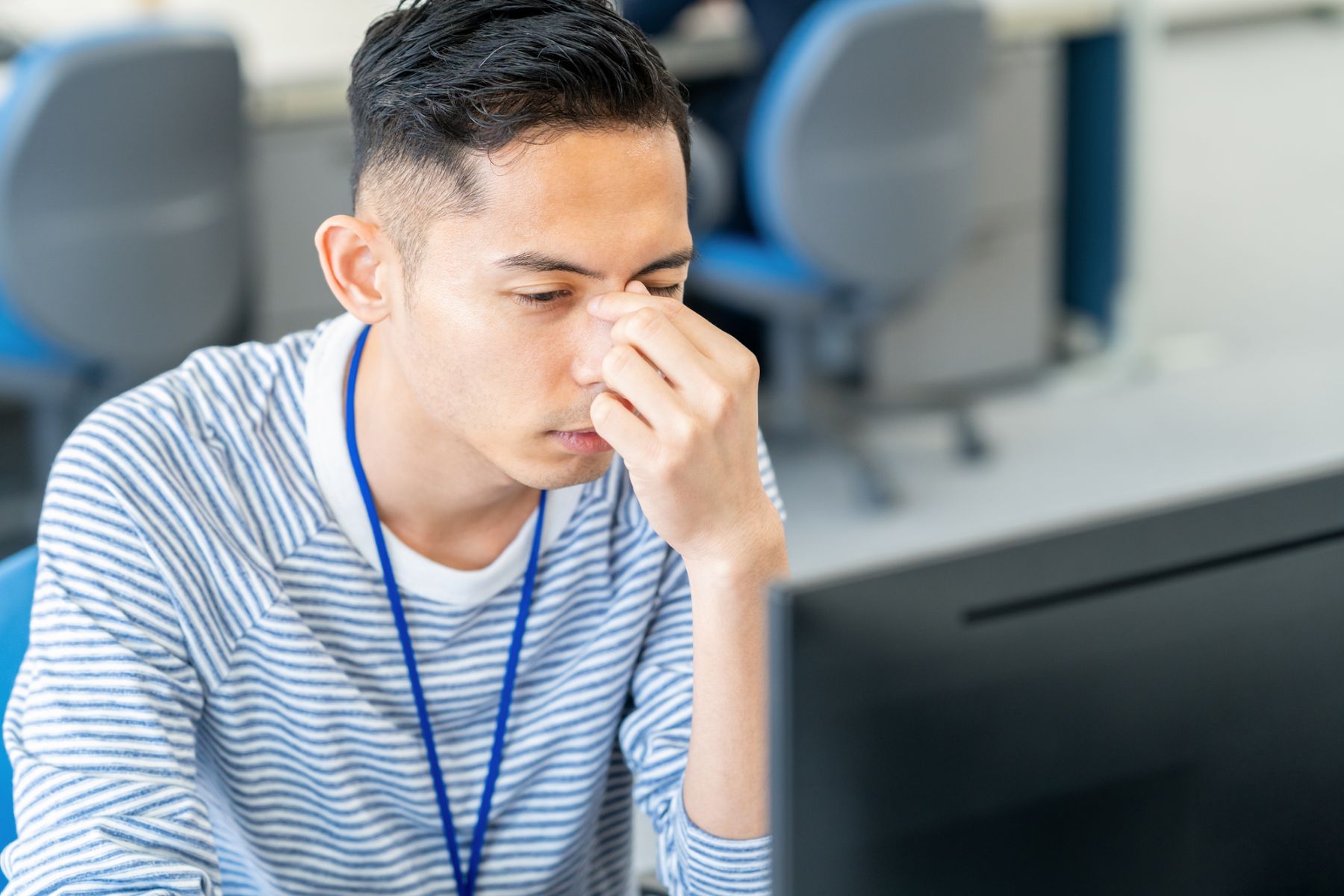 つぎに該当する場合、β-カロテン(ビタミンA)の摂取が必要である可能性があります。
つぎに該当する場合、β-カロテン(ビタミンA)の摂取が必要である可能性があります。







