1.ED(勃起障害)とは
EDは、正式には「Erectile Dysfunction」といい、日本語では「勃起不全/勃起障害」を意味します。EDというと、まったく勃起しなくなることのみを指すと思われるかもしれませんが、性交時に勃起状態を維持できない場合なども該当します。
つまりEDとは、十分に勃起できないことや、十分な勃起状態を維持できないことで、性交を満足に行なえない状態といえるでしょう。
原因について詳しくは後述しますが、EDを発症する原因は運動不足や喫煙など生活習慣に関わるものから、うつなどの精神的なものまでさまざまです。さらに、加齢もEDが起こる原因の一つとなり、年齢を重ねるにつれて有病率が高くなる傾向にあります。
日本国内では、1998年時点でEDの有病者数がおよそ1,130万人(中等度の人も含む)とされています。上記のように、加齢とともに有病率が上がることを考えると、2022年1月現在では、さらに増えていることが考えられるでしょう。
2.EDを引き起こすおもな原因
 先述のとおり、EDが起こる原因にはさまざまなものがありますが、原因によって器質性、心因性、混合性に分かれます。
先述のとおり、EDが起こる原因にはさまざまなものがありますが、原因によって器質性、心因性、混合性に分かれます。
混合性は器質性と心因性が混在するもののため、ここでは器質性EDと心因性EDの原因を紹介します。
2-1.器質性EDの原因
神経や血管など、身体的な障害によって起こるEDを器質性EDといいます。高血圧や高脂血症の場合は、血管の柔軟性が失われ勃起に必要な血液が陰茎まで回らなくなることで起こり、糖尿病の場合は、神経障害によって性的刺激が陰茎に伝わらないことで起こるものです。
また、メタボリックシンドロームも血管の柔軟性を失う要因となることから、EDにつながるとされています。高血圧や糖尿病、メタボリックシンドロームなどが原因となることから、EDは生活習慣病と深く関係していると考えられるでしょう。
2-2.心因性EDの原因
勃起機能に問題がないにも関わらず、精神的な要因で勃起不全を起こすものを心因性EDといいます。夜間陰茎勃起現象(睡眠時に起こりやすい生理的な勃起)は正常に発生しやすいのが特徴です。
心因性EDは、うつ病などの精神疾患やストレスなどの精神的な問題が原因で起こります。後者の精神的な問題には、日常のストレスなどが該当するでしょう。
心因性EDの場合は、原因となっている心理的要素を解消することで、改善に向かうことがあるようです。
3.ED改善に役立つ日常生活での工夫
 器質性EDの原因でも述べたとおり、EDは生活習慣病と深く関わっています。そのため、生活習慣病の予防がED予防にもなると考えられるでしょう。
器質性EDの原因でも述べたとおり、EDは生活習慣病と深く関わっています。そのため、生活習慣病の予防がED予防にもなると考えられるでしょう。
3-1.バランスの良い食事と運動
バランスの良い食事を適量とり、運動による体重減少は肥満の解消につながるため、ED改善に有効だといえるでしょう。
食事では、栄養が偏らないように気を付けて塩分や動物性脂肪を控えることと、満腹になるまで食べすぎないようにすることがポイントです。
運動には、気軽に始めやすいウォーキングなどを取り入れるとよいでしょう。適度な運動すれば、生活習慣予防やストレス解消にもつながります。
3-2.禁煙
「ED(勃起障害)とは」の章でも少し触れたとおり、喫煙もEDにつながるため、禁煙もED改善につながります。
EDと禁煙の関係を調べた研究では、EDを発症したヘビースモーカーが1ヵ月禁煙した結果、陰茎の硬度や膨張率にしっかりと改善が見られたことがわかっています。
このことから、禁煙はEDの改善に有効だと考えられるでしょう。
生活習慣を整えて元気に過ごそう
ED(勃起障害)は、QOLを低下させる疾患の一つだといえるでしょう。
EDには、身体的な障害が要因で起こる器質性EDと、精神的な障害が要因で起こる心因性EDがあります。器質性EDは高血圧や糖尿病、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病が大きく関わっているため、生活習慣を整えることが大切です。
普段の食事の見直しや適度な運動、禁煙などを行なって健康的な生活を心がけてください。食事においては栄養バランスや食事の摂取量を意識し、運動においては手軽に始められて継続しやすいものを取り入れるよう意識するとよいでしょう。
監修者情報

氏名:西原 佑一(にしはら・ゆういち)
2018年慶應義塾大学医学部外科学大学院卒業(医学博士)。
現在は関東の病院で外科医として勤務。おもにがん治療 ・外科手術 ・教育などの外科医療を提供している。


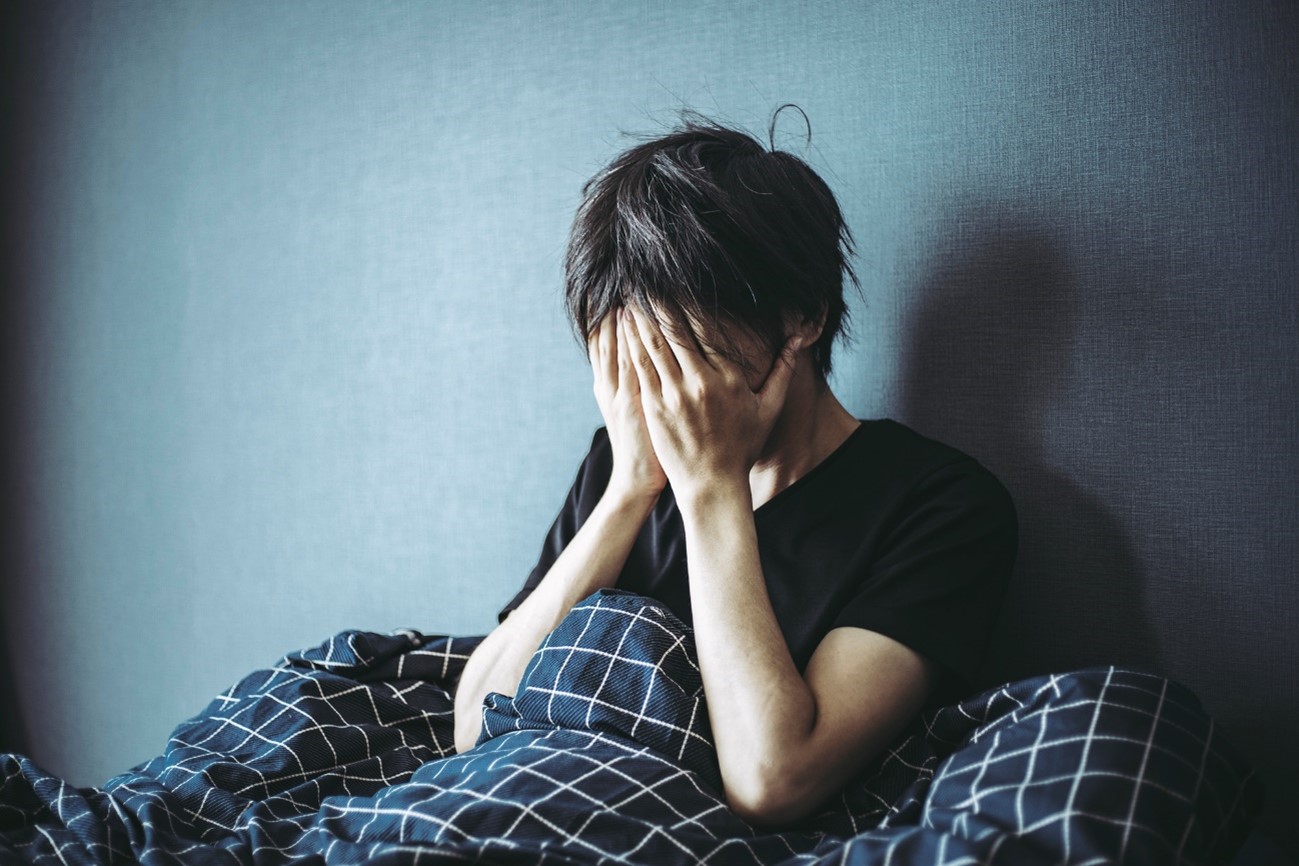 人は加齢にともない、体の不調を感じることが多くなります。そのなかには、命には影響がないものの、QOL(生活の質)を下げてしまうような症状があることも少なくありません。
人は加齢にともない、体の不調を感じることが多くなります。そのなかには、命には影響がないものの、QOL(生活の質)を下げてしまうような症状があることも少なくありません。 先述のとおり、EDが起こる原因にはさまざまなものがありますが、原因によって器質性、心因性、混合性に分かれます。
先述のとおり、EDが起こる原因にはさまざまなものがありますが、原因によって器質性、心因性、混合性に分かれます。 器質性EDの原因でも述べたとおり、EDは生活習慣病と深く関わっています。そのため、生活習慣病の予防がED予防にもなると考えられるでしょう。
器質性EDの原因でも述べたとおり、EDは生活習慣病と深く関わっています。そのため、生活習慣病の予防がED予防にもなると考えられるでしょう。







