1.頻尿とは?基本について解説
 「トイレに行ったばかりなのに、またすぐに行きたくなる」「寝ているときにトイレが近くて何度も目覚めてしまう」というように、排尿の回数が多くなったと感じる場合は頻尿の可能性があります。
「トイレに行ったばかりなのに、またすぐに行きたくなる」「寝ているときにトイレが近くて何度も目覚めてしまう」というように、排尿の回数が多くなったと感じる場合は頻尿の可能性があります。
具体的には、日中の排尿が8回以上である場合を頻尿と呼ぶことが多いですが、個人差があるため、回数で判断するのではなく「トイレが近くて困る」と感じる場合は頻尿といえます。
1-1.習慣性頻尿
尿がたまっている感覚がないのに、心配だからと頻繁にトイレに行っていませんか?「電車やバスに乗る前に必ずトイレに行くようにしている」「外出すると、トイレを見かけるたびに入っている」という人は、「習慣性頻尿」の可能性があります。膀胱に尿がたまり切らない状態でトイレに行き、少量の尿を頻繁に出しているだけなので、病気とはいえないでしょう。
漏れそうな状態のときに我慢する必要はありませんが、もし尿が出そうになる感覚が少ない状態でトイレに行く人は、もう少し間隔を延ばしてみることがおすすめです。
1-2.夜間頻尿
日中では気にならないものの、夜寝ている間にトイレに行きたくなり、何度も目が覚めてしまうという場合は「夜間頻尿」の可能性があります。夜間頻尿の原因は、一日の水分量などにともなう尿量の増加、治療のために服用している薬の影響や、睡眠に障害があるなどさまざまな要因が考えられるでしょう。
また、男性の場合は前立腺肥大が原因で夜間頻尿に陥る場合があり、詳細は次章にて解説します。
夜間頻尿で困っているという場合は病院で相談しましょう。
2.男性の頻尿に多いおもな原因
男性が50歳を過ぎると、排尿に関するさまざまな症状があらわれ始めますが、多くの場合、「前立腺肥大症」が関わっています。前立腺とは膀胱の出口にあり、男性の生殖機能に関わる器官です。尿道を取りまき、クルミぐらいの大きさをしています。肥大した前立腺は尿道や膀胱を圧迫します。その結果「尿が出にくい」「トイレに行く回数が増える」「尿が出るまでの時間がかかる」「排尿の我慢ができなくなる」など、排尿障害と呼ばれるさまざまな症状があらわれます。
前立腺肥大症は、まず薬による治療から開始。薬で症状が改善しない場合は手術による治療が検討されることもあります。
3.頻尿に見られるおもな疾患・症状
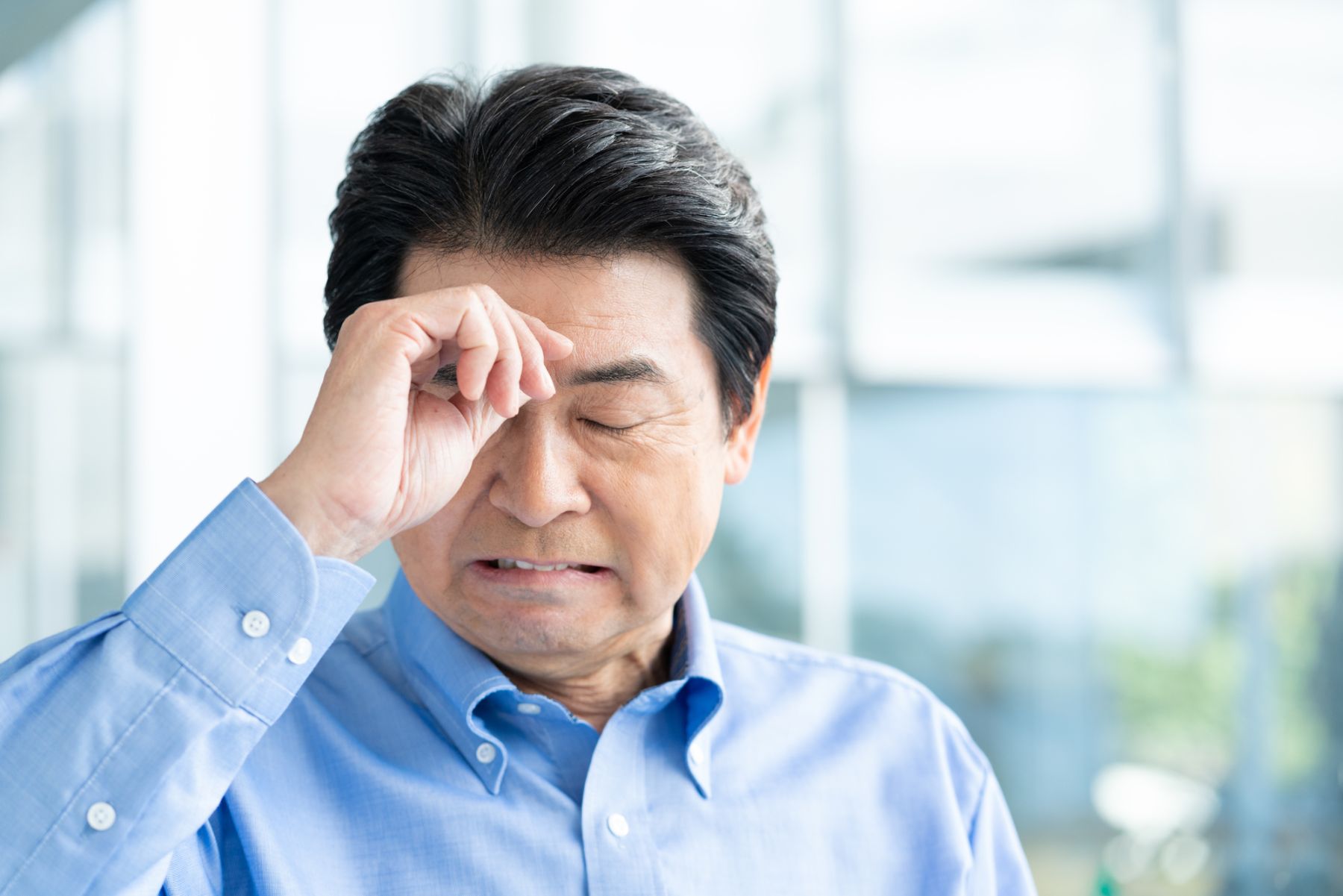 前立腺肥大症以外にも、頻尿になる原因や疾患はさまざまあります。
前立腺肥大症以外にも、頻尿になる原因や疾患はさまざまあります。
3-1.過活動膀胱
過活動膀胱とは、膀胱に尿がたまっていないにも関わらず、膀胱の筋肉が意図せず動いてしまい尿を出そうとする疾患です。何度も急にトイレに行きたくなったり、間に合わずに漏らしてしまったりするなどの症状が起こります。
過活動膀胱になる理由ははっきりしていませんが、前立腺肥大症や女性の場合では出産や加齢による骨盤底筋の異常などが原因となるといわれています。
3-2.多尿
「さっき済ませたのにまたトイレに行きたくなる」「1回あたりの尿の量が多いと感じる」という場合は、水分を摂りすぎている可能性があります。
一日のなかで、食事以外で摂る水分量は体重の2~2.5%が適量とされています。例えば体重50kgの人の場合、一日あたり1,000~1,250ml、体重70kgの人の場合は一日あたり1,400~1,750mlが適量です。
夏場や汗をかいたとき、乾燥しているときなどはより水分が必要になります。そのため目安の数値として参考にしてください。また、紅茶などの利尿作用を促す飲み物は、体の水分を外に出しやすい特性があるため、適量を守るようにしましょう。
3-3.膀胱炎
膀胱は、腎臓で生成された尿をためておく器官です。膀胱が何らかの原因で炎症を起こすと、排尿に関する症状が出てきます。例えば排尿するときの痛み、尿が残っている感覚(残尿感)、血が混じった尿が出る、尿の回数が増えるなどです。
また、膀胱炎の一種である「間質性膀胱炎」は、膀胱に尿がたまっていくと下腹部・肛門周辺に激しい痛みが起こりやすい疾患で、その痛みにともない尿の回数が増えます。
頻尿の原因を知り、体調の変化に気をつけましょう
男性に多い頻尿の原因や考えうる疾患についてお伝えしました。男性の場合、50歳前後から前立腺肥大症によって頻尿を自覚するケースが多い傾向にあります。頻尿の自覚がある人のなかにはトイレに頻繁に行く習慣があったり、水分の摂りすぎであったりとすぐに受診が必要ない場合もありますが、治療を必要とする可能性もあります。
そのため、日常生活に支障があると感じた場合は早めの受診を検討してみてください。
監修者情報

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)
外科医として地方中核病院に勤務中。
消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。
資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医
 「トイレに行ったばかりなのに、またすぐに行きたくなる」「寝ているときにトイレが近くて何度も目覚めてしまう」というように、排尿の回数が多くなったと感じる場合は頻尿の可能性があります。
「トイレに行ったばかりなのに、またすぐに行きたくなる」「寝ているときにトイレが近くて何度も目覚めてしまう」というように、排尿の回数が多くなったと感じる場合は頻尿の可能性があります。

 ある程度年齢を重ねてきた男性のなかには、「以前よりのトイレの回数が増えた」と感じる人も多いのではないでしょうか。なかなか人に言いづらい悩みではありますが、年齢とともにトイレが近くなるのは決して少数派ではありません。
ある程度年齢を重ねてきた男性のなかには、「以前よりのトイレの回数が増えた」と感じる人も多いのではないでしょうか。なかなか人に言いづらい悩みではありますが、年齢とともにトイレが近くなるのは決して少数派ではありません。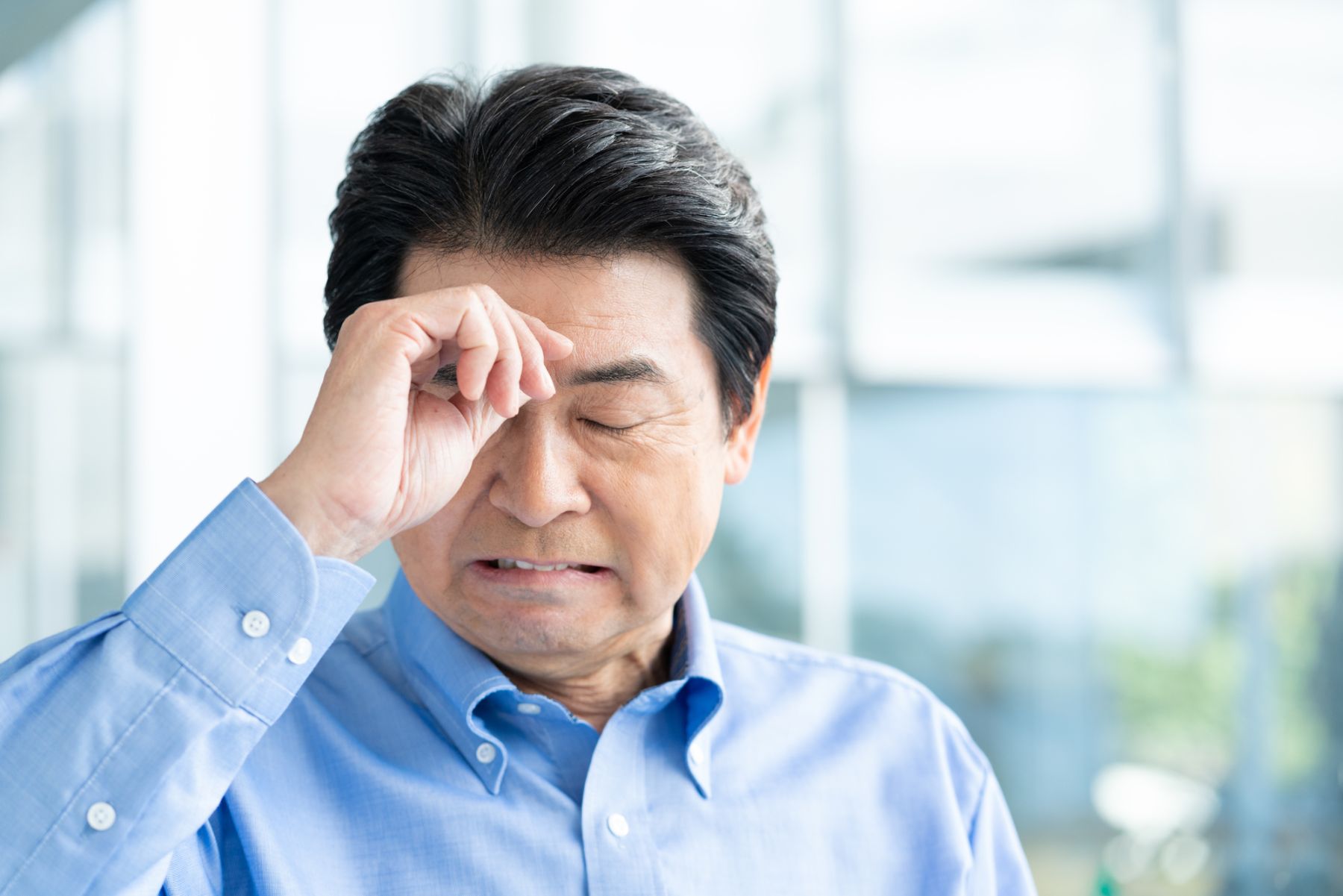 前立腺肥大症以外にも、頻尿になる原因や疾患はさまざまあります。
前立腺肥大症以外にも、頻尿になる原因や疾患はさまざまあります。







