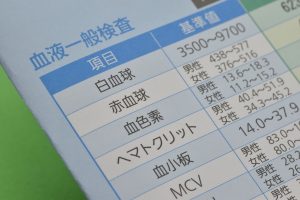目次
1.【部位別】内臓が不調になる原因とその症状
 まずは、内臓が不調となる原因やその症状を、腸と胃、肝臓の部位別にそれぞれ説明します。
まずは、内臓が不調となる原因やその症状を、腸と胃、肝臓の部位別にそれぞれ説明します。
1-1.【腸】不調の原因と症状
腸の不調としておもに考えられるのは、便秘や過敏性腸症候群でしょう。
-
便秘
健康な状態を保つうえで、快便は重要なポイントです。しかし、食生活の乱れや運動不足、ストレスなどによって便秘になる人は増えています。
「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では、便秘の定義を「本来体外に出すべき便を十分な量かつ快適に排出できない状態」としています。
また、以下に挙げる診断基準のうち2つ以上を満たす場合は、便秘症に該当します。
<便秘症の診断基準>
・排便の4分の1超の頻度で、強くいきまなければならない
・排便の4分の1超の頻度で、硬便または兎糞状便が出る
・排便の4分の1超の頻度で、残便感がある
・排便の4分の1超の頻度で、直腸肛門の閉そく感または排便困難感がある
・排便の4分の1超の頻度で、摘便や会陰部圧迫などの用手的な排便介助が必要となる
・自発的な排便回数が週3回未満である
なお、便秘症にはいくつかの種類がありますが、日本では器質性・薬剤性・症候性・機能性の4つに大きく分け、さらに機能性便秘症を弛緩性・痙攣性・直腸性の3つに分けています。
このうち、日本人に多いのは弛緩性便秘です。弛緩性便秘は、運動不足や生活習慣の乱れにより、腸のぜん動運動が弱くなることで起こります。
私たちの腸内にはおよそ100兆個の腸内細菌が存在し、その種類は善玉菌・悪玉菌・どちらでもない中間の菌の3つに分かれます。悪玉菌は肥満・糖尿病・腸の疾患などと関連のある腸内細菌で、便秘は悪玉菌を増やす要因の一つとなるため注意しましょう。
-
過敏性腸症候群
便秘や下痢のほかに、慢性的な腹痛や膨張感がある場合は、過敏性腸症候群かもしれません。過敏性腸症候群は、ストレスや不規則な生活、食生活の乱れなどが要因となり、腸が刺激に対して過敏になっている状態です。
1-2.【胃】不調の原因と症状
胃のおもな不調として挙げられるのは、胃炎や機能性ディスペプシアでしょう。
-
急性胃炎と慢性胃炎
急性胃炎は、急に胃の粘膜が炎症を起こす病気です。おもな原因には、過食やストレス、アレルギーなども挙げられます。
一方の慢性胃炎は、胃の粘膜が度々炎症を起こす病気です。おもな原因はピロリ菌への感染とされていますが、加齢や喫煙などでも起こります。
なお、ピロリ菌は全世界でおよそ半数の人が感染している細菌です。ピロリ菌に感染しても多くの場合は無症状ですが、胃痛や胃もたれだけでなく、慢性胃炎や十二指腸潰瘍などを引き起こすことがあるので注意しましょう。 -
機能性ディスペプシア
胃の調子が悪いのに、検査をしても特に異常が見られない場合は、機能性ディスペプシアを疑ったほうがよいでしょう。胃の不調で医療機関を受診する人の約50%は、機能性ディスペプシアと診断されることが多いようです。
おもな原因は、ストレスや不規則な生活習慣、胃の働きの低下とされています。
1-3.【肝臓】不調の原因と症状
肝臓は、胃や腸から吸収した栄養素を蓄えたり、有害物質やアルコールの分解を行なったりする働きを持つ臓器です。食べ過ぎや節度を超えた過度の飲酒、運動不足、睡眠不足、ストレス、喫煙などは肝臓の負担となりやすいため、不調の要因といえるでしょう。
食べ過ぎや節度を超えた過度の飲酒などで肝臓に中性脂肪がたまると起こるのが、脂肪肝です。脂肪肝は症状が出ないことが多いものの、放置すると肝炎や肝硬変へと進行するおそれがあります。
なお、肝炎の症状は種類によって異なり、過食や生活習慣などが原因の非アルコール脂肪性肝炎は自覚症状がほとんどありません。一方、節度を超えた過度の飲酒が原因となるアルコール性肝炎は、体のだるさや食欲不振、発熱、腹部右上が痛むなどの症状が見られます。また、肝硬変では、黄疸や吐血、腹水などの症状が現れます。
「沈黙の臓器」とも呼ばれる肝臓では、気付かないうちに病気が進行していることもあるため、定期健診を受けたほうがよいでしょう。


 五臓六腑とも言いますが、内臓は健康を保つうえで大切な臓器です。例えば消化管の不調で、便秘や胃痛など慢性的に抱えている人も少なくないでしょう。
五臓六腑とも言いますが、内臓は健康を保つうえで大切な臓器です。例えば消化管の不調で、便秘や胃痛など慢性的に抱えている人も少なくないでしょう。 腸や胃、肝臓などの内臓を健康な状態にする方法を、それぞれ紹介します。
腸や胃、肝臓などの内臓を健康な状態にする方法を、それぞれ紹介します。