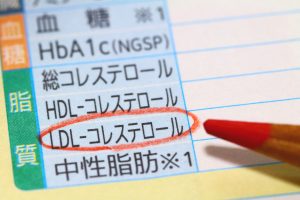1.コレステロールとは
コレステロールとは、私たちの体内に存在する脂質の一種で、細胞膜やホルモンなどのもととなります。一般的には、体に悪いものだと思われているかもしれませんが、体にとっては欠かせません。
コレステロールはおもに体内で合成され、食事から取り入れる量は全体の約20~30%です。
ただし、合成量と摂取量は体内でうまく調整され、食事からコレステロールを多くとった場合は肝臓での合成が減少し、摂取量が少なければ合成が増えるようになっています。そのため、通常は食事からの摂取量が、血中コレステロール値にそのまま反映されるわけではありません。
2.コレステロールの種類と役割
コレステロールには、いくつか役割が違うものが存在しています。一般的によく知られている2種類の役割について見ていきましょう。
2-1.LDL(悪玉)コレステロール
LDLコレステロールは、肝臓でつくられたコレステロールを全身へ運ぶ働きがありますが、増えすぎると血管内皮への炎症などを引き起こします。そのため、一般的に悪玉コレステロールと呼ばれています。
2-2.HDL(善玉)コレステロール
HDLコレステロールは、体内の過剰なコレステロールや、血管の壁に溜まったコレステロールを回収し、肝臓へ戻す働きがあります。LDLコレステロールとは逆に、善玉コレステロールと呼ばれています。
3.脂質異常症との関係
 ここでは、コレステロールが深く関わっている脂質異常症について紹介します。
ここでは、コレステロールが深く関わっている脂質異常症について紹介します。
3-1.脂質異常症とは
脂質異常症とは、食事からの脂質量が過剰だったり、体内の脂質の処理がうまく行なわれなかったりして血液中の脂質が基準値外になる疾患です。主に「LDLコレステロールが高すぎるタイプ」「HDLコレステロールが低すぎるタイプ」「中性脂肪が多すぎるタイプ」の3種類が存在します。
中性脂肪は体のエネルギー源となりますが、増えすぎると脂肪肝や肥満につながり、生活習慣病の要因となります。
3-2.コレステロールの正常範囲
脂質異常症には診断基準があり、LDLコレステロールの正常範囲は140mg/dL未満で、140mg/dL以上の場合は高LDLコレステロール血症とされています。
そして、一般的にHDLコレステロールの正常範囲は40mg/dL以上となり、40mg/dL未満の場合は低HDLコレステロール血症です。
ただし、これらの数値が正常範囲外であっても、すぐに治療が必要とは限りません。
3-3.脂質異常症のリスク
脂質異常症そのものはあまり自覚症状がなため、放置してしまうことも少なくありません。
放置したままにしてしまうと血中のLDLコレステロール量が過剰になってしまい、血管の壁にたまってしまいます。しかし、HDLコレステロールが少ないと、これらの余分なコレステロールが回収されないため、蓄積して血管の幅が狭くなります。
4.コレステロール値を下げるのに効果的とされる食べ物
 LDLコレステロールが高くなる原因として、バターや生クリーム、肉の脂身、加工食品などに含まれる飽和脂肪酸のとりすぎが挙げられます。また、卵黄や魚卵など、コレステロールを多く含む食品もとりすぎないように注意しましょう。
LDLコレステロールが高くなる原因として、バターや生クリーム、肉の脂身、加工食品などに含まれる飽和脂肪酸のとりすぎが挙げられます。また、卵黄や魚卵など、コレステロールを多く含む食品もとりすぎないように注意しましょう。
豆腐や納豆などの大豆製品に含まれている大豆たんぱくには、体内のコレステロール吸収を抑制する働きがあるとされています。また、サバ・サンマなどの青魚やオリーブオイルに含まれる不飽和脂肪酸には、LDLコレステロールを減らす作用が期待できます。そのため、こういった食品を日々の食事に取り入れるとよいでしょう。
コレステロールの数値に注意しましょう
コレステロールは人体において大切な成分ですが、体内で増えすぎるとあらゆる病気を引き起こす原因になります。
そのため、増えすぎないように食事などで抑えることが大切です。LDLコレステロールを増加させる飽和脂肪酸やコレステロールを控え、大豆たんぱくや不飽和脂肪酸を摂取しましょう。
日々を健やかに過ごすために、ぜひ食事内容を見直してみてください。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


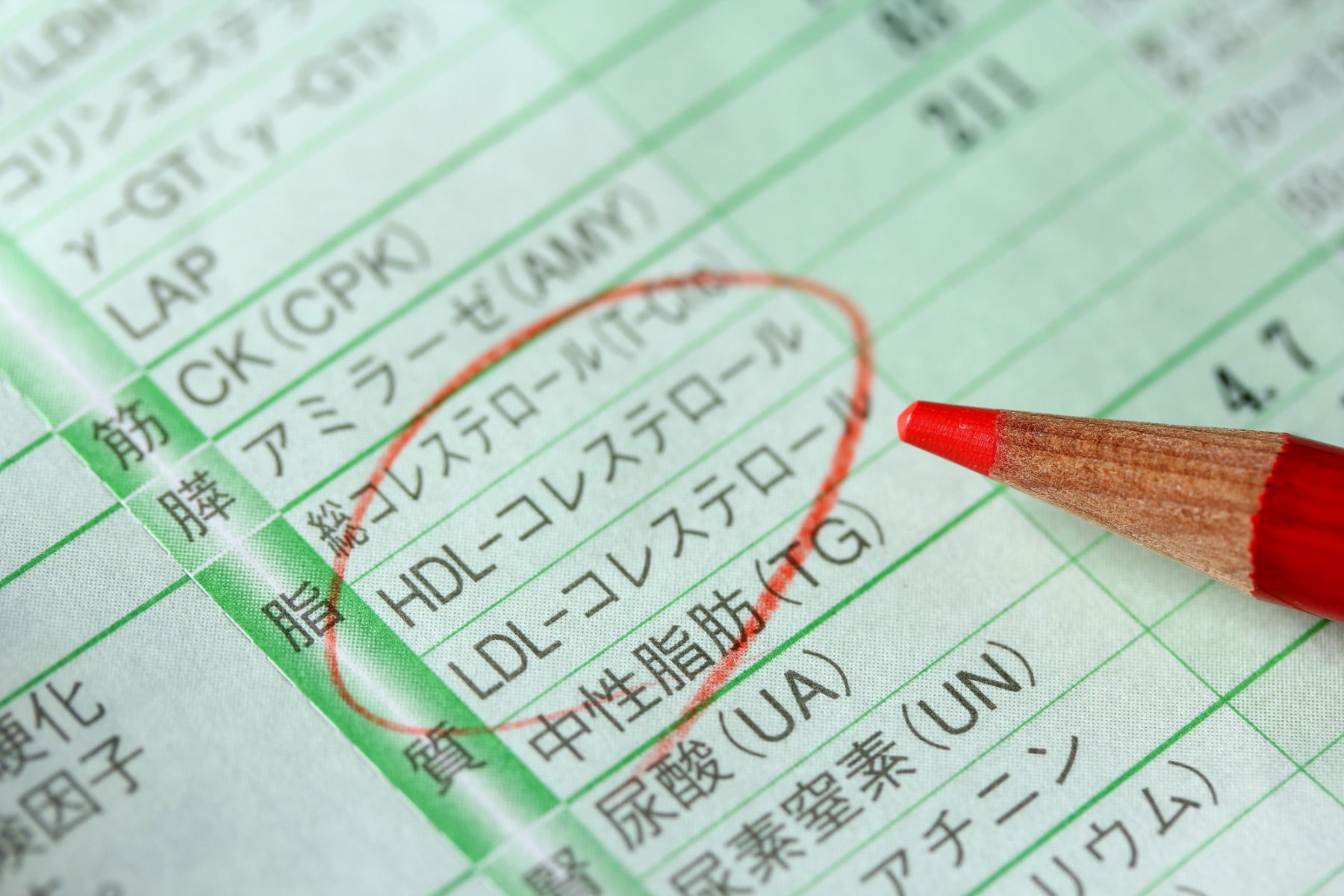 「コレステロールは体に良くないもの」というイメージを持っている人も多いかもしれませんが、実は体にとってなくてはならない物質です。ただし、なかには増えすぎると体に悪影響をおよぼすものも存在します。
「コレステロールは体に良くないもの」というイメージを持っている人も多いかもしれませんが、実は体にとってなくてはならない物質です。ただし、なかには増えすぎると体に悪影響をおよぼすものも存在します。 ここでは、コレステロールが深く関わっている脂質異常症について紹介します。
ここでは、コレステロールが深く関わっている脂質異常症について紹介します。 LDLコレステロールが高くなる原因として、バターや生クリーム、肉の脂身、加工食品などに含まれる飽和脂肪酸のとりすぎが挙げられます。また、卵黄や魚卵など、コレステロールを多く含む食品もとりすぎないように注意しましょう。
LDLコレステロールが高くなる原因として、バターや生クリーム、肉の脂身、加工食品などに含まれる飽和脂肪酸のとりすぎが挙げられます。また、卵黄や魚卵など、コレステロールを多く含む食品もとりすぎないように注意しましょう。