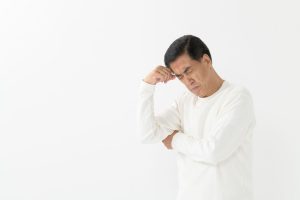1.加齢臭は40代くらいから強くなる
 加齢臭は40代頃から強くなるとされていますが、なぜなのでしょうか。ここでは、40代以降で加齢臭が強くなる原因と仕組みについて解説します。
加齢臭は40代頃から強くなるとされていますが、なぜなのでしょうか。ここでは、40代以降で加齢臭が強くなる原因と仕組みについて解説します。
1-1.40代から加齢臭が強くなる原因
加齢臭は、ノネナールという物質が原因で発生します。この物質は40歳を過ぎた頃から急激に増加する傾向にあり、このことが40代から加齢臭が強くなることに関係しているといえるでしょう。
ノネナールは、全身から分泌される物質です。特に、耳の裏・首の周り・背中・わきの下などから分泌されるため、ふとんや枕が臭いやすくなります。
また、一年中発生する物質のため、毎日しっかりケアすることが大切です。皮脂から発生するノネナールは脂溶性のため水に溶けにくく、シャワーや入浴だけでは落とすのが難しいといわれています。
1-2.ノネナールが発生する仕組み
ノネナールは、皮脂に含まれるヘキサデセン酸という臭い物質の原因が発生し、皮膚に存在する常在菌がヘキサデセン酸を分解することで発生します。
皮膚常在菌とは、皮膚にもともと住んでいる菌のことです。発生したノネナールが皮膚の表面で特有の臭いを放つため、加齢臭が気になるようになります。
ヘキサデセン酸は年齢とともに増える傾向にあり、特に40歳から量が多くなるとされています。ノネナールも40歳頃から増えるため、ヘキサデセン酸が増加するとノネナールの発生量も増加しやすいと考えられるでしょう。
ヘキサデセン酸は皮脂に含まれるため、過剰な皮脂分泌を抑える生活習慣や皮脂対策を行なうことが大切です。
2.加齢臭が発生しやすい生活習慣
加齢臭が発生する原因がわかったところで、ここでは加齢臭が発生しやすい生活習慣について解説します。
次のような習慣があると、加齢臭の原因となる皮脂が出やすくなるとされています。
-
・焼肉やマヨネーズなどの脂っこい食事を好む
-
・喫煙習慣がある
-
・運動不足である
-
・強いストレスを感じている
脂質の多い食事は皮脂の分泌を増やすため、加齢臭の原因となるノネナールの発生量を増やします。
年齢によるノネナールの増加は避けられませんが、少しでもノネナールの発生を抑えるには上記のような生活習慣を避けたほうがよいでしょう。
3.加齢臭がしない人の特徴とは?
 加齢臭がしない人は、どのような生活をしているのでしょうか。ここでは、加齢臭がしない人の特徴について解説します。
加齢臭がしない人は、どのような生活をしているのでしょうか。ここでは、加齢臭がしない人の特徴について解説します。
3-1.健康的な生活をしている
加齢臭がしない人は、健康的な食事や生活習慣を心がけていることが多いでしょう。
例えば、次のような生活です。
-
・脂質の摂り過ぎに注意する
-
・運動習慣を身につける
-
・タバコを吸わない
-
・自分なりのストレス解消法を見つける
ノネナールの原因となる皮脂を控え、健康的な食生活をしている人は、加齢臭が発生しにくい傾向にあります。また、適度に運動をしたり、タバコを吸わないようにしたり、ストレスを溜めないようにしたりすることも、加齢臭対策には重要です。
3-2.正しい臭いケアをしている
入念に全身を洗っている人は、ノネナールがしっかり洗い流されるため、加齢臭がしにくいでしょう。
体を洗う際には、石鹸をたっぷり泡立てて、皮脂や汗が発生しやすい部分を中心に洗うことが大切です。特に、耳の裏・首周辺・胸・脇の下・背中などは入念に洗うことをおすすめします。
皮脂や汗などをそのままにしておくと、皮膚の表面で菌が繫殖して臭いが発生しやすくなるため、臭い対策として丁寧に体を洗うことが重要です。
加齢臭対策で臭わない人を目指そう
年齢を重ねるごとに発生する加齢臭は女性よりも男性のほうが臭いやすく、特に40代以降の中高年になると、加齢臭が強くなる傾向にあります。
加齢臭は、皮脂から発生するノネナールが原因であるため、皮脂の過剰分泌が起こらないように、健康的な食事や生活習慣を心がけることが大切です。
また、たっぷりの泡で全身を入念に洗い、臭いの原因をしっかり洗い流すことも加齢臭対策として有効といえます。毎日、全身を丁寧に洗い、清潔な状態に保ちましょう。
臭わない人を目指し、日々しっかりと加齢臭対策を行なうことをおすすめします。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
 加齢臭は40代頃から強くなるとされていますが、なぜなのでしょうか。ここでは、40代以降で加齢臭が強くなる原因と仕組みについて解説します。
加齢臭は40代頃から強くなるとされていますが、なぜなのでしょうか。ここでは、40代以降で加齢臭が強くなる原因と仕組みについて解説します。


 加齢臭とは、中高年で発生しやすくなる体臭のことです。自分では加齢臭に気付かないという人もいるかもしれませんが、一緒に住む家族は意外と臭いが気になっていることも。
加齢臭とは、中高年で発生しやすくなる体臭のことです。自分では加齢臭に気付かないという人もいるかもしれませんが、一緒に住む家族は意外と臭いが気になっていることも。 加齢臭がしない人は、どのような生活をしているのでしょうか。ここでは、加齢臭がしない人の特徴について解説します。
加齢臭がしない人は、どのような生活をしているのでしょうか。ここでは、加齢臭がしない人の特徴について解説します。