目次
1.マカとは?
マカとはペルーのアンデス山地に生育している植物で、原産地のペルーから世界各国に輸出されています。
マカは強い日差しや強風、低温など、人間にとっては過酷な環境でも成長できる強靭な植物です。使われるのはおもに根の部分で、白や黒、ピンク、赤、黄などさまざまな色が存在します。
中高年の活力維持を目的としたサプリメントの材料に使用されることが知られていますが、そのまま野菜として使われることも少なくありません。例えば、スープにしたり、発酵飲料として飲まれたりします。
 マカは「いつまでも元気な体でいたい」という男性から注目を浴びる植物です。ドラッグストアや通信販売などでもマカのサプリメントを見かける方も多いのではないでしょうか。
マカは「いつまでも元気な体でいたい」という男性から注目を浴びる植物です。ドラッグストアや通信販売などでもマカのサプリメントを見かける方も多いのではないでしょうか。
精力増強などのイメージが強いマカですが、具体的にどのような効果があるのか知らない方も多いでしょう。今回は、マカに含まれている成分や期待される効果を解説します。
目次
マカとはペルーのアンデス山地に生育している植物で、原産地のペルーから世界各国に輸出されています。
マカは強い日差しや強風、低温など、人間にとっては過酷な環境でも成長できる強靭な植物です。使われるのはおもに根の部分で、白や黒、ピンク、赤、黄などさまざまな色が存在します。
中高年の活力維持を目的としたサプリメントの材料に使用されることが知られていますが、そのまま野菜として使われることも少なくありません。例えば、スープにしたり、発酵飲料として飲まれたりします。
 マカは多くの成分を含む植物です。おもな成分としては、以下が挙げられます。
マカは多くの成分を含む植物です。おもな成分としては、以下が挙げられます。
・リノレン酸
・パルミチン酸
・オレイン酸
・必須アミノ酸
・カルシウム
・銅
・グルコシノレート類
・イソチオシアネート類
・ステロール
・不飽和脂肪酸
・アルカロイド類(レピリジンA、マカリジンなど)
・アミド誘導体(マカミドA、N-ベンジル-9-オキソ-12など)
気温差が激しいアンデスの高地で育つマカは、大地の栄養をあますことなく吸収して、さまざまな成分を含んでいます。
マカに含有される必須アミノ酸は、人間の体内で作ることができません。アミノ酸はたんぱく質を合成するために必要なもので、エネルギーを産出する栄養素の一つです。必須アミノ酸には、イソロイシンやロイシン、トリプトファン、メチオニンなどがあります。
また、不飽和脂肪酸は、体に良い油として注目されている脂肪酸です。不飽和脂肪酸の一つであるオレイン酸は、オリーブ油に多く含まれています。
その他、リノレン酸やドコサヘキサエン酸(DHA)、イコサペンタエン酸(IPA)などもよく知られているでしょう。これらは、血液をサラサラにしたり、コレステロールを下げたりする効果が期待されています。
 マカは男性の活力を高めるうれしい働きが期待できます。ここでは、具体的な効果を見ていきましょう。
マカは男性の活力を高めるうれしい働きが期待できます。ここでは、具体的な効果を見ていきましょう。
ペルーで行なわれた試験では、マカを健康な成人男性に12週間にわたって摂取してもらったところ、性ホルモンの一つである17ヒドロキシプロゲステロンの上昇が見られました。黄体形成ホルモンや卵胞刺激ホルモンなどには影響が見られなかったため、一部の性ホルモンに特化して影響を与えると考えられるでしょう。
こちらもペルーで行なわれた試験です。健康な成人男性にマカを12週間にわたって摂取してもらったところ、性欲の改善が見られました。なお、テストステロンやエストラジオールなどの性ホルモンへの影響は確認されていません。
軽度から中程度の勃起不全患者にマカを8週間にわたり摂取してもらったところ、精神状態を表す指標のうち1つに改善が見られました。なお、この試験では勃起機能の指標や性ホルモンに変化は認められていません。
軽度の勃起不全がある患者にマカを12週間にわたり摂取してもらったところ、勃起機能の指標に改善が見られました。
マカには男性の活力維持が期待されていますが、精液の量や精子の濃度、運動性には影響がないとする試験結果もあります。そのため、マカは精液・精子の質や量に問題がない方において、一部の性ホルモンを上昇させたり、性欲・勃起の改善に期待ができます。
マカは必須アミノ酸や不飽和脂肪酸など多くの成分を含んでおり、いつまでも活力的でいたい男性のサポートによく用いられる植物です。サプリメントとして利用されるだけでなく、スープや発酵飲料の材料としても活用されています。
日中は強い日差しに、夜は氷点下の空気にさらされて育つマカの逞しさは、男性の活力に良い影響を与えるでしょう。実際、数々の試験によって性ホルモンの上昇や性欲・勃起の改善などが一部認められています。
サプリメントでマカをうまく取り入れて、日々の活力維持に役立ててみてはいかがでしょうか。

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
成分

インスタント麺やソーセージなどの加工食品に多く含まれる成分に「リン酸塩」があります。
成分
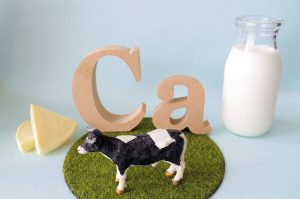
カルシウムとは、簡単にいうとミネラルの一種です。
成分

ミツバチが作り出すローヤルゼリーは、それを食する女王蜂の生命力を支える高栄養食です。
成分

みなさんは、ヘム鉄と呼ばれる成分を知っていますか? 鉄には、大きく分けて肉や魚などの動物性食品に含まれるヘム鉄と野菜や大豆などの植物性食品に含まれる非ヘム鉄があります。
成分

たんぱく質は、エネルギーをつくりだして筋肉や皮膚・髪など体を構成するために重要な栄養素です。