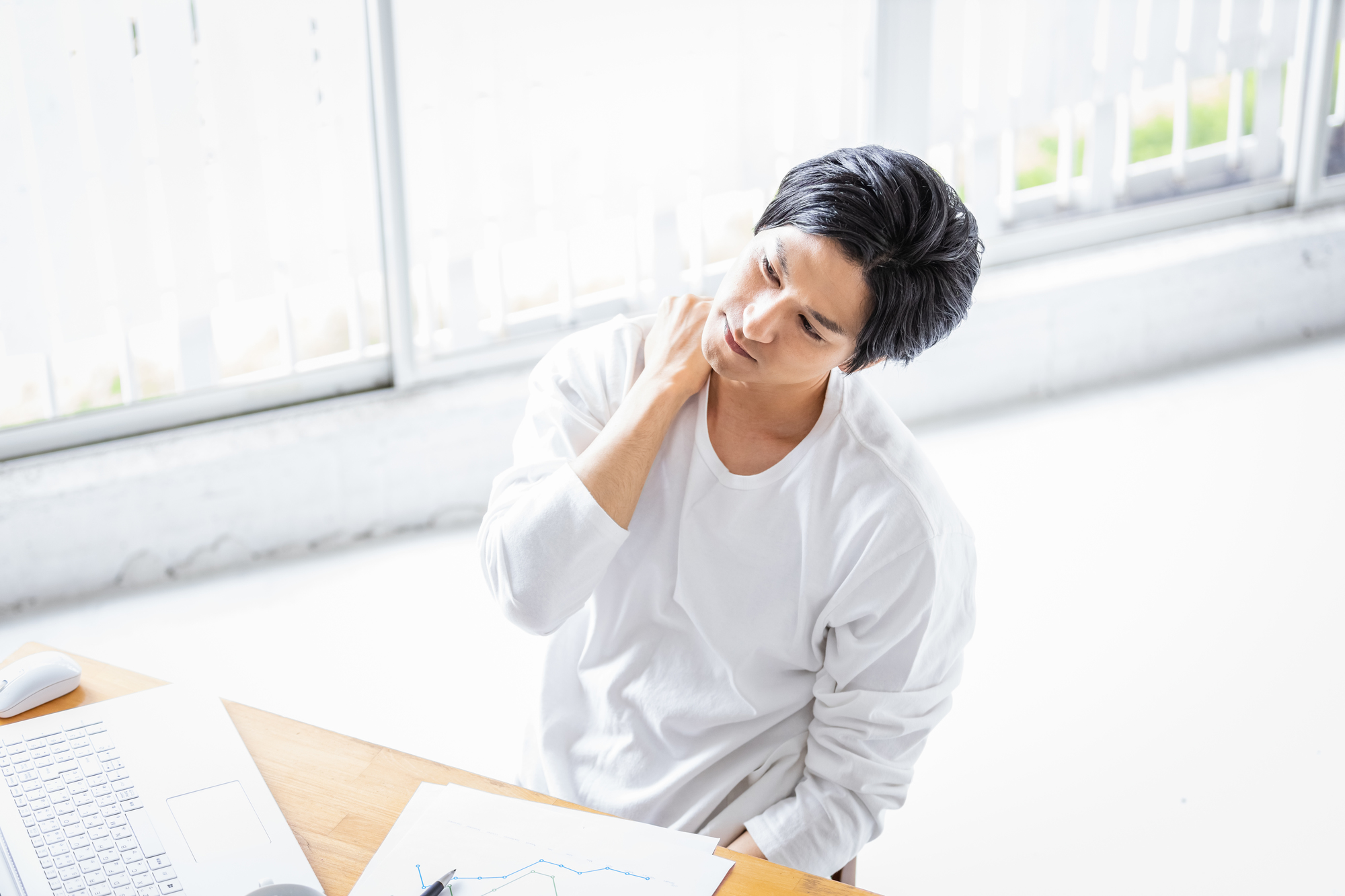1.タンパク質とは
タンパク質は、炭水化物や脂質とともに、体の基礎を構成する役割を担っています。生体乾燥重量の50%を占める栄養素であり、生命の維持に欠かすことができません。そのため、タンパク質は体づくりにおいてとても重要な存在といえます。
また、タンパク質は20種類のアミノ酸が結合した高分子化合物であり、そのうち9種類のアミノ酸である「必須アミノ酸」は体内で作ることができませんので、食事から摂取する必要があるのです。
なお、残り11種類のアミノ酸は「非必須アミノ酸」と呼ばれ、体内で生成することができます。これら20種類のアミノ酸が、一つでも欠けるとタンパク質が合成できないのです。
1-1.アミノ酸の種類
「必須アミノ酸」と「非必須アミノ酸」の種類は以下の通りです。
| 必須アミノ酸 |
バリン、ロイシン、イソロイシン、スレオニン、メチオニン、リジン、フェニルア、ラニン、トリプトファン、ヒスチジン |
| 非必須アミノ酸 |
グリシン、アラニン、グルタミン酸、グルタミン、セニン、アスパラギン酸、アスパラギン、チロシン、システイン、アルギニン、プロリン |
2.タンパク質の主な働き(役割)
体内に取り込まれたタンパク質は、アミノ酸に分解・吸収され、体に必要なタンパク質を再合成します。また、酵素やホルモンとして健康維持のためにさまざまな働きをし、ヘモグロビン、アルブミン、トランスフェ リン、アポリポタンパク質などは物質輸送に関与しています。体にとって重要な栄養素です。
3.一日に必要な摂取量(目安)
一日のタンパク質摂取の推奨量は、成人男性で約60g、成人女性で約50gとなります。これは一日の摂取エネルギーの約13%~20%に相当します。以下が年代別の一日に必要なタンパク質の摂取量の目安となりますので、ぜひ自身の年齢の推定平均必要量や推奨量を確認してみてください。
|
男性 |
女性 |
| 年齢(歳) |
推定平均必要量 (単位:g) |
推奨量 (単位:g) |
推定平均必要量 (単位:g) |
推奨量 (単位:g) |
| 1~2 |
15 |
20 |
15 |
20 |
| 3~5 |
20 |
25 |
20 |
25 |
| 6~7 |
25 |
30 |
25 |
30 |
| 8~9 |
30 |
40 |
30 |
40 |
| 10~11 |
40 |
45 |
40 |
50 |
| 12~14 |
50 |
60 |
45 |
55 |
| 15~17 |
50 |
65 |
45 |
55 |
| 18~29 |
50 |
65 |
40 |
50 |
| 30~49 |
50 |
65 |
40 |
50 |
| 50~64 |
50 |
65 |
40 |
50 |
| 65~74(※) |
50 |
60 |
40 |
50 |
| 75以上(※) |
50 |
60 |
40 |
50 |
※厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を元に作成
※65 歳以上の場合、体づくりのサポートを目的とした量を定めることは難しく、身長・体重が参照体位に比べて小さい方や、特に 75 歳以上であって加齢に伴い身体活動量が大きく低下した方など、必要エネルギー摂取量が低い方では、下限が推奨量を下回る場合があります。これらの場合でも、下限は推奨量以上とすることが望ましいとされています。
4.タンパク質不足によって引き起こされる体の症状
タンパク質が不足する原因として、食事や運動不足などが挙げられます。では、タンパク質が不足すると体にどのような影響が出るのでしょうか。
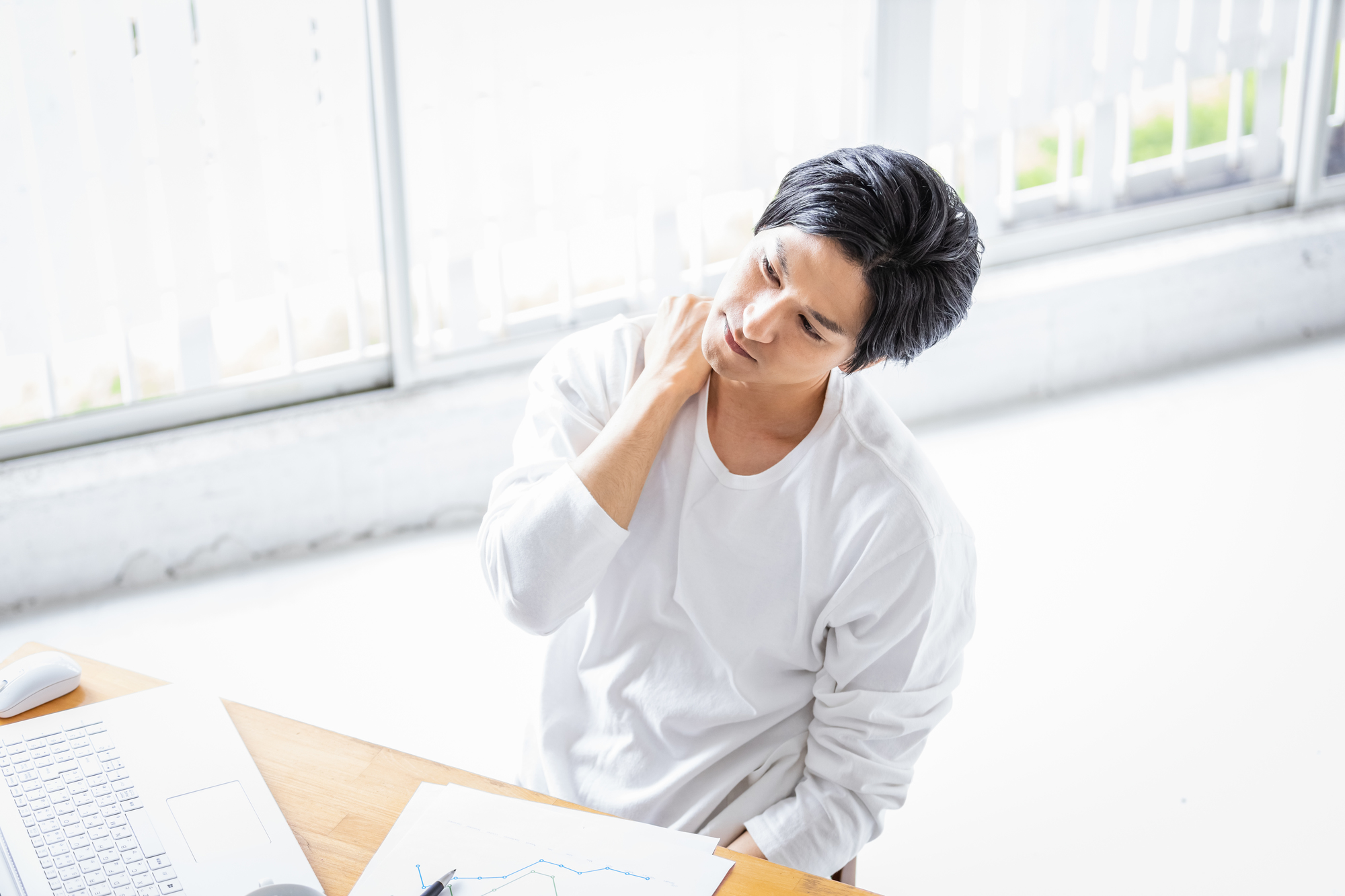
4-1.免疫機能や集中力の低下
タンパク質には、酵素やホルモンなど体の機能を調節する役割があります。そのため、タンパク質が不足すると免疫機能が低下し、抵抗力も弱くなってしまいます。
また、脳内の神経伝達物質はアミノ酸からできているので、タンパク質と深い関わりを持っています。やる気を出し前向きな気分にしてくれるドーパミンや、精神を安定する働きのあるセロトニンが神経伝達物質です。タンパク質が不足すると、神経伝達物質の分泌が鈍くなり、集中力が低下してしまいます。
4-2.筋力の低下
タンパク質は筋肉を作るための栄養素です。タンパク質不足が続くと、筋肉量が減ることが考えられます。若年層の方にとっては、筋肉量が減ることによる日常生活への支障はあまり考えられませんが、高齢者の方は自力で立ち上がることが困難になるなどの可能性が考えられます。
4-3.タンパク質の過剰摂取について
摂取したタンパク質は、体内で合成と分解を繰り返します。過剰摂取によって余ってしまったタンパク質は、分解されて窒素になります。
窒素は体内では有害な物質なので、肝臓で無害な尿素に変換され、腎臓を経て尿として排出されます。タンパク質を過剰摂取すると、有害物質を無害化する働きが必要になるため、腎臓などに負担が掛かってしまいます。
タンパク質不足によって引き起こされる不調はありますが、過剰摂取によって招かれるリスクもあるため、適量を摂るよう心がけましょう。
5.タンパク質が多く含まれる食品
以下は、タンパク質が多く含まれる食品例となります。ぜひ日ごろの食生活で取り入れることを意識してみてください。タンパク質不足が心配な方は、肉類・魚類・卵・大豆類・乳製品類を意識して摂ることをおすすめします。
| 食品例 |
成分量100gあたりのタンパク質含有量(g) |
| 豚肉などの畜肉類など |
87.6 |
| 卵類、鶏卵、卵白、乾燥卵白など |
86.5 |
| 乳類(牛乳及び乳製品)など |
86.2 |
| かつお節など |
77.1 |
| とびうお、煮干しなど |
80.0 |
| 豆類、大豆など |
79.1 |
| 鮭(サケ)、鱒(マス)など |
77.4 |
| 鰹(カツオ)、鰹節(カツオブシ)など |
77.1 |
※文部科学省「食品成分データベース」を元に作成
タンパク質を上手に摂るには高タンパク低カロリーの食事を心がけてみましょう
タンパク質を上手に摂るには、バランスのとれた食事が大切です。必須アミノ酸が多く、体内吸収率のよい肉や魚などの動物性タンパク質と、大豆や小麦などの低カロリーの植物性タンパク質をバランスよく摂りましょう。ただしタンパク質ばかりを意識すると高カロリーな食事になってしまうこともあるため、高タンパク低カロリーの食事を心がけることが大切です。
また、規則正しい生活と適度な運動をあわせて行い、健康的な体づくりを目指していきましょう。
監修者情報

氏名:河村優子(かわむら・ゆうこ)
アンチエイジングをコンセプトに体の中と外から痩身、美容皮膚科をはじめとする様々な治療に取り組む医師。海外の再生医療を積極的に取り入れて、肌質改善などの治療を行ってきたことから、対症療法にとどまらない先端の統合医療を提供している。