目次
1.コンドロイチンとは?
コンドロイチンとは、フカヒレなどにも多く含まれているサメ軟骨の成分です。保水力がありネバネバしていることから、ひざ関節にある軟骨を守る働きがある成分として注目されています。
しかし、私たちの体内にあるコンドロイチンは、加齢とともに減少してしまいます。そのうえ、体内では合成されにくいため、食品などで外から補うことが大切です。
 関節の軟骨を守る働きがあるとして、ひざに悩みを抱える方が摂取していることの多いコンドロイチン。
関節の軟骨を守る働きがあるとして、ひざに悩みを抱える方が摂取していることの多いコンドロイチン。
今回は、このコンドロイチンが具体的に体内でどのような働きをしているのかを解説します。関節軟骨との関係性なども詳しく解説するので、ぜひご覧ください。
目次
コンドロイチンとは、フカヒレなどにも多く含まれているサメ軟骨の成分です。保水力がありネバネバしていることから、ひざ関節にある軟骨を守る働きがある成分として注目されています。
しかし、私たちの体内にあるコンドロイチンは、加齢とともに減少してしまいます。そのうえ、体内では合成されにくいため、食品などで外から補うことが大切です。
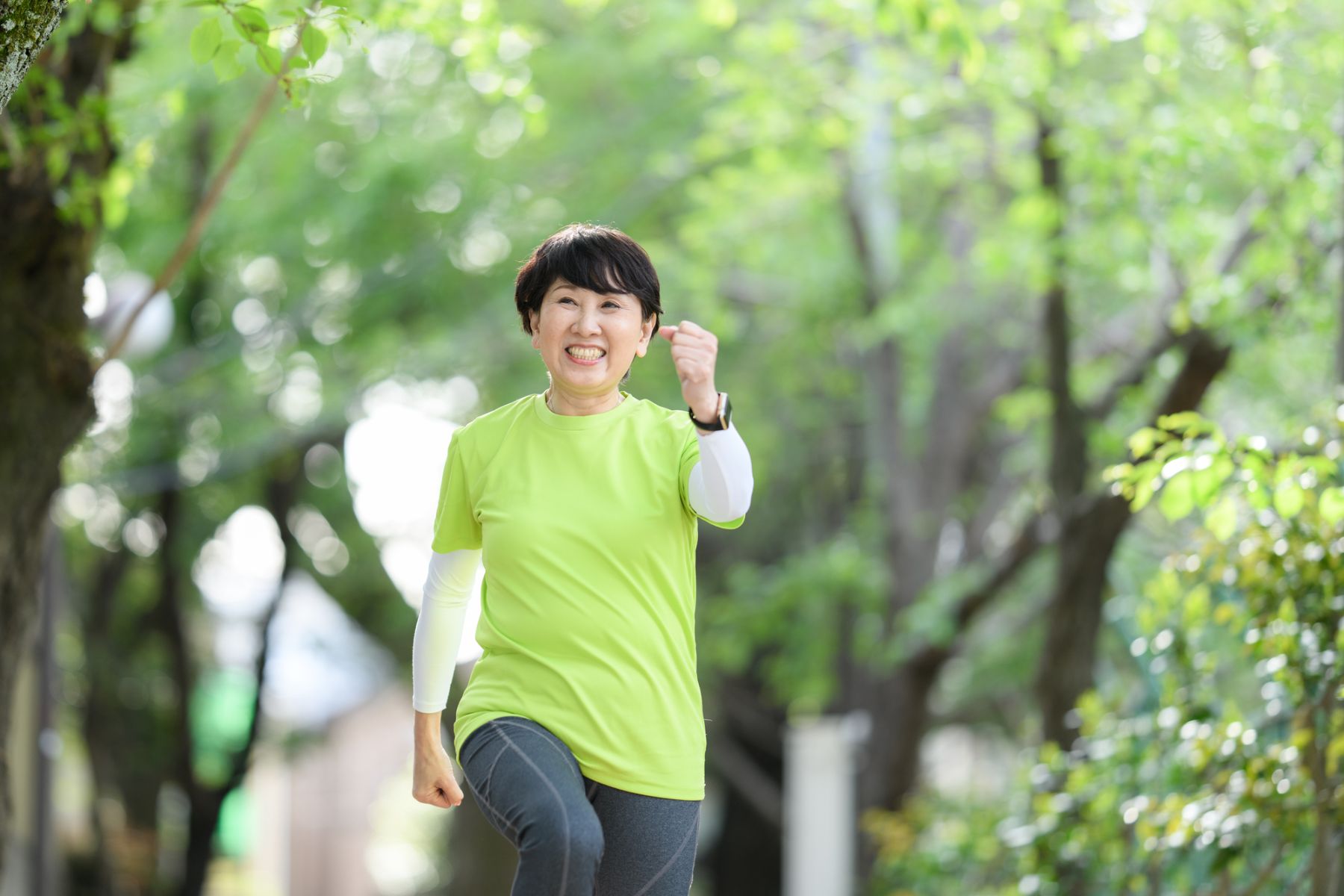 では、コンドロイチンがなぜ関節軟骨に良いといわれているのでしょうか。関節軟骨の構造や仕組みを見ながら、確認していきましょう。
では、コンドロイチンがなぜ関節軟骨に良いといわれているのでしょうか。関節軟骨の構造や仕組みを見ながら、確認していきましょう。
関節軟骨とは、ひざの骨の端を覆っているもののことで、その厚さは3~5ミリメートルです。
とても薄い構造ではありますが、走るときなどに骨が受ける衝撃をやわらげたり、関節の曲げ伸ばしをする際の摩擦を防いだりする働きがあります。関節軟骨がなければ、私たちは走ったり屈伸したりすることが難しくなってしまうでしょう。
この関節軟骨は、コラーゲン繊維が網目状に広がった形をしています。強靱なコラーゲン繊維にプロテオグリカンという成分がしっかり絡みつくことで、軟骨細胞を守っているのです。
プロテオグリカンは、ヒアルロン酸やコンドロイチン硫酸、コアたんぱくなどが結び付いてできあがっています。関節軟骨を構成するプロテオグリカンにコンドロイチンが含まれていることから、コンドロイチンは関節の働きと密接な関係があると考えられるでしょう。
関節をスムーズに動かすためには、関節の主成分であるプロテオグリカンの働きが欠かせません。
関節軟骨には血管が通っておらず、血液から栄養素を吸収できないため、代わりに関節液から栄養素を吸収しています。関節軟骨が関節液から栄養素を吸収することで柔軟性や緩衝性が維持でき、関節を滑らかに動かせるようになります。
関節軟骨が栄養素を吸収する際にサポートしているのが、プロテオグリカンです。プロテオグリカンは、水分と結合しやすい性質を持っています。この性質によって、プロテオグリカンは関節液に含まれる水分と栄養素を保持し、関節軟骨に栄養素を与えているのです。なお、関節軟骨が栄養素などを吸収するのは、ひざを曲げ伸ばしするたびに行なわれています。
柔軟性や緩衝性に関してですが、歩いたり走ったりして関節に圧力がかかると、保持していた水分がプロテオグリカンから放出されます。すると、関節軟骨が圧力に応じて変形し、うまく力を分散してくれるのです。
関節を動かすうえでは、プロテオグリカンだけでなく、軟骨下骨という関節軟骨の下にある組織の働きも重要になります。軟骨下骨は、関節軟骨にかかった圧力をうまく受け止めてくれる存在です。
 ひざに痛みが生じる疾患として、変形性ひざ関節症が知られています。初期段階では、関節軟骨に小さな傷が付いたり、軟骨が変性したりするなどの症状が見られるでしょう。
ひざに痛みが生じる疾患として、変形性ひざ関節症が知られています。初期段階では、関節軟骨に小さな傷が付いたり、軟骨が変性したりするなどの症状が見られるでしょう。
たびたび、ひざ関節に大きな負担がかかることで起こるものですが、初期段階ではあまり自覚症状がありません。そのため、気付かないうちにプロテオグリカンが失われ、関節軟骨が少しずつすり減っていきます。
さらに症状が進行すると、ひざが変形したり、関節に水がたまったりするなどの症状が目立つようになるでしょう。関節軟骨が完全にすり減ると、強い痛みが出て出歩くのが難しいほどにまで症状が進行します。日常生活にも支障が出てくるため、早めの対応が肝心です。
コンドロイチンは、サメの軟骨などに多く含まれていますが、人間の関節の働きとも密接な関係がある成分です。
ひざ関節にある関節軟骨は、走るときなどの衝撃をやわらげる働きがあり、強靱なコラーゲン繊維にプロテオグリカンが絡みつくことで機能を維持しています。このプロテオグリカンには、コンドロイチン硫酸をはじめとした成分が結合していることから、コンドロイチンは関節軟骨の働きに重要な役割をはたしているといえるでしょう。
ひざ関節は、関節軟骨が関節液の水分や栄養素を吸収し、柔軟性や緩衝性を維持していることで滑らかに動かせています。
関節軟骨がすり減ると、変形性ひざ関節症という、ひざに痛みをともなう疾患に発展しかねないので注意しましょう。変形性ひざ関節症が進行すると、歩くのが難しいほどの痛みが発生するため、生活習慣を改善して早めに対処することが大切です。

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
成分

ビタミンは、体内ではタンパク質・脂質・炭水化物に比べると微量ではありますが、私たちにとっては健康維持のために重要な栄養素です。
成分

サプリメントなどで、アスタキサンチンという成分を目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
成分

りんごは栄養価が高く、幅広い効果を持つといわれています。
成分

インスタント麺やソーセージなどの加工食品に多く含まれる成分に「リン酸塩」があります。
成分

ビタミンAは、おもに脂肪組織や肝臓に貯蔵される脂溶性ビタミンの一種です。