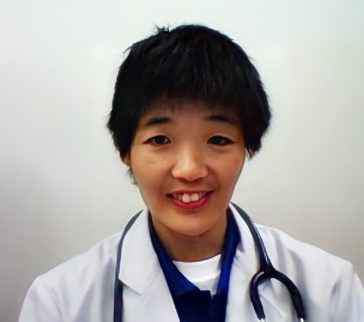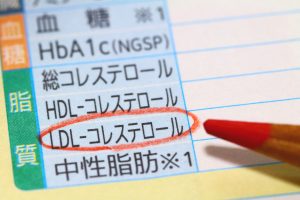1.冷え(冷え性)のおもな原因
冷え性は女性に多い症状ですが、女性ホルモンの影響や筋肉量が冷え性と関係していることもあります。ここでは、冷え性の原因について見ていきましょう。
1-1.血流の悪化
人の体は、熱を運ぶ血液が体内を流れることで体温を調整しています。そのため、血流の悪化は冷え性の大きな原因の一つといえるでしょう。
また、血液は栄養素や酸素など健康維持に必要なものを運んでおり、血流が悪くなると内臓の働きも悪くなります。それにより、免疫力が低下することもあるため注意しましょう。
1-2.筋肉量の低下
体の熱は、安静にしているときにはその多くが内臓で作られていますが、筋肉を少しでも使っているときには筋肉によって作られているものが大半を占めます。そのため、男性に比べて筋肉量が少ない女性のほうが冷え性になりやすいといえるでしょう。
筋肉は、体内に存在する臓器、組織のなかでも多くのエネルギーを消費し、基礎代謝量の22%を骨格筋が占めています。筋肉量が低下すると冷え性の原因になるだけでなく、基礎代謝量も低下して太りやすくなるので注意が必要です。
1-3.自律神経の乱れ
自律神経の乱れが冷え性の原因になることもあります。過剰なストレスによって交感神経が優位に働くと、手足の血管が収縮して血流が悪化するといわれています。
1-4.ホルモンバランスの乱れ
月経と、女性ホルモンの分泌には深い関係があります。しかし、出産や閉経などによって大きくホルモンバランスが崩れると、自律神経にも影響し血流が悪化します。
そのため、更年期を迎えた女性では、冷え性の割合が増えてくるので注意が必要です。
2.冷え(冷え性)に見られるおもな症状
 冷え性は、体のさまざまな箇所に不調をきたす可能性があります。重大な病気が隠れていることがあるので、長期間続く場合は注意が必要です。ここでは、冷え性の代表的な症状を解説します。
冷え性は、体のさまざまな箇所に不調をきたす可能性があります。重大な病気が隠れていることがあるので、長期間続く場合は注意が必要です。ここでは、冷え性の代表的な症状を解説します。
2-1.髪の毛のトラブル
髪の毛の成長に欠かせない栄養素は、血液によって運ばれているため、血流が悪化すると髪の毛の成長にも影響を与えます。冷え性を放置していると慢性的に血流が悪くなり、髪の毛がうまく成長できずに薄毛や抜け毛、白髪の原因になることもあるので注意しましょう。
2-2.肌トラブル
冷え性による血流の悪化によって、肌を作るための栄養素が十分に届かずに肌の新陳代謝が阻害されることがあります。冷え性が、肌のくすみやしみ、しわ、乾燥肌の原因になることもあるので気を付けましょう。
2-3.口の中のトラブル
歯周病・歯肉炎は、糖尿病患者や喫煙者など末梢血管の血流悪化リスクがある方の約半数に認められる症状です。血流が悪くなると、体が炎症にうまく対処できず、炎症が進行しやすくなるといわれています。
冷え性の方は血流が悪い傾向にあるため、歯周病や歯肉炎になると炎症が進行しやすいと考えられるでしょう。冷え性の方は、ぜひ口の中の健康にも気を配ってください。
2-4.目の健康のトラブル
冷え性と目は関係していないように思えますが、眼球には無数の血管が存在し、眼球に栄養を送る役割を果たしています。そのため、眼球の血流が悪化すると、疲れ目やドライアイ、老眼など、目のトラブルを招くことも考えられるでしょう。
3.冷え(冷え性)を改善する方法
 冷え性を改善するためには、生活習慣を改善したり血流を良くしたりすることが重要です。ここでは、冷え性の改善が期待できる方法を紹介します。
冷え性を改善するためには、生活習慣を改善したり血流を良くしたりすることが重要です。ここでは、冷え性の改善が期待できる方法を紹介します。
3-1.運動をして筋肉を付ける
筋肉量が少ないと体内で十分に熱を作れないため、冷えを感じやすくなります。筋トレなど負荷の高い運動だけでなく、ウォーキングなどの負荷の軽い運動でも筋力を強化する効果が期待できるので、運動を生活に取り入れてみましょう。
3-2.食事をしっかりとる
人は、食事から得る栄養素をもとに、熱を生みだしています。そのため、食事量が少なかったり、栄養が偏っていたりすると熱をうまく作れない可能性があるでしょう。冷え性の改善には、しっかりと食事をとることが重要です。
タンパク質は、糖質や脂質に比べて熱として消費される量を示す「食事誘発性熱産生量」が多いので、積極的に摂取しましょう。ただし、特定の食品や栄養素に偏ることがないよう、バランスの良い食事を心がけてください。
3-3.湯船に浸かる
入浴は、体を温める効果が期待できます。シャワーや半身浴だけでは十分に温まらないため、湯船にしっかり浸かることが大事です。ただし、長時間の入浴はのぼせるので、ぬるめの温度で10~15分くらいを目安にしましょう。
3-4.自律神経の乱れを整える
自律神経が乱れると血管が収縮するだけでなく、不安感やイライラなどの精神症状が起こる原因となります。自律神経の乱れを改善するためには、睡眠や食事など生活習慣の改善やストレス対策が重要です。
冷え性は早めの対策が大切
冷え性は、血流の悪化や自律神経・ホルモンバランスの乱れなどによって引き起こされ、放置しているとさまざまな病気の原因になる可能性があります。そのため、早めの対処が必要です。
冷え性の対策としては、筋肉量を増やす、食事をしっかり取る、湯船に浸かる、自律神経の乱れを整えるなどが挙げられます。なお、対策をしても冷え性がなかなか改善しない場合には、医療機関を受診しましょう。
監修者情報
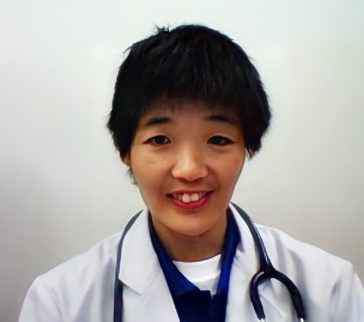
氏名:豊田早苗(とよだ・さなえ)
とよだクリニック院長。鳥取大学医学部卒。精神科・心療内科・内科・神経内科(認知症、物忘れ)の診療を担当している。総合診療医学会、認知症予防学会、精神医学会などに所属。現在は医師業務の傍ら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


 冷え性に悩まされている方は少なくないでしょう。冷え性を放置していると、さまざまな症状を引き起こすことがあるので、早めの対処が重要です。
冷え性に悩まされている方は少なくないでしょう。冷え性を放置していると、さまざまな症状を引き起こすことがあるので、早めの対処が重要です。 冷え性は、体のさまざまな箇所に不調をきたす可能性があります。重大な病気が隠れていることがあるので、長期間続く場合は注意が必要です。ここでは、冷え性の代表的な症状を解説します。
冷え性は、体のさまざまな箇所に不調をきたす可能性があります。重大な病気が隠れていることがあるので、長期間続く場合は注意が必要です。ここでは、冷え性の代表的な症状を解説します。
 冷え性を改善するためには、生活習慣を改善したり血流を良くしたりすることが重要です。ここでは、冷え性の改善が期待できる方法を紹介します。
冷え性を改善するためには、生活習慣を改善したり血流を良くしたりすることが重要です。ここでは、冷え性の改善が期待できる方法を紹介します。