1.ご飯(白米)などの炭水化物のはたらき
 炭水化物が不足すると、肝臓や筋肉中に蓄えられているグリコーゲンが消費され、エネルギーが欠乏して、疲れやすくなってしまいます。
炭水化物が不足すると、肝臓や筋肉中に蓄えられているグリコーゲンが消費され、エネルギーが欠乏して、疲れやすくなってしまいます。
特に脳は、炭水化物のなかに含まれるブドウ糖を唯一のエネルギー源としていることから、炭水化物が不足になると神経や脳へ栄養が届かなくなります。判断力や注意力が低下することになりかねないため、きちんと一日の摂取量を把握しましょう。
1-1.炭水化物とは?
炭水化物は、脂質やタンパク質とともに「エネルギー産生栄養素」と呼ばれている物質です。これら3つの栄養素は、ヒトの体に必須の成分として「三大栄養素」とされています。
炭水化物は、体内でエネルギーとなる糖質と、ヒトの消化酵素では消化吸収できずエネルギーにならない食物繊維の2つに大きく分けられます。
なお、糖質とは、果糖やブドウ糖などの単糖で構成されるであり、体内に吸収されてエネルギーとなるもののことです。でんぷんやショ糖などの糖質は、体内で1gにつき4kcalのエネルギーを生み出します。
糖質はさらに、ブドウ糖や果糖などのそれ以上は分解されない単糖類、2~10数個の単糖で構成されたショ糖や乳糖などの少糖類、それ以上の数の単糖で構成されるでんぷんやグリコーゲンなどの多糖類に分けられます。
1-2.炭水化物のはたらき
炭水化物は、体内でエネルギーを生み出して体を動かしたりするはたらきがあります。また、炭水化物が分解されてできるブドウ糖は、脳の唯一のエネルギー源です。
1-3.炭水化物の一日の摂取目安量
炭水化物の一日の摂取目安量は、食事から摂取するエネルギーをもとに定められています。
男女ともに、食事から得るエネルギーのうち50~65%にあたる量が、炭水化物の一日の摂取目安量です。具体的な重さで表すと、一日250~325gが目安となるでしょう。
2.ご飯(白米)に含まれる栄養素
それでは、ご飯(白米)に含まれる栄養素を見ていきましょう。
ご飯(白米)100gあたりに含まれる栄養成分は、以下のとおりです。
-
・水分:60.0g
-
・炭水化物:36.1g
-
・タンパク質:3.5g
-
・脂質:0.3g
-
・ナトリウム:1mg
-
・カリウム:29mg
-
・カルシウム:3mg
-
・マグネシウム:7mg
-
・リン:34mg
3.炭水化物が不足した場合と過剰摂取した場合
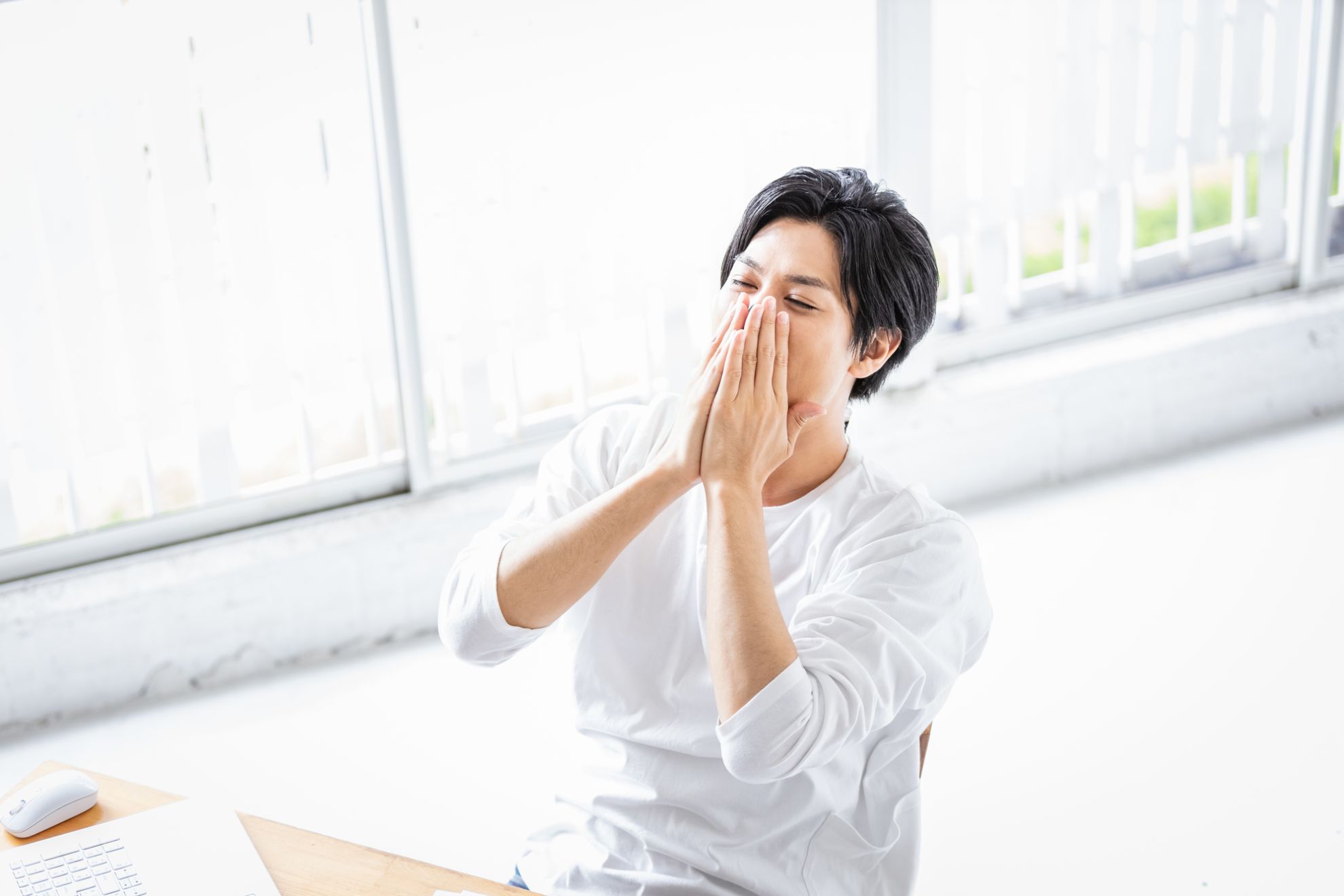 炭水化物の摂取量が偏ると、体に影響が出てきてしまいます。炭水化物が不足した場合と、過剰摂取した場合で体にどのような変化が起こるのかを確認しましょう。
炭水化物の摂取量が偏ると、体に影響が出てきてしまいます。炭水化物が不足した場合と、過剰摂取した場合で体にどのような変化が起こるのかを確認しましょう。
3-1.炭水化物不足が引き起こすおもな症状
炭水化物が不足すると、筋肉や肝臓に蓄積されているグリコーゲンが消費され、エネルギー不足となり、疲れやすい状態になってしまいます。
先述したように、脳の唯一のエネルギー源はブドウ糖です。そのため、炭水化物が不足すると神経や脳へ栄養が行き渡らずに、判断力・注意力が低下するだけでなく、意識障害につながることもあるため注意が必要です。
3-2.過剰摂取した場合
炭水化物を過剰に摂取した場合、エネルギーとして使われなかった糖質は、中性脂肪となって体内に蓄えられてしまいます。
その結果、生活習慣病や肥満につながるおそれがあるため、摂取量には注意しましょう。
ご飯などに含まれる炭水化物は適量を摂取するように心がけましょう
今回は、ご飯などに含まれる炭水化物のはたらきや、ご飯に含まれる栄養素を紹介しました。
炭水化物は体のエネルギー源となる栄養素です。炭水化物が不足した場合と過剰摂取した場合のどちらも、体に大きな影響を与えるため、適切な量を摂取することが大切です。
今回紹介した炭水化物の目安摂取量を参考に、普段の食生活を見直してみましょう。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
 炭水化物が不足すると、肝臓や筋肉中に蓄えられているグリコーゲンが消費され、エネルギーが欠乏して、疲れやすくなってしまいます。
炭水化物が不足すると、肝臓や筋肉中に蓄えられているグリコーゲンが消費され、エネルギーが欠乏して、疲れやすくなってしまいます。

 ご飯などに含まれる炭水化物のはたらきを知っているでしょうか。
ご飯などに含まれる炭水化物のはたらきを知っているでしょうか。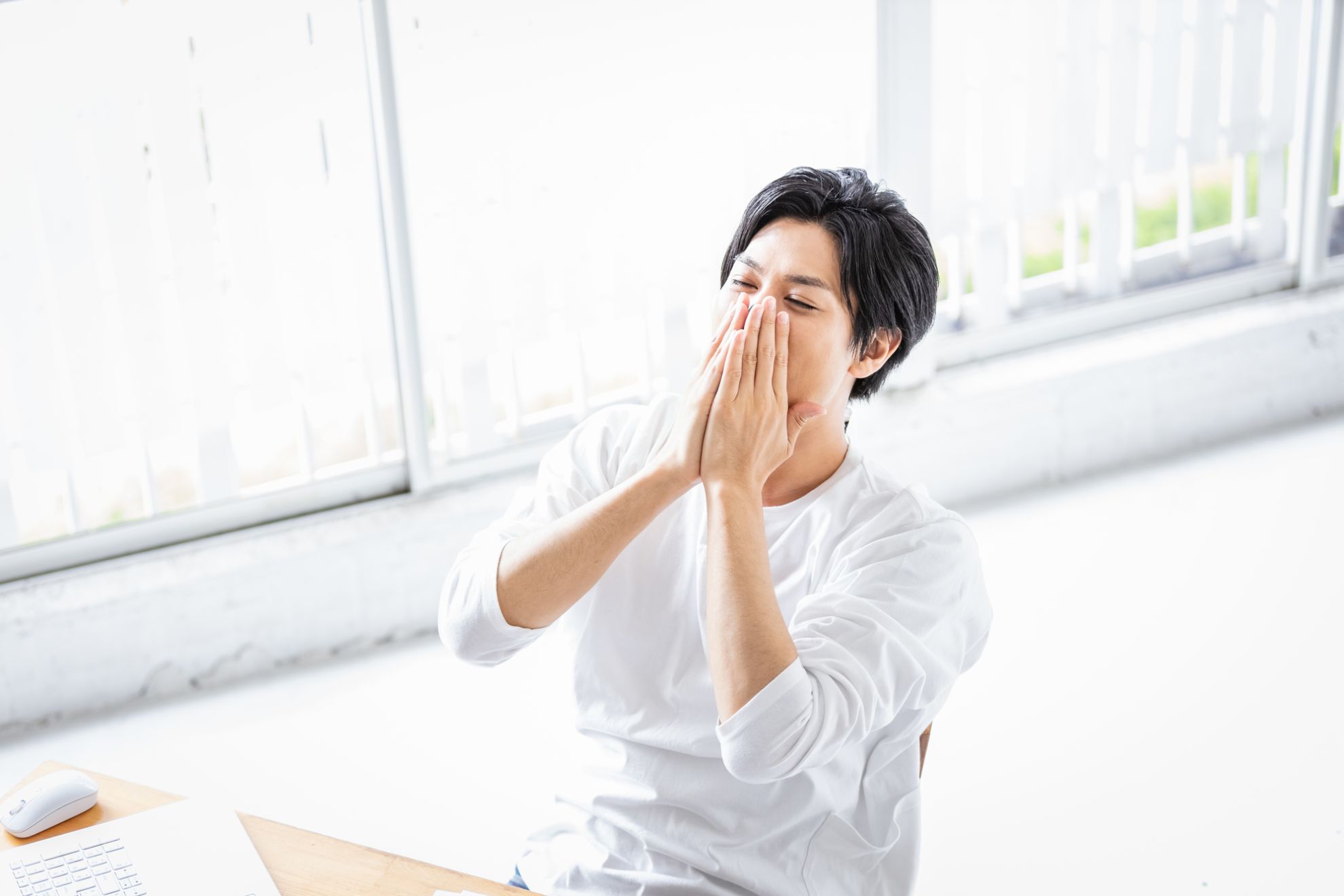 炭水化物の摂取量が偏ると、体に影響が出てきてしまいます。炭水化物が不足した場合と、過剰摂取した場合で体にどのような変化が起こるのかを確認しましょう。
炭水化物の摂取量が偏ると、体に影響が出てきてしまいます。炭水化物が不足した場合と、過剰摂取した場合で体にどのような変化が起こるのかを確認しましょう。






