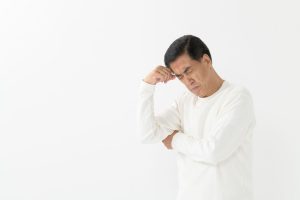1.高齢者が筋トレを行なうメリットとは?
 筋力が低下すると、ちょっとした動作ができなくなったり、自分で立ち上がることさえできなくなる恐れがあります。筋力があるかどうかで、高齢者の生活は大きく左右されるので、高齢者が筋トレをすることにより生活の質の向上が期待できます。
筋力が低下すると、ちょっとした動作ができなくなったり、自分で立ち上がることさえできなくなる恐れがあります。筋力があるかどうかで、高齢者の生活は大きく左右されるので、高齢者が筋トレをすることにより生活の質の向上が期待できます。
1-1.高齢者でも筋力の増強は可能
「筋トレなんて若者が体型作りのために行なうものだ」「高齢になってから筋トレをしても意味がない」と思われている方もいるかもしれません。しかし、高齢者こそ筋トレを行うことが重要です。抗重力筋といわれる体を支えるのに必要な筋肉は、高齢になっても鍛えることができるのです。
おもに背中やお腹、太ももやふくらはぎを鍛えることで、背筋を真っ直ぐ保ったり、転倒を予防したりすることができます。とはいえ、ジムに通わないとできないような大がかりな筋トレを行なう必要はありません。
のちほど紹介するウォーキングや自分の体の重みを使った簡単な自重トレーニングで十分な筋力をつけることができます。
1-2.筋トレによって期待できる効果
筋トレは、高齢者の体にさまざまなメリットを与えてくれる素晴らしい運動です。
おもに次のような効果が期待できます。
-
・筋肉量の増加
-
・骨格筋量の増加
-
・体脂肪の減少
-
・生活習慣病の予防や改善
-
・サルコペニア、フレイル、ロコモの予防や改善
-
・生活の質の向上
-
・嚥下機能の維持や改善
-
・腰痛や膝痛の予防や改善
サルコペニアやフレイル、ロコモという言葉には馴染みがない方が多いかもしれません。
サルコペニアとは、年齢を重ねるにつれて筋力が減少していく状態を指します。
フレイルとは、介護が必要になる手前の状態で、体や社会的な脆弱性、精神的な問題などを抱えている状態を指します。
ロコモとは、正式名称を「ロコモティブシンドローム」といい、筋力やバランス能力が低下することで転倒したり自立した生活を送れず介護が必要になったりする状態のことです。
高齢者に多く見られるこれらの状態は筋トレを行なうことで、予防や改善をすることができます。
2.高齢者におすすめの筋トレ方法
では、具体的にどのような筋トレが高齢者におすすめなのかを見ていきましょう。ここでは、有酸素運動と筋力トレーニングの2種類をそれぞれ紹介します。
2-1.有酸素運動
有酸素運動のなかでも手軽に始められるのがウォーキングです。ほかに、自転車こぎや水中歩行などを行なうのもよいでしょう。体力に合わせて、軽めか少しきつい程度の強度に調節してください。
一日に30分、週に3~5回程度を目標に体を動かしましょう。一日の運動時間は、一度に30分行なうのではなく、10分以上の運動を合計して30分でも問題ありません。
2-2.筋力トレーニング
膝をついた状態で行なうプッシュアップや、ダンベルを両手に持って行なうスクワットは、自宅でも簡単にできる筋力トレーニングです。1回あたり8~12回のトレーニングを一日に1~4セットを目安に行ないましょう。週に2~3回の頻度で行なうのが理想です。
3.高齢者が筋トレをする際の注意点
 普段あまり体を動かさない方が急に運動を行なうと、体に負担がかかってしまうことがあります。
普段あまり体を動かさない方が急に運動を行なうと、体に負担がかかってしまうことがあります。
いきなり激しく体を動かすのは避け、ゆっくりと動かしながら少しずつ強度を上げていくことで、心血管系の事故が起きるリスクを最小限に抑えられます。
また、膝や腰の調子が悪い方は、医師に相談してから運動を始めるようにしてください。
高齢者の方こそ筋トレで元気な体を手に入れよう
高齢者が筋トレを行なうことで筋肉量を増加させ、生活習慣病やサルコペニア、フレイルなどの予防や改善ができます。
一日30分程度のウォーキングや自転車こぎなどを行なうだけでも、体に良い刺激を与えることが可能です。普段あまり運動をしない方は、体に無理をさせすぎないよう、軽めの運動から始めてみましょう。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。
 筋力が低下すると、ちょっとした動作ができなくなったり、自分で立ち上がることさえできなくなる恐れがあります。筋力があるかどうかで、高齢者の生活は大きく左右されるので、高齢者が筋トレをすることにより生活の質の向上が期待できます。
筋力が低下すると、ちょっとした動作ができなくなったり、自分で立ち上がることさえできなくなる恐れがあります。筋力があるかどうかで、高齢者の生活は大きく左右されるので、高齢者が筋トレをすることにより生活の質の向上が期待できます。

 筋力は、立ち上がったり歩いたりなど日常の動作をスムーズにするうえで欠かせません。筋力が低下するとちょっとした動作もやりづらくなるため、生活に大きな影響をおよぼします。
筋力は、立ち上がったり歩いたりなど日常の動作をスムーズにするうえで欠かせません。筋力が低下するとちょっとした動作もやりづらくなるため、生活に大きな影響をおよぼします。 普段あまり体を動かさない方が急に運動を行なうと、体に負担がかかってしまうことがあります。
普段あまり体を動かさない方が急に運動を行なうと、体に負担がかかってしまうことがあります。