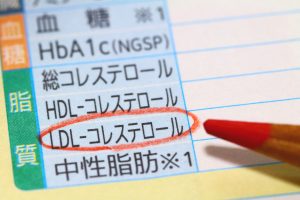1.高血圧の診断基準
 高血圧とは、血圧が高くなる病気です。血圧を測定するときは、収縮期血圧と拡張期血圧を測ります。収縮期血圧とは「上の血圧」のことで、心臓が収縮したときの血圧です。一方、拡張期血圧とは「下の血圧」のことで、心臓が拡張したときの血圧を指します。
高血圧とは、血圧が高くなる病気です。血圧を測定するときは、収縮期血圧と拡張期血圧を測ります。収縮期血圧とは「上の血圧」のことで、心臓が収縮したときの血圧です。一方、拡張期血圧とは「下の血圧」のことで、心臓が拡張したときの血圧を指します。
なお、収縮期血圧が140mmHg以上、拡張期血圧が90mmHg以上である場合が高血圧と定義されています。高血圧は数値によって、下表のようにさらに細かく分類されます。
|
収縮期血圧 |
拡張期血圧 |
| Ⅰ度高血圧 |
140~159mmHg |
90~99mmHg |
| Ⅱ度高血圧 |
160~179mmHg |
100~109mmHg |
| Ⅲ度高血圧 |
180mmHg以上 |
110mmHg以上 |
※収縮期血圧もしくは拡張期血圧のどちらか一方の基準を超えた場合
また、収縮期血圧が140mmHg以上でなおかつ拡張期血圧が90mmHg未満の場合は、孤立性収縮期高血圧と診断されます。
高血圧はさまざまな病気の発症リスクを高めますが、度数が上がると高血圧の重症度は上がり、さらに発症リスクも増大します。健康を保つためには血圧コントロールが重要です。
腎不全や糖尿病といった病気を治療中の方は、合併症の発症リスクはさらに高くなるため、より厳格に血圧管理を行なう必要があります。
2.収縮期血圧が180mmHgを超える「悪性高血圧」とは
高血圧患者のうち1%以下にしか起こらないものの、発症すると予後が非常に悪いものが、高血圧緊急症(悪性高血圧)です。悪性高血圧は30~40歳代の男性に多くみられる疾患で、収縮期血圧が180mmHg、拡張期血圧が120mmHgを超えます。
血圧が異常に上がり、大動脈解離や高血圧脳症、心臓の疾患、腎機能低下などの臓器の急性障害が起こります。急に悪化・進行するおそれがあるため、すみやかな対処が必要です。
急性期には頭痛や嘔吐、吐き気、意識障害、けいれん、視力障害、頻脈、尿が出にくくなるなど、さまざまな症状が現れます。
悪性高血圧は、ホルモン分泌に関わる臓器に腫瘍ができたり、普段の生活習慣によって高血圧が進行したりして起こります。高血圧の進行による悪性高血圧では、血圧上昇のほか肩こりや頭痛といった自覚症状をともなうことがあるため、高血圧の方は日頃から自分の体調変化に留意しましょう。
3.悪性高血圧を防ぐ生活習慣
 高血圧の進行によって引き起こされる悪性高血圧は、治療を適切に進めることで発症を防げるでしょう。悪性高血圧の発症にはストレスのほか、不規則な生活習慣や治療を途中でやめることが関わっています。
高血圧の進行によって引き起こされる悪性高血圧は、治療を適切に進めることで発症を防げるでしょう。悪性高血圧の発症にはストレスのほか、不規則な生活習慣や治療を途中でやめることが関わっています。
生活習慣の改善としては、まず食生活の見直しをしましょう。果物や野菜の摂取を心がけ、塩分やコレステロール・飽和脂肪酸の摂り過ぎに注意してください。
肥満解消のためには、適度な運動習慣をつけることも重要です。特に持病がない方は、毎日30分ほどの有酸素運動を行なうことをおすすめします。ぜひ、BMIの数値が25以下になるよう目指してください。
また、喫煙も高血圧を悪化させるため、たばこを吸っている方は禁煙を検討しましょう。
悪性高血圧は前兆がないまま、一気に進行することが少なくありません。高血圧の方は症状がひどくならないうちに受診し、原因をはっきりさせることが大切です。血圧を上げている要因を排除することで、高血圧自体の改善につながるケースもあります。体調に異常を感じた場合は、早めに医師に相談しましょう。
収縮期血圧が180mmHgを超えるときはまず病院を受診しよう
血圧が140/90mmHgを超えると高血圧と診断されますが、その1%に満たない割合で悪性高血圧を発症することがあります。
悪性高血圧になると、収縮期血圧が180mmHg以上となるほか、脳や心臓、腎臓などの臓器に障害を引き起こして急激に悪化するおそれがあります。このような急激な高血圧であることに気が付いたら、まず病院を受診しましょう。
悪性高血圧にいたる原因の一つが生活習慣です。予防のためには、減塩を心がけ、コレステロールや飽和脂肪酸の過剰摂取を避けましょう。
また、運動を毎日の生活に組み込んで肥満対策をすることも大切です。高血圧を予防するために、生活習慣の改善に取り組みましょう。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。
 高血圧とは、血圧が高くなる病気です。血圧を測定するときは、収縮期血圧と拡張期血圧を測ります。収縮期血圧とは「上の血圧」のことで、心臓が収縮したときの血圧です。一方、拡張期血圧とは「下の血圧」のことで、心臓が拡張したときの血圧を指します。
高血圧とは、血圧が高くなる病気です。血圧を測定するときは、収縮期血圧と拡張期血圧を測ります。収縮期血圧とは「上の血圧」のことで、心臓が収縮したときの血圧です。一方、拡張期血圧とは「下の血圧」のことで、心臓が拡張したときの血圧を指します。

 現在、日本ではおよそ4000万人もの方が高血圧であると診断されています。高血圧は、さまざまな病気のリスクとなるため、血圧を適切にコントロールすることは重要です。
現在、日本ではおよそ4000万人もの方が高血圧であると診断されています。高血圧は、さまざまな病気のリスクとなるため、血圧を適切にコントロールすることは重要です。 高血圧の進行によって引き起こされる悪性高血圧は、治療を適切に進めることで発症を防げるでしょう。悪性高血圧の発症にはストレスのほか、不規則な生活習慣や治療を途中でやめることが関わっています。
高血圧の進行によって引き起こされる悪性高血圧は、治療を適切に進めることで発症を防げるでしょう。悪性高血圧の発症にはストレスのほか、不規則な生活習慣や治療を途中でやめることが関わっています。