1.ヒスタミンとは?
ヒスタミンとは、食中毒の原因となる化学物質のことです。
もともと“ヒスタミン”として食品に含まれているわけではなく、細菌の酵素の働きによって、食品に含まれるアミノ酸の一種“ヒスチジン”から生成されます。ただし、魚の場合は、漁獲された時点でヒスタミンを生成する細菌が付着していることもあるので、注意が必要です。
ヒスチジンを含む食品を、室温で放置するなど不適切な状態で保管していると、細菌が増殖し、ヒスタミンがつくられてしまいます。
ヒスタミンは熱に強いため、一度つくられてしまうと加熱しても減ることがなく、冷凍状態でも壊れない性質があるので、保管状態には注意しましょう。
2.ヒスタミン食中毒について
 サバやカツオなどを食べたあとに、体に湿疹が出たり、顔が赤くなったりした経験はありませんか?アレルギーに似たその症状は、もしかするとヒスタミン食中毒かもしれません。
サバやカツオなどを食べたあとに、体に湿疹が出たり、顔が赤くなったりした経験はありませんか?アレルギーに似たその症状は、もしかするとヒスタミン食中毒かもしれません。
2-1.ヒスタミン食中毒とは
ヒスタミンを多く含む食品を食べることによって引き起こされる食中毒を「ヒスタミン食中毒」といいます。症状がアレルギーと似ているので混同されがちですが、実はアレルギーではありません。
ヒスタミン食中毒は、年中発生しているので季節を問わず注意が必要です。
2-2.どのような症状?
赤身魚など原因となる食品を食べた直後から、1時間以内に次のような症状が現れます。
-
・口の周りの腫れ・かゆみ・熱感
-
・しびれ
-
・耳たぶが赤く腫れる
-
・頭痛
-
・じんましん
-
・発熱
-
・嘔気
-
・嘔吐など
なお、重症になることは少なく、大半は抗ヒスタミン薬で症状が治まります。そのため、発症したら早めに医療機関を受診しましょう。
2-3.注意したい食品は?
赤身魚やその加工食品には、ヒスチジンというアミノ酸が多く含まれており、ヒスタミン食中毒の原因となっています。
その他、鶏肉やチーズ・ザワークラウトなどによるヒスタミン食中毒も報告されているようです。
また、醤油・味噌・キムチ・納豆などの発酵食品や、ビールやワイン・サラミやソーセージといった食品にも、ヒスタミンが含まれていることがあります。そのため、これらが食中毒の原因になる可能性も否定できません。
【赤身魚100g中に含まれるヒスチジン含有量】
| 食品名 |
ヒスチジン含有量(㎎/100g中) |
| 春獲りカツオ(生) |
2,500 |
| 天然クロマグロ(生) |
2,500 |
| キハダマグロ(生) |
2,100 |
| ブリ(生) |
1,700 |
| サバ(生) |
1,600 |
| サンマ(生) |
1,200 |
| イワシ(生) |
1,100 |
| アジ(生) |
790 |
出典:文部科学省「食品成分データベース」
白身魚ではヒスチジン含有量が数㎎から10㎎(100g中)ほどなので、いかに赤身魚の数字が大きいかがわかります。
2-4.どのくらいのヒスタミン量で発症するの?
「食品100gあたり100㎎以上」のヒスタミンが含まれる場合に、ヒスタミン食中毒は発症するとされています。しかし、食べる量が多い場合はこの限りではありません。
過去の食中毒事例から計算した結果から、大人では「22~320㎎」のヒスタミン摂取によって発症したという報告もあります。
このことからもヒスタミンに対する耐性は、個人差が大きいといえるでしょう。さらに、消化器の病気の有無や女性の場合は月経など、体調によってもヒスタミンの代謝スピードは遅くなったり早くなったりします。
また、喫煙はヒスタミンの分解を遅くするため、食中毒の症状が出やすくなるので注意しましょう。
3.ヒスタミン食中毒の予防法について
 食中毒を予防するには、「つけない・増やさない・やっつける」ことが大切です。
食中毒を予防するには、「つけない・増やさない・やっつける」ことが大切です。
しかし、ヒスタミン食中毒では、魚を漁獲したときにすでにヒスタミンが付着している場合もあります。また、ヒスタミンは一度つくられてしまうと加熱しても減りません。
そのため、ヒスタミンを「増やさない」ということがポイントとなります。
食品の見た目や臭いからは、ヒスタミンが増殖しているかどうかの判断ができません。そのため、次の4点に注意しましょう。
3-1.魚はすぐに冷蔵庫で保管しましょう
ヒスタミンは魚を常温で放置すると増えてしまうため、購入した魚はすぐに冷蔵庫へ入れましょう。
自分で釣った魚の場合も、速やかにクーラーボックスに入れて冷却することが大切です。
3-2.魚の内臓やエラはできるだけ早く取り除きましょう
消化管やエラにはヒスタミンをつくる菌が多く存在するので、魚の内臓やエラはできるだけ早く取り除きましょう。
3-3.鮮度が落ちてしまった魚は食べないようにしましょう
一度つくられたヒスタミンは加熱してもダメージを受けないので、鮮度が落ちてしまった魚は食べないようにしましょう。
3-4.一口食べて異変を感じたら、食べずに捨てましょう
ヒスタミンが多い食品を食べると、舌や唇に異常な刺激を感じる場合があります。
一口食べて舌や唇がピリピリしたり、異常を感じたりしたら、食べずに捨てましょう。
魚からヒスタミンを増やさないために保存方法は注意しましょう
ヒスタミンは食中毒を引き起こす原因物質であり、カツオやマグロといった赤身魚に多く含まれるヒスチジンからつくられます。魚を常温で放置していると、ヒスタミンが増えてしまうので、速やかに冷蔵庫に入れるなど冷やして保存することを徹底しましょう。
ヒスタミン食中毒になる危険性は一年を通じていつでも潜んでおり、発症すると口の周りがかゆくなったり、じんましんが出たり、吐き気がしたりなど苦しい思いをすることになります。
ヒスタミン食中毒を避けるためにも、日頃から魚は内臓やエラを取り除いて調理する・鮮度が良いうちに食べるなど対策をしていきましょう。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


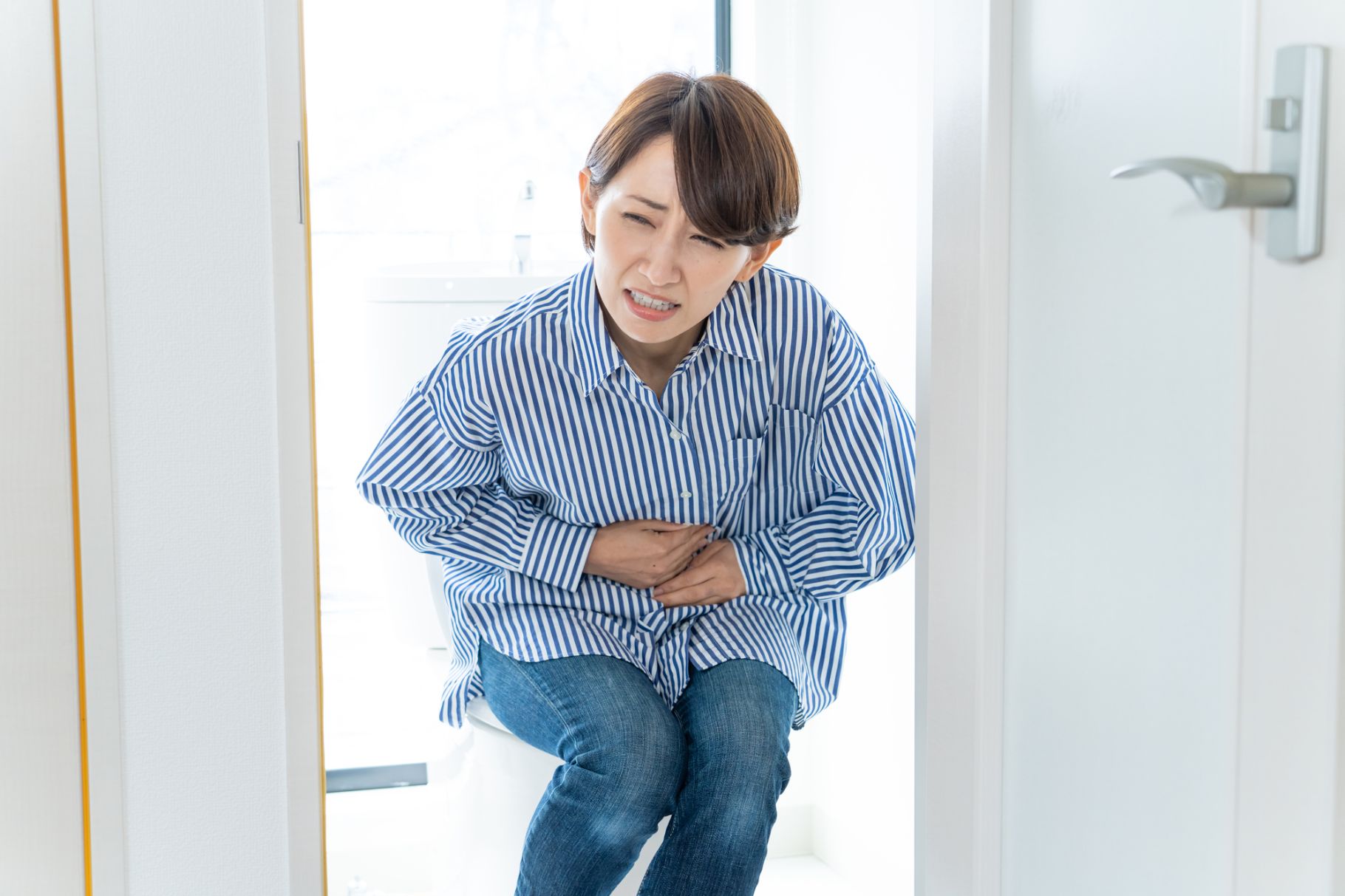 ヒスタミンによる食中毒が、毎年発生しているのをご存じでしょうか。梅雨時や夏だけに限らず年間を通して発生しており、多くの方が苦しい思いをしています。また、身近な食品が原因となっていることが多いため、予備知識を持っておいたほうがよいでしょう。
ヒスタミンによる食中毒が、毎年発生しているのをご存じでしょうか。梅雨時や夏だけに限らず年間を通して発生しており、多くの方が苦しい思いをしています。また、身近な食品が原因となっていることが多いため、予備知識を持っておいたほうがよいでしょう。 サバやカツオなどを食べたあとに、体に湿疹が出たり、顔が赤くなったりした経験はありませんか?アレルギーに似たその症状は、もしかするとヒスタミン食中毒かもしれません。
サバやカツオなどを食べたあとに、体に湿疹が出たり、顔が赤くなったりした経験はありませんか?アレルギーに似たその症状は、もしかするとヒスタミン食中毒かもしれません。
 食中毒を予防するには、「つけない・増やさない・やっつける」ことが大切です。
食中毒を予防するには、「つけない・増やさない・やっつける」ことが大切です。






