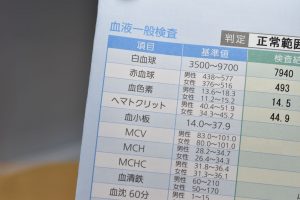1.メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドロームは、直訳すると「代謝症候群」または「内臓脂肪症候群」です。内臓脂肪型肥満を基盤として、高血圧や高血糖、脂質代謝異常が組み合わさった状態をいいます。
内臓脂肪型肥満は、内臓に脂肪が蓄積して腹囲が増えるタイプの肥満であり、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの発症リスクを高めるため注意が必要です。
糖や脂肪などの栄養素を分解してエネルギーを得たり、人体に必要な成分を合成したりすることを代謝と呼びますが、メタボリックシンドロームになると代謝機能の安定性が損なわれてきます。代謝の安定性が崩れると、糖や脂肪を一定量で維持できなくなる、水分代謝が乱れて血圧が高くなるなど、全身に悪影響が生じます。
なお、メタボリックシンドロームには診断基準があり、腹囲が基準値を超えていても他の項目が該当しなければ、メタボリックシンドロームには当てはまりません。
2.メタボリックシンドロームの診断基準
 メタボリックシンドロームの診断基準には、「必須項目」と3項目中2項目の該当で判断する「選択項目」が存在します。
メタボリックシンドロームの診断基準には、「必須項目」と3項目中2項目の該当で判断する「選択項目」が存在します。
2-1.必須項目(腹囲)
メタボリックシンドロームと診断するには、腹囲(ウエスト周囲径)が男性85cm以上、女性90cm以上であることが必須とされます。この基準値は、男女ともに内臓脂肪面積が100cm2以上に相当する数値です。
2-2.選択項目(3項目のうち2項目以上)
選択項目として、以下3項目のうち2項目以上に該当するか否かが診断基準とされています。
3.メタボリックシンドロームの改善・予防方法
 メタボリックシンドロームを改善・予防するための基本方針は、内臓脂肪の蓄積を解消したり、内臓脂肪がつかないようにしたりすることです。
メタボリックシンドロームを改善・予防するための基本方針は、内臓脂肪の蓄積を解消したり、内臓脂肪がつかないようにしたりすることです。
具体的な対処法には、食事内容の見直しと運動不足の解消が挙げられます。食事から摂取するエネルギー量を適切な範囲内にとどめ、定期的な運動習慣によってエネルギーの消費量を増やしましょう。
メタボリックシンドロームが気になる人は、GI値(グリセミックインデックス値)の低い食品を食べて血糖値の上昇を穏やかにしたり、食べ物をしっかり噛んで腹七から八分目の食事量に抑えたりするとよいでしょう。食物繊維をたっぷり摂ること、間食や夜食を避けることも大切です。
運動では、1週間あたり10メッツ・時以上のジョギングや水泳、ウォーキングなどの有酸素運動を行なうと、メタボリックシンドロームの改善に効果的です。メッツは身体活動の強さを表す単位で、普通の歩行が3メッツ、毎分160m程度のランニングや平泳ぎが10メッツに相当します。
メタボリックシンドロームを予防・改善しましょう
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪に加えて高血圧、高血糖、脂質代謝異常が複合的に組み合わさった状態を指します。メタボリックシンドロームになると代謝の安定性が損なわれ、血圧や脂質代謝などに異常が出やすくなるので注意が必要です。
メタボリックシンドロームに注意するために、自分の腹囲を測ってみましょう。男性では腹囲85cm以上、女性では90cm以上で、なおかつ血圧や血糖値などが基準値から複数外れていればメタボリックシンドロームと診断されます。
メタボリックシンドロームの予防・改善に取り組み、健康的な毎日を過ごしましょう。
監修者情報

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)
外科医として地方中核病院に勤務中。
消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。
資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医


 テレビや新聞などで取り上げられることの多い、メタボリックシンドローム。自分がメタボリックシンドロームに該当しているか、気になっている方もいるのではないでしょうか。
テレビや新聞などで取り上げられることの多い、メタボリックシンドローム。自分がメタボリックシンドロームに該当しているか、気になっている方もいるのではないでしょうか。 メタボリックシンドロームの診断基準には、「必須項目」と3項目中2項目の該当で判断する「選択項目」が存在します。
メタボリックシンドロームの診断基準には、「必須項目」と3項目中2項目の該当で判断する「選択項目」が存在します。
 メタボリックシンドロームを改善・予防するための基本方針は、内臓脂肪の蓄積を解消したり、内臓脂肪がつかないようにしたりすることです。
メタボリックシンドロームを改善・予防するための基本方針は、内臓脂肪の蓄積を解消したり、内臓脂肪がつかないようにしたりすることです。