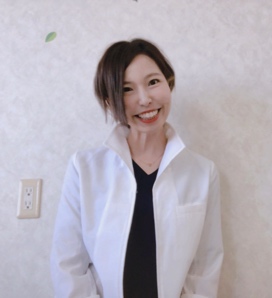1.歯周病の症状について
 ここでは、歯周病がどのような病気でどういった状態になるのかを、詳しく解説します。
ここでは、歯周病がどのような病気でどういった状態になるのかを、詳しく解説します。
1-1.そもそも歯周病とは?
歯周病とは、歯肉炎と歯周炎を合わせたものを指します。
歯肉炎は、歯ぐきと歯の隙間にある歯周ポケットから細菌が入り込み、歯ぐきが炎症を起こしている状態のことです。そして歯周炎は、歯を支えている歯槽骨と呼ばれる骨が溶けはじめている状態をいいます。
それに対し、むし歯は、細菌の分泌した酸が歯を溶かすことで、歯に穴があく病気です。歯周病は、歯そのものではなく、歯ぐきや歯を支える骨が破壊されていく病気であり、むし歯とはまったく異なります。
1-2.歯周病によって見られる現象
歯周病になると、歯がぐらぐらしたり歯ぐきが下がったりして、最終的には歯が抜け落ちる現象が見られます。
歯肉炎によって歯ぐきに出血や腫れが生じ、歯周ポケットがさらに深くなります。そして歯を支える骨が溶ける歯周炎によって歯がぐらつくのです。
歯周ポケットは酸素が少なく、歯周病の病原菌が増殖しやすい環境にあります。プラークの中に潜む細菌が、リン酸やカルシウムの影響で歯石になり、歯の表面へ付着。そこから、組織のさらに奥まで細菌が進行し、どんどん状態が悪化するのです。
2.歯周病のおもな原因
歯周病になるおもな原因は、いくつかあります。
まず、挙げられるのが歯周病原菌です。ブラッシングが不十分だと、プラークが歯と歯ぐきの境目に残ったままになり、プラークに潜む細菌が毒素を出します。その結果、歯ぐきに出血や腫れが現れてしまうのです。
また、病気による免疫力の低下・年齢・遺伝など、宿主側の原因で歯周病が起こっていることもあります。その他、喫煙やストレスなどの環境因子も、歯周病を引き起こす原因です。
かみ合わせの悪さや歯ぎしりなど、歯に負荷がかかるような状態も歯周病の原因として考えられます。
3.歯周病の予防方法
 歯周病の原因や見られる現象について理解したところで、ここからは歯周病の予防について解説します。
歯周病の原因や見られる現象について理解したところで、ここからは歯周病の予防について解説します。
3-1.セルフケアについて
歯周病の予防では、毎日の丁寧な歯磨きによって、細菌性プラークを除去することが大切です。
使う歯ブラシは大きすぎないサイズ、毛足が真っすぐで毛束は3~4列程度なら磨きやすいでしょう。また、通気性の良いものを選ぶのがポイントです。
歯が健康な方は、硬めか普通くらいの硬さの毛を選びましょう。歯ぐきに痛みなどがある方は、やわらかめの毛がおすすめです。
歯を磨く際は、鉛筆を持つように歯ブラシを持ち、一歯ずつ丁寧に磨きましょう。とはいえ、自分の歯に合った磨き方がそれぞれあるため、最初は歯科医院で磨き方の指導を受けたほうが確実です。
磨き方には、おもにバス法とスクラッピング法の2種類があります。
バス法では、歯の外側・内側の歯に向かって毛先を45度斜めにして、軽い力で小刻みに磨きます。歯ぐきに炎症がある方に適した方法です。
スクラッピング法では、歯の外側から歯に向かって毛先を直角に当てて、小刻みに磨きます。このとき、力は入れずに軽い力で磨くのがポイントです。歯の内側を磨くときは、舌側から歯に向かって45度くらいの角度で当てて、同じように軽い力で小刻みに動かしましょう。この方法は、歯が健康な人に向いています。
3-2.生活習慣のポイント
歯周病にならないためには、まずは禁煙することが大切です。タールやニコチン、一酸化炭素などの物質は体にとって有害なうえに、タールが歯に付着するとプラークも付きやすくなり、歯周病の原因になってしまいます。
そして、ストレスを溜めすぎないようにすることも大切です。ストレス発散のために、運動や音楽療法など、自分に合ったリラックス方法を探してみてください。
また、食事の際には、よく噛んで食べることも大切です。唾液と食べ物を混ぜるようにしながら、しっかりと噛みましょう。
歯周病を予防していつまでも元気な歯を守ろう
歯周病は、むし歯と並ぶ2大歯科疾患です。将来、歯周病にならないためにも、いまから日々の食生活や歯磨き習慣を見直しましょう。
歯磨きでは、自分に合った磨き方を身につけて、歯周病の原因となるプラークを除去することが大切です。しっかりと口腔内をケアして、元気な歯を守りましょう。
監修者情報
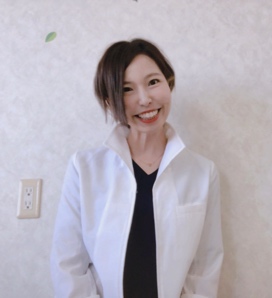
氏名:福田尚美(ふくだ・なおみ)
歯科医師臨床研修終了後、審美歯科・ホワイトニング専門医院に勤務。現在は一般歯科・小児歯科非常勤勤務のかたわら歯科医師としての知識と経験を生かし、歯科医師webライター、歯科企業やオンラインセミナーのサポートなども行なっている。
 ここでは、歯周病がどのような病気でどういった状態になるのかを、詳しく解説します。
ここでは、歯周病がどのような病気でどういった状態になるのかを、詳しく解説します。


 歯科の2大疾患として知られている、むし歯と歯周病。「歯周病という病名は聞いたことがあるけれど、実は詳しく知らない」という方も多いのではないでしょうか。
歯科の2大疾患として知られている、むし歯と歯周病。「歯周病という病名は聞いたことがあるけれど、実は詳しく知らない」という方も多いのではないでしょうか。 歯周病の原因や見られる現象について理解したところで、ここからは歯周病の予防について解説します。
歯周病の原因や見られる現象について理解したところで、ここからは歯周病の予防について解説します。