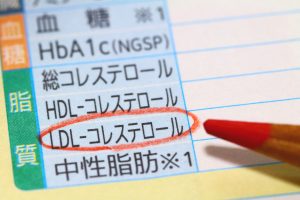目次
1.胃潰瘍のおもな原因とは?
 胃潰瘍の特徴やおもな原因を紹介します。
胃潰瘍の特徴やおもな原因を紹介します。
1-1.胃潰瘍について
胃潰瘍とは、胃酸によって胃の内壁が傷付けられ、痛みや出血がある状態のことです。通常、胃の内壁は粘液によって強い塩酸の胃液から守られていますが、胃液と粘膜のバランスが何らかの原因で崩れると胃を守る機能が弱くなり、胃潰瘍になります。
胃潰瘍になると、みぞおちに痛みを感じるほか、吐血したり、便に血が混じるタール便が出たりすることもあります。
その他、次のような現象も見られるでしょう。
-
・胸やけやげっぷ
-
・吐き気
-
・嘔吐
-
・貧血
-
・食欲不振
胃潰瘍が悪化すると傷がさらに深くなり、胃に穴が空くケースもあるので注意しましょう。なお、胃潰瘍を発症する年代としては、40~50歳代が多いのも特徴です。
1-2.胃潰瘍のおもな原因
胃潰瘍は、おもに次のようなことが原因で起こります。
-
・ストレス
-
・不規則な生活
-
・塩分の過剰摂取
-
・喫煙
-
・節度ある量を超えた飲酒
-
・胃がヘリコバクター・ピロリ菌(以下ピロリ菌)に感染
喫煙は、胃酸の分泌を多くする作用があります。さらに、タバコに含まれるニコチンは、粘膜の血流を妨げて胃の防御を低下させるため、喫煙は胃壁を荒らす大きな原因です。
また、喫煙者はピロリ菌への感染率が高い傾向にあります。
ピロリ菌は胃の粘膜に存在する細菌で、粘液内にいるため胃酸の影響を受けることがありません。毒素やアンモニアを作り出して粘膜にダメージを与え、炎症しやすい状態にしたり、粘液の分泌を減少させて、胃の内壁が胃酸のダメージを受けやすい状態にしたりします。
ピロリ菌は食べ物を介して感染するケースが多く、しっかりとした衛生環境が確保できなかった頃には、多くの人が感染していました。
ただし、ピロリ菌に感染しても必ずしも胃潰瘍になるわけではなく、ピロリ菌保有者のうちのごく一部と考えられています。


 何らかの原因で、誰しも一度は胃が痛くなったことがあるのではないでしょうか。
何らかの原因で、誰しも一度は胃が痛くなったことがあるのではないでしょうか。 胃潰瘍は、ストレスや性格などの影響で起こりやすくなります。ストレスがたまらないようにしっかり休み、胃腸に負担をかけない生活を送ることが大切です。前述した生活習慣の見直しを含め、少しずつ行なっていきましょう。
胃潰瘍は、ストレスや性格などの影響で起こりやすくなります。ストレスがたまらないようにしっかり休み、胃腸に負担をかけない生活を送ることが大切です。前述した生活習慣の見直しを含め、少しずつ行なっていきましょう。