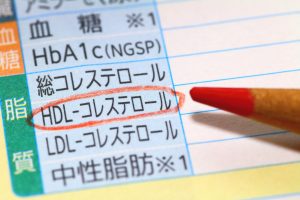目次
1.糖尿病とは
糖尿病は、高血糖の状態が慢性的に続く病気です。糖尿病になると血管が傷つき、ほかの病気につながる恐れがあります。腎不全などになるほか、場合によっては失明することもあります。
また、糖尿病の初期は、血糖値が高いことを自覚しづらいという面もあります。目立った症状が出ないまま悪化するのも糖尿病の怖さです。
糖尿病で血糖値が高いままとなる原因は、血糖値を下げる成分として体内で分泌されるインスリンが不足するほか、効きが悪くなるためです。
なお、糖尿病は以下で説明する「1型」と「2型」におもに分類されます。詳しく見ていきましょう。
1-1.1型糖尿病
1型糖尿病はインスリンの分泌量が低下するタイプの糖尿病です。
体内では膵臓のβ細胞がインスリンを分泌していますが、1型糖尿病はこのβ細胞が壊れ、インスリンがほとんど出なくなってしまいます。
しかし、1型糖尿病の原因についてはよくわかっていないのが現状です。
理由として推測されているのは、自己免疫が正常に働かないことにより、自分の免疫が間違ってβ細胞を攻撃していることが関係しているということです。
また、1型糖尿病は全世界の糖尿病患者の割合で見ると約5%と少ない傾向にありますが、中高年に多い2型糖尿病とは違い、幅広い年代で発症することがわかっています。特に痩せ型の人は1型糖尿病が多い傾向があります。
1型糖尿病の治療には、インスリン注射が使われます。これは、1型糖尿病の発症後はインスリンを出す力が弱まり、体内で作ることが難しくなるためです。
1-2.2型糖尿病
2型糖尿病は、食べ過ぎや運動不足のほか肥満などの要因によってインスリンの効きが悪くなるタイプの糖尿病です。要因の一つとして、遺伝的な影響であるケースもあります。
正常な身体は分泌されたインスリンが細胞に働きかけ、血中の糖を取り込みます。
一方、2型糖尿病になると、インスリンが細胞に働きかけても糖が細胞内に入りません。結果として、血中に糖が残ったままになり、高血糖の状態が続きます。
インスリンの分泌は正常に行なわれているものの、うまく機能が働かない状態を「インスリン抵抗性」と呼び、この状態により2型糖尿病で血糖値が高くなります。
2型糖尿病は、遺伝的な要因もありますが、主に食べ過ぎや運動不足、肥満といった生活習慣や環境が関係しています。


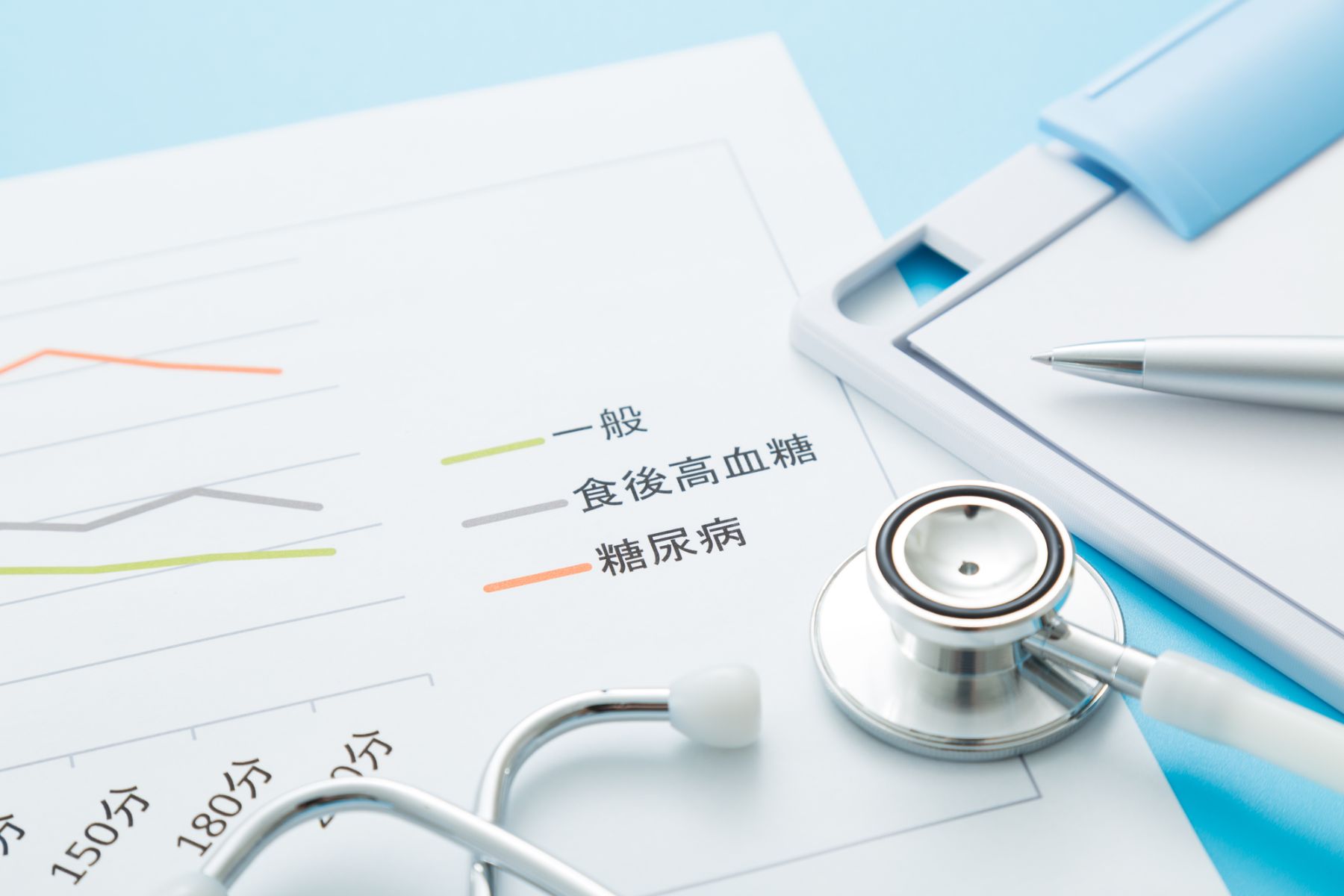 糖尿病が怖い病気であることはよく知られていますが、その症状や原因について詳しく知らない方も多いでしょう。
糖尿病が怖い病気であることはよく知られていますが、その症状や原因について詳しく知らない方も多いでしょう。 糖尿病は初期では症状がないため、気付かない人が多くいます。
糖尿病は初期では症状がないため、気付かない人が多くいます。 糖尿病を引き起こすほかの要因としては、遺伝的要因や内分泌疾患、肝臓疾患などの別の疾患によるもの、薬剤や自己免疫的な機序などがあります。
糖尿病を引き起こすほかの要因としては、遺伝的要因や内分泌疾患、肝臓疾患などの別の疾患によるもの、薬剤や自己免疫的な機序などがあります。