目次
1.補酵素とは
 人間には、さまざまな代謝経路があります。体内での代謝はさまざまな酵素が担っており、その酵素作用を補酵素が行なっています。
人間には、さまざまな代謝経路があります。体内での代謝はさまざまな酵素が担っており、その酵素作用を補酵素が行なっています。
補酵素には複数の種類があり、役割は多岐にわたります。基本的には食事から摂取できるものがほとんどで、体内で大切な役割を担っている成分なため、欠かさずに摂ることが推奨されます。
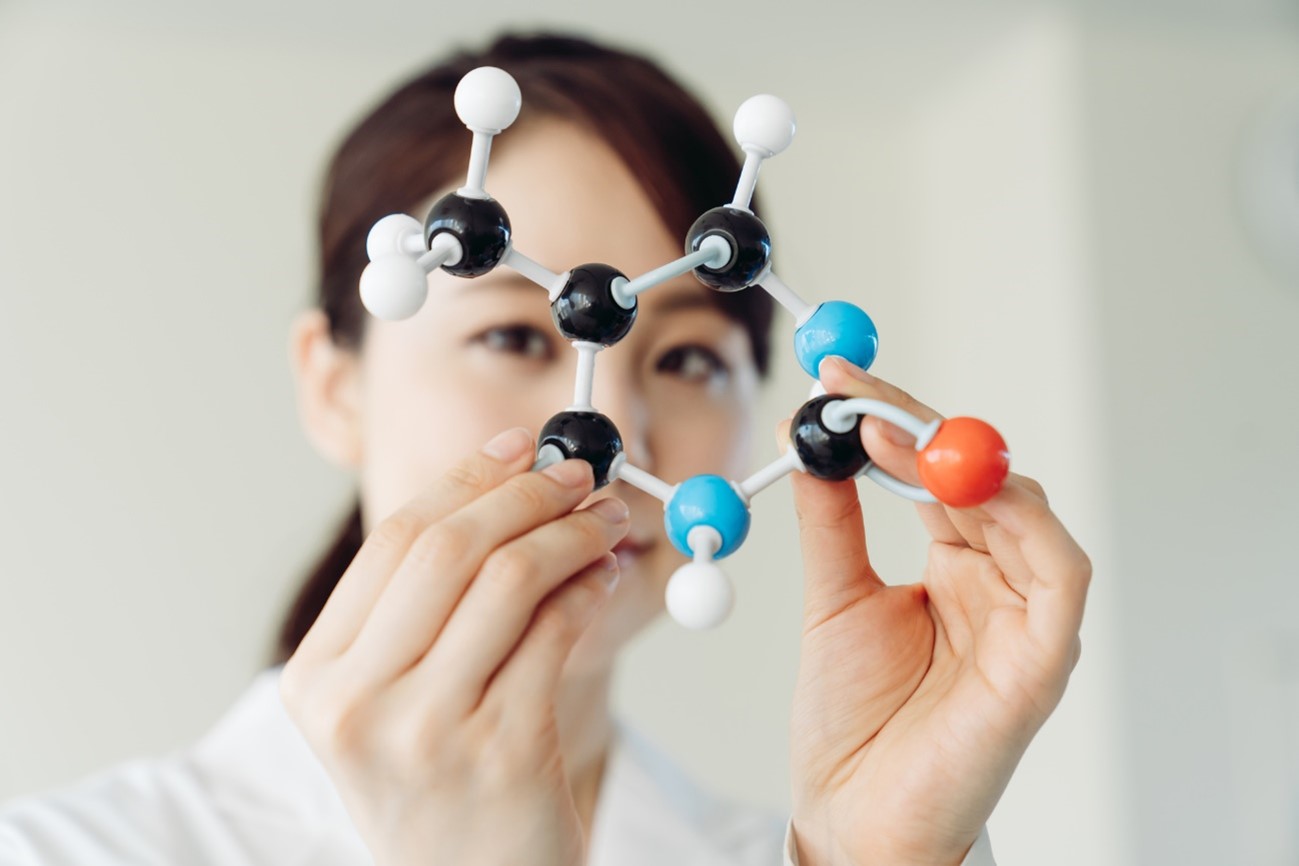 「酵素」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、「補酵素」といわれてピンとくる人は少ないかもしれません。
「酵素」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、「補酵素」といわれてピンとくる人は少ないかもしれません。
この記事では補酵素が体内でどのような役割を果たすのか、また、補酵素の種類と種類ごとの役割、含まれている食品の具体例も挙げてご紹介します。
目次
 人間には、さまざまな代謝経路があります。体内での代謝はさまざまな酵素が担っており、その酵素作用を補酵素が行なっています。
人間には、さまざまな代謝経路があります。体内での代謝はさまざまな酵素が担っており、その酵素作用を補酵素が行なっています。
補酵素には複数の種類があり、役割は多岐にわたります。基本的には食事から摂取できるものがほとんどで、体内で大切な役割を担っている成分なため、欠かさずに摂ることが推奨されます。
 次に代表的な補酵素について、それぞれ説明します。ここでは9つの補酵素の働きと、それぞれを豊富に含む食品を紹介します。
次に代表的な補酵素について、それぞれ説明します。ここでは9つの補酵素の働きと、それぞれを豊富に含む食品を紹介します。
チアミンと呼ばれる補酵素で、糖からエネルギーを作るために必要なため、毎日を元気に過ごすために摂りたい成分です。ビタミンB1を多く含む食品には玄米や豆腐、スイートコーン、豚肉、うなぎ、たらこがあります。なお、食事で糖質の多いものを食べたときなどはビタミンB1が不足しやすくなるため、注意が必要です。
リボフラビンとも呼ばれる補酵素で、新陳代謝や成長に関係する成分です。食品では納豆や玉露、アーモンド、ぶり、うなぎ、豚ヒレ肉、牛乳などに含まれています。
酸化還元酵素の補酵素で体内ではヌクレオチド(NAD)やニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)に変換され、脂質やアミノ酸の代謝を助けます。食品では、たらこ、鶏むね肉、かつお、豚ヒレ肉、まぐろ、玄米、落花生、スイートコーンに含まれています。なお、ビタミンB6が不足しているとナイアシンも欠乏しやすくなります。
ピリドキシンと呼ばれる補酵素で、たんぱく質の代謝や合成、脂質の吸収を助けます。豚ヒレ肉、まぐろ、かつお、鶏むね肉、バナナ、フライドポテト、玄米などに含まれています。
複数のビタミンの総称でコバルト、ヒドロキソコバラミン、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、シアノコバラミン、スルフィトコバラミンのことを示し、アミノ酸や脂質の代謝に関係する補酵素です。微生物により作られる成分で、しじみやあさりなどの貝類、さば、さんま、いくらなどの動物性食品に含まれます。植物性食品にはほぼ含まれないため、菜食主義の方は不足しないよう注意が必要な成分です。
プテロイルモノグルタミン酸と呼ばれる補酵素です。プリンヌクレオチドやデオキシピリミジンヌクレオチドの合成に関与しているため、細胞の増殖に関係しています。以前はビタミンBcやビタミンMと呼ばれることもありました。妊娠時の栄養補給として摂っておきたい成分としても知られています。食品では玉露、えだまめ、ほうれん草などに含まれています。
アミノ酸や脂肪酸など、エネルギーの代謝に関係している補酵素です。体内では作ることができないビタミンですが、さまざまな食品に含まれているため不足することは基本的に少ないと考えられています。食品では卵、落花生、アーモンド、ブロッコリー、納豆などに多く含まれています。
ギリシャ語で「どこにでも存在する酸」という意味を持つ補酵素で、糖や脂質の代謝に関わっています。食品では鶏むね肉、納豆、玄米、アボカドに多く含まれています。腸内細菌からも作られますが、多くの食品に含まれているため、不足することは少ないと考えられています。
ビタミンKにはフィロキノンと呼ばれるビタミンK1と、メナキノンと呼ばれるビタミンK2があります。ビタミンK1は緑黄色野菜・海藻類・緑茶・植物油から、ビタミンK2は腸内細菌からも作られます。ビタミンKは骨の構成成分としても知られており、食品ではほうれん草、小松菜、納豆、春菊、ブロッコリー、鶏肉、ツナなどに多く含まれています。
補酵素には複数の種類があり、糖質・脂質やアミノ酸の代謝に関わるものから、妊娠時の栄養補給として摂っておきたいものまでさまざまです。
パントテン酸やビオチンのように、基本的に欠乏することはないと考えられている補酵素もある一方で、ビタミンB12のように植物性食品からはほとんど摂れないものもあるため、食生活に偏りがある方は注意が必要です。
毎日を元気に過ごしたい方は補酵素の役割を理解するとともに、今回紹介した食品を日々の食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
成分

健康のために毎日ヨーグルトを食べている人は多いのではないでしょうか。
成分

活力のある毎日を応援してくれるクエン酸。
成分

人体のさまざまな機能を正常に働かせるうえで、大切な栄養素となるのがビタミンです。
成分

サラダや煮物など、にんじんはさまざまな調理法でおいしく食べられています。
成分

じゃがいもは、多くの家庭でキッチンに常備されている食材の一つで、肉じゃがに、カレーにと、食べる機会も多いものです。