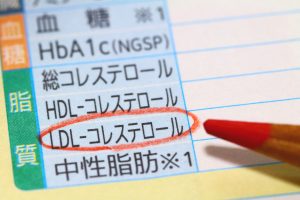目次
1.体のだるさから考えられる病気
 体のだるさがあるときには、どのような病気の可能性があるのでしょうか。
体のだるさがあるときには、どのような病気の可能性があるのでしょうか。
1-1.心の病気
心の病気の原因としてあげられるもののひとつに慢性疲労症候群があります。
慢性疲労症候群
慢性疲労症候群は別名、筋痛性脳脊髄炎ともいいます。
何の前触れもなく強い倦怠感を自覚し、それとともに関節痛、筋肉痛、頭痛、微熱、脱力感などが数カ月にわたって続き、健康的な社会生活が困難になる疾患です。
現時点では詳しい原因がわかっていないため、除外診断で診断するものでかつ明確な治療方法はありません。
日常生活に大きな影響をおよぼしている場合がほとんどで、症状の辛さのほかに周りの人たちから理解が得られないことや、就労に支障をきたすことが大きなストレスとなり、症状をさらに悪化させているケースもあります。
1-2.体のだるさが長引く病気
だるさが続くときには、以下の疾患の可能性もあります。ただし自己判断はせずに病院に相談しましょう
貧血
貧血とは、血液中の赤血球にあるヘモグロビンの濃度が低下している状態を指します。
貧血にはいくつか種類があり、最も多い貧血は鉄分が不足することで起こる鉄欠乏性貧血です。
鉄欠乏性貧血は、体内の鉄が減少してしまうことで酸素を全身に運ぶ力(赤血球の力)が低下し、疲れやすさや頭痛、息切れなどの症状をまねきます。これを予防するには、鉄を食事から摂取することが大切です。動物性食品と植物性食品をバランス良く摂りましょう。
甲状腺の病気
甲状腺とは、甲状腺ホルモンをつくる臓器です。
甲状腺の働きが低下すると、甲状腺ホルモンが不足し、疲れやすくなる、体重が増えやすい、断続的な眠気などのさまざまな症状をともないます。
一方で、甲状腺ホルモンが過剰になると暑がりになり、頻脈になりやすく、痩せやすい、疲れやすいなどの症状が出てきます。
何かしらの症状が疑われたら早めに病院を受診しましょう。
こういった症状が見られたら一度専門の病院を受診しましょう。


 風邪などで高熱を出すと全身がだるくなるという経験は誰でも一度はあるでしょう。
風邪などで高熱を出すと全身がだるくなるという経験は誰でも一度はあるでしょう。 特に病気ではない場合でも体のだるさがあるという人へ、おすすめの対策についてお伝えします。
特に病気ではない場合でも体のだるさがあるという人へ、おすすめの対策についてお伝えします。