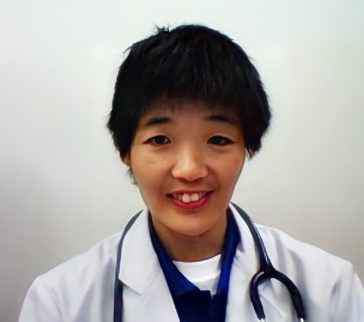肩こりは日々の生活のなかで、多くの方が抱える悩みです。実際に厚生労働省が行なっている「国民生活基礎調査」でも、自覚症状として肩こりを訴える方は多く、女性では1位(人口1,000人あたり113.8)、男性では2位(人口1,000人あたり57.2)に挙げられています。
肩こりは日々の生活のなかで、多くの方が抱える悩みです。実際に厚生労働省が行なっている「国民生活基礎調査」でも、自覚症状として肩こりを訴える方は多く、女性では1位(人口1,000人あたり113.8)、男性では2位(人口1,000人あたり57.2)に挙げられています。
今回は肩こりの原因と解消方法について解説するので、肩こりに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
1.なぜ肩こりが起きるのか
肩こりにはさまざまな原因がありますが、まずは人体の構造が考えられるでしょう。肩は、重たい頭を支える首や2本の腕がつながる場所であるため、それらの重みでコリやすいといわれています。
このことから、日常生活を送るだけでも肩に多少の負担がかかり、肩こりになる可能性があります。
肩こりは頸部や肩から背中にかけて、痛みや違和感があるのがおもな症状です。また、痛みだけでなく、頭痛や吐き気をともなうこともあります。
1-1.肩こりが悪化する際に見られる症状
肩こりは、筋肉の緊張や柔軟性の低下により起こることが多くなっていますが、他の病気により引き起こされることもあります。
ここでは、他の病気が疑われる具体的な症状を紹介するので、これらの症状が見られた際は早めに医療機関を受診しましょう。
2.肩こりのおもな原因とは
 多くの方が悩まされる肩こりですが、その原因はさまざまです。おもな原因としては、以下のものが知られています。
多くの方が悩まされる肩こりですが、その原因はさまざまです。おもな原因としては、以下のものが知られています。
2-1.首や肩の骨・筋肉が原因のケース
-
椎間板ヘルニア
椎間板とは背骨をつなぎ、クッションの役目をする軟骨を指します。その一部が飛び出して神経や脊髄を圧迫するのが椎間板ヘルニアです。頚椎椎間板ヘルニアでは、首の神経が圧迫されて肩に痛みやしびれが出ることがあります。
腰椎や胸椎で椎間板ヘルニアになることもありますが、これらは肩に痛みなどが出る可能性は少ないでしょう。
-
頚椎症、後縦靭帯骨化症
頚椎症とは、椎間板が変形して神経や脊髄を圧迫する病気です。また、後縦靭帯骨化症は背骨を連結している靭帯組織が厚くなり、さらに骨のように硬くなることで脊髄を圧迫します。どちらも、肩や手のしびれ、鈍痛などがおもな症状です。
2-2.首や肩とは別のところが原因のケース
-
内臓の病気や高血圧
首や肩といった直接的な原因でなく、肺の病気などの内臓疾患が原因で肩こりが起こることがあります。また、高血圧が原因で肩の痛みが出ることもあるので注意しましょう。
-
眼精疲労
眼精疲労は目に疲れを感じる状態を指し、目の痛みや充血といった症状のほか、肩こりや頭痛、疲労感などの症状が現れることがあります。近視や遠視、老眼などがあると目の周囲の筋肉が緊張しやすいため、眼精疲労が生じやすくなるでしょう。また、白内障や緑内障も眼精疲労の原因になり、肩こりにつながることもあります。
-
その他
顎関節症や耳鼻科系の疾患が、肩こりの原因になることがあります。その他、更年期障害や自律神経失調症なども肩こりの原因になるとされる疾患です。
2-3.原因がはっきりしないケース
3.つらい肩こりを解消する方法
 肩こりを解消するには、原因や対策を知ることが大切です。ここでは、つらい肩こりを解消するための具体的な方法を紹介します。
肩こりを解消するには、原因や対策を知ることが大切です。ここでは、つらい肩こりを解消するための具体的な方法を紹介します。
3-1.危険な肩こりの可能性があればすぐに検査する
「肩こりが悪化する際に見られる症状」で紹介した、2つの症状のいずれかが該当する方は、重大な病気にかかっている可能性があります。これらのサインが見られたら「肩こり程度」と軽く考えず、早めに医療機関を受診しましょう。
3-2.肩こりの原因を探す
肩こりの原因がわかれば、それを治療することで肩こりが治る可能性があります。肩こりには、椎間板ヘルニアのような脊髄の病気や内臓疾患、眼精疲労などさまざまな原因が考えられるため、医療機関で検査を受けることが大切です。
また、日々の生活に原因が隠れているかもしれないので、普段の姿勢や視力をチェックしてみましょう。
3-3.対症療法を行なう
原因の病気を治療しても肩こりが続いたり、器質的原因が見つからない本態性肩こりであったりする場合は、対症療法を行なうことで痛みを和らげることができます。自分でできる対症療法は、以下のようなものです。
-
同じ姿勢を長く続けない
仕事や勉強などで長く同じ姿勢でいると、肩こりの原因になります。また、姿勢の悪さも肩こりにつながるので、パソコンやスマートフォンを操作するときの姿勢をチェックしてみましょう。
-
蒸しタオル、温水シャワーなどで温める
慢性的な肩こりは、温めて血行を良くすることで痛みが軽減するといわれています。蒸しタオルやカイロ、シャワーなどを活用してみましょう。
-
肩の体操を行なう
東京都医師会健康スポーツ医学委員会で作成された『外来で指導できるロコモ体操』というパンフレット内では、短時間でできる体操が紹介されています。ゆっくりと肩を上下する、回すといった内容がイラスト付きで掲載されているので、日課として続けてみるとよいでしょう。
肩こりは医療機関にご相談を
肩こりは、原因の器質的疾患がない本態性肩こりだけでなく、脊髄など、さまざまな疾患が原因となって起こることがあります。そのため、肩こりを治すには医療機関を受診して原因となる疾患の有無を確認し、必要であれば対症療法を続けることが大切です。
肩こりに悩んでいる方は、医療機関と相談のうえ、自分ができることから始めてみてはいかがでしょうか。
監修者情報
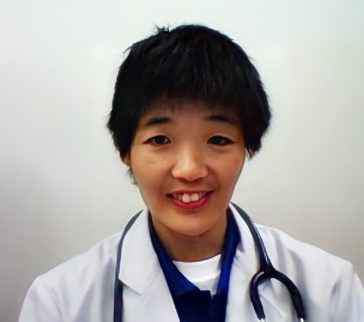
氏名:豊田早苗(とよだ・さなえ)
とよだクリニック院長。鳥取大学医学部卒。精神科・心療内科・内科・神経内科(認知症、物忘れ)の診療を担当している。総合診療医学会、認知症予防学会、精神医学会などに所属。現在は医師業務の傍ら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


 肩こりは日々の生活のなかで、多くの方が抱える悩みです。実際に厚生労働省が行なっている「国民生活基礎調査」でも、自覚症状として肩こりを訴える方は多く、女性では1位(人口1,000人あたり113.8)、男性では2位(人口1,000人あたり57.2)に挙げられています。
肩こりは日々の生活のなかで、多くの方が抱える悩みです。実際に厚生労働省が行なっている「国民生活基礎調査」でも、自覚症状として肩こりを訴える方は多く、女性では1位(人口1,000人あたり113.8)、男性では2位(人口1,000人あたり57.2)に挙げられています。 多くの方が悩まされる肩こりですが、その原因はさまざまです。おもな原因としては、以下のものが知られています。
多くの方が悩まされる肩こりですが、その原因はさまざまです。おもな原因としては、以下のものが知られています。
 肩こりを解消するには、原因や対策を知ることが大切です。ここでは、つらい肩こりを解消するための具体的な方法を紹介します。
肩こりを解消するには、原因や対策を知ることが大切です。ここでは、つらい肩こりを解消するための具体的な方法を紹介します。