1.低血糖について
低血糖とは、血液内のブドウ糖の濃度である血糖値が、必要以上に低くなる状態をいいます。
血糖値は、健康な人でも食前と食後で変動しますが、通常の場合、食前の血糖値はおよそ70~100㎎/dLの範囲に保たれています。
空腹になって血糖値が下がると、グルカゴンなどのホルモンが働いて血糖値が正常に戻ります。そのため、健康な人であれば、空腹時でも70㎎/dL未満まで下がることはほぼありません。
血糖値が60~70㎎/dL未満になると、冷や汗、寒気、気持ち悪さ、強い空腹感、動悸や手足の震え、頭痛、目のちらつき、ふらつき、脱力感などの症状が出ます。
これらの多くは交感神経症状と呼ばれ、血糖値を上げる働きのあるアドレナリンやグルカゴンが分泌されることで生じる症状です。
2.低血糖になった際の対処法
 低血糖になった場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか。
低血糖になった場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか。
まずは口から糖分を摂ることができるかどうかで、対処法が変わります。
先述したように低血糖状態と思われる症状が出た場合は、なるべく早めに吸収が速い、砂糖または砂糖を含んでいる飲み物などの糖分を摂取しましょう。通常であれば5分以内に症状は改善されます。
ただし、α-グルコシダーゼ阻害薬を服用している人はブドウ糖を摂りましょう。
意識障害があり、口から糖分を摂取できない場合は、すぐに医療機関へ相談してください。可能であれば、歯肉や唇にブドウ糖を塗り付けて対処しましょう。
3.低血糖の予防方法
 ここでは、低血糖を予防する方法を解説します。
ここでは、低血糖を予防する方法を解説します。
3-1.糖分摂取を無理に控えない
低血糖は食事の時間が遅れたときや、早朝・昼食・夕食の空腹時、就寝時などにもみられます。
そのため、過剰に食事を制限しすぎないようにしましょう。
すでに糖尿病と診断されている場合は、血糖値のコントロールが健常人よりも乱れやすいため、低血糖になるリスクが高まります。
特に薬によって血糖値を下げるための治療を始めている人は、低血糖になる可能性が高いことを意識しておきましょう。
3-2.無理な運動はしない
強度の高い運動を長時間にわたって続けると、低血糖になるリスクが高まります。
そのため、無理に激しい運動をしないように注意しましょう。
特に運動しているときに低血糖になりやすい人は、空腹時の運動は控えてください。
低血糖は最悪の場合、命にも関わります。低血糖により意識が低下した場合でもすぐに対処できるよう、家族の人たちも準備をしておくことが大切です。
低血糖は早めの対処と予防を心がけましょう
低血糖とは、血液内のブドウ糖の濃度である血糖値が、必要以上に低くなる状態です。
低血糖状態になると、体内で血糖値を上げようとするアドレナリンやグルカゴンなどのホルモンが働き、冷や汗や手足の震え、頭痛やふらつきなどの症状が起こります。
低血糖になった際の対処法は、口から糖分を摂れる状態であれば、吸収されやすい糖分を摂りましょう。
糖分を摂っても改善されない場合や、意識障害などで口から糖分が摂れない場合には、すぐに医療機関へ相談してください。
低血糖は、命に関わる可能性があります。そのため、周りの人も何かあったらすぐに対応できるように普段から準備をしておきましょう。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


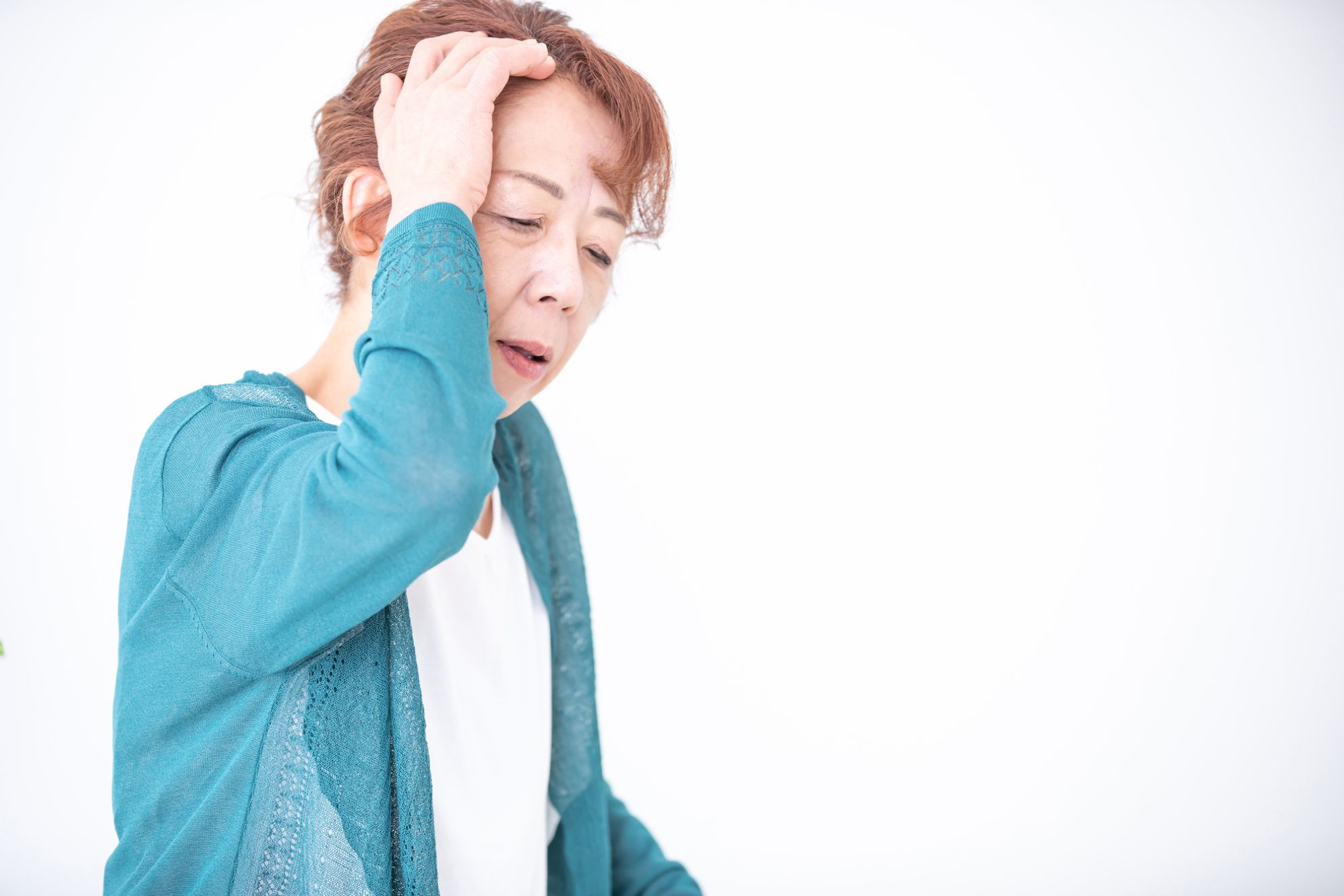 血液内に存在するブドウ糖が低すぎると、低血糖状態を引き起こします。
血液内に存在するブドウ糖が低すぎると、低血糖状態を引き起こします。 低血糖になった場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか。
低血糖になった場合は、どのような対応をすればよいのでしょうか。 ここでは、低血糖を予防する方法を解説します。
ここでは、低血糖を予防する方法を解説します。







