1.寝不足で吐き気がするのはなぜ?
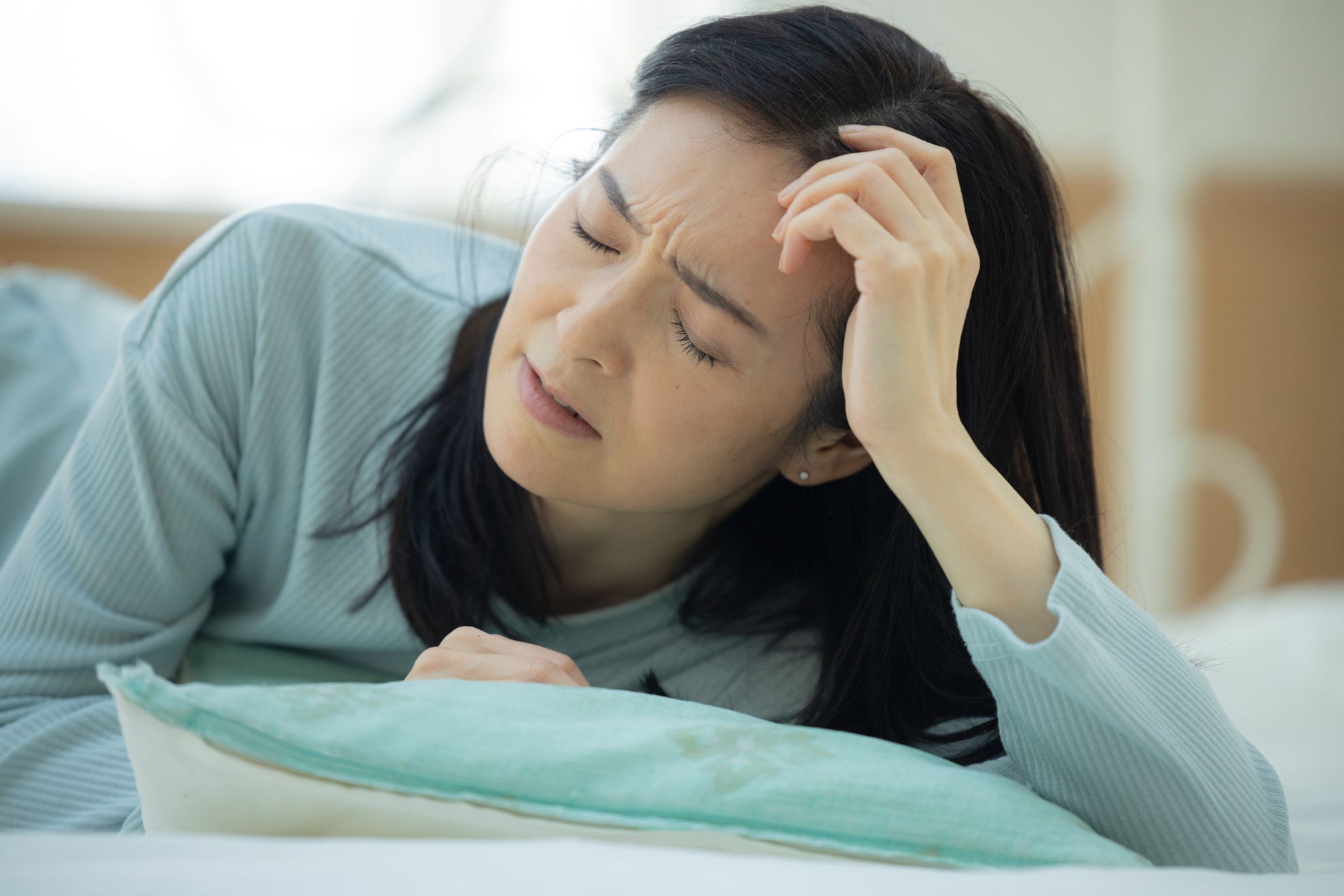 睡眠不足による体への影響はさまざまあり、吐き気もそのうちの一つです。
睡眠不足による体への影響はさまざまあり、吐き気もそのうちの一つです。
睡眠不足は記憶力ややる気の低下、ホルモン分泌の変化などさまざまな悪影響をおよぼします。その一つである自律神経系への影響が、吐き気につながるといわれています。
自律神経には交感神経と副交感神経に分かれており、この2つがバランス良く働くことで、人間の体は正常な状態を保っています。
しかし、不規則な生活が続くと自律神経のバランスが崩れ、頭痛や動悸、立ちくらみ、倦怠感、下痢、便秘、冷えなどさまざまな症状が現れます。
吐き気も同様に、この自律神経系の不調が胃腸に影響し、食物の消化に関係することで現れることがわかっています。リラックスできないと消化吸収はうまくできません。交感神経と副交感神経のバランスが崩れると消化がうまくいかず、吐き気につながるのです。
2.寝不足や疲労回復におすすめの栄養素と食べ物
 では、睡眠不足を解消するためには、どのような食べ物をとればよいのでしょうか。
では、睡眠不足を解消するためには、どのような食べ物をとればよいのでしょうか。
ここでは、睡眠や疲労回復に良いとされる栄養素や食材を紹介します。
2-1.乳酸菌
乳酸菌の適度な摂取は、睡眠に良いことがわかっています。
そのメカニズムは解明されていないものの、夜行性のマウスに乳酸菌を与え続けたところ、夜間に行動量が減ったという研究結果もあります。
2-2.ビタミンB1
ビタミンB1は、疲労回復に役立つ栄養素です。
糖質をエネルギーに変えることにより、体を疲れにくくすることがわかっています。
豚肉やうなぎなどに含まれており、にんにくやたまねぎ、ねぎなどに含まれるニオイの成分であるアリシンと一緒に摂るとビタミンB1の吸収率が上がります。
2-3.クエン酸
クエン酸は、体内でエネルギー生成をサポートする栄養素です。
体内にはATP(アデノシン三リン酸)と呼ばれる物質が存在しており、人間の体はATPが分解されたときに発生するエネルギーにより生命が維持されています。
このATPは体を動かすエネルギーをつくるTCA回路というシステムで産生されています。クエン酸にはこのTCA回路を動きやすくする効果があるため、疲労感を軽減する作用があるとされています。
レモンやグレープフルーツなどの柑橘類、お酢などに多く含まれている成分です。
2-4.コエンザイムQ10
コエンザイムQ10は、エネルギーを作り出すのになくてはならない栄養素です。
ユビキノンやユビデカレノンとも呼ばれており、油に溶けやすいビタミンのような物質です。
体内で合成されるものの、加齢にともなって減少するとされており、特に心臓などの活発に動く臓器での減少量が著しいことがわかっています。
食品から摂取することは可能ですが、一日30mgのコエンザイムQ10を食品から摂取する場合、ブロッコリーなら約3.5kg、牛肉なら約1kg、イワシなら約6匹を食べなければいけません。
また、コエンザイムQ10を効率良く摂取するには、ゴマに含まれるセサミンと一緒に摂ることが有効です。
2-5.L-カルニチン
L-カルニチンは脂肪の燃焼を助け、エネルギー産生をサポートする栄養素です。
脂肪酸は体内のミトコンドリア膜という場所でエネルギーとなりますが、その前段階として、L-カルニチンと結合しなければミトコンドリア膜には入れません。
このことから、L-カルニチンは脂肪燃焼系アミノ酸とも呼ばれています。
食品では、おもにラム肉やかつお、赤貝、牛肉などに含まれています。
睡眠不足や疲労からくる吐き気には食べ物で対策しよう
寝不足が続くと、自律神経から胃腸への影響が出てしまい、吐き気につながります。
寝不足の改善には、睡眠に良い効果があるといわれている乳酸菌を摂取するとよいでしょう。
その他、ビタミンB1、クエン酸、コエンザイムQ10、L-カルニチンなど、疲労感軽減に効果があるとされている食べ物や栄養素も取り入れ、吐き気を改善しましょう。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
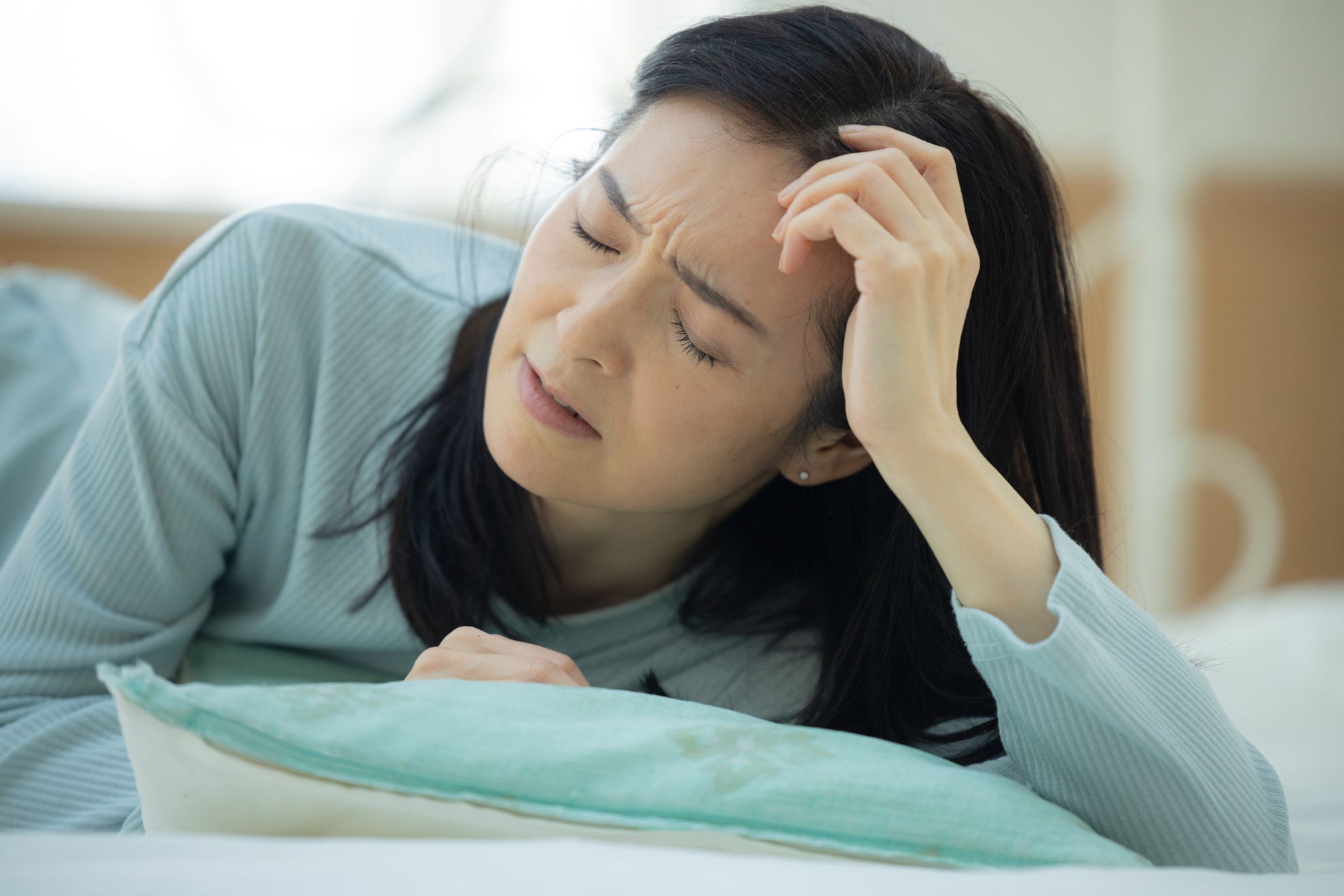 睡眠不足による体への影響はさまざまあり、吐き気もそのうちの一つです。
睡眠不足による体への影響はさまざまあり、吐き気もそのうちの一つです。

 睡眠時間が足りていなかったり不規則な生活が続いたりすると、さまざまな不調が現れがちです。
睡眠時間が足りていなかったり不規則な生活が続いたりすると、さまざまな不調が現れがちです。 では、睡眠不足を解消するためには、どのような食べ物をとればよいのでしょうか。
では、睡眠不足を解消するためには、どのような食べ物をとればよいのでしょうか。






