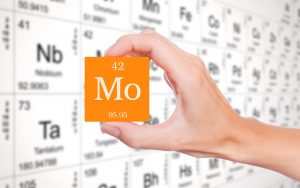1.ヘム鉄とは?
 鉄のうち、赤身肉や魚などに多く含まれているものをヘム鉄といい、タンパク質と結合した状態で存在しています。
鉄のうち、赤身肉や魚などに多く含まれているものをヘム鉄といい、タンパク質と結合した状態で存在しています。
一方で、非ヘム鉄はヘム鉄以外のタンパク質に結合していない無機鉄のことをいい、野菜や卵、牛乳などに多く含まれている成分です。
ヘム鉄は、非ヘム鉄に比べて体内での吸収率が高い特徴があります。鉄は血液中のヘモグロビンの構成成分であり、酸素の運搬に重要な役割を果たしています。鉄が不足すると貧血となり、疲れやすくなったり、頭痛や息切れなどの症状が出たりすることはみなさんもご存知でしょう。鉄を効率良く吸収できるヘム鉄は、貧血を防ぐために積極的に体に摂取したい栄養素です。
鉄の必要量は性別や月経の有無によって異なり、以下のように設定されています。
男性
-
・18~74歳:7.5mg
-
・75歳以上:7.0mg
女性
-
・18~49歳:10.5mg
-
・50~64歳:11.0mg
月経のない女性
-
・18~64歳:6.5mg
-
・65歳以上:6.0mg
参照:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
2.ヘム鉄を多く含む食品
 ヘム鉄は、赤身肉や魚に多く含まれます。
ヘム鉄は、赤身肉や魚に多く含まれます。
-
・あゆ(焼き):5.5mg
-
・めざし(焼き):4.2mg
-
・牛肉(焼き):3.5mg
-
・まぐろ(刺身):0.8mg
鉄の吸収を高めるビタミンC、血球の合成に必要なビタミンB12や葉酸も一緒に摂取しましょう。
逆に、米ぬかに含まれるフィチン酸、紅茶や緑茶に含まれるタンニン、ほうれん草に含まれるシュウ酸は鉄の吸収を阻害するため、食べ合わせに注意しなければなりません。
3.ヘム鉄を摂ることができるおすすめレシピ
ここからは、ヘム鉄を含む食品を使ったレシピを2品ご紹介します。
3-1.まぐろのステーキ にんにくしょうゆがけ
まず紹介するレシピは、にんにくの風味豊かな「まぐろのステーキ にんにくしょうゆがけ」です。
【材料】2人分
-
・まぐろ(刺身用) 120g
-
・にんにく 1かけ
-
・オリーブ油 大さじ1
-
・塩 適量
-
・こしょう 適量
-
・バター 10g
【A】
-
・しょうゆ 大さじ1.5
-
・みりん 大さじ1.5
-
・酒 大さじ1
【作り方】
-
1. まぐろに塩、こしょうで下味をつけます。にんにくはみじん切りにしておきましょう。
-
2. フライパンにオリーブ油大さじ1/2を熱したあと、まぐろを入れて強めの中火で焼きます。両面に焼き色が付いたら取り出してください。
-
3. フライパンに残りのオリーブ油とにんにくを入れ、中火で炒めます。
-
4. にんにくの香りがしてきたら【A】を加えます。1~2分煮立てたあと、バターを入れて溶けるまで加熱し、ソースを作ります。
-
5. まぐろを食べやすい大きさにカットし、皿に盛り付けてソースをかけたら完成です。
刺身用のまぐろを使用する場合は、まぐろへの火の入れ方はお好みで調整するとよいでしょう。
3-2.牛肉ときのこのクリーム煮
次に紹介するのは、ヘム鉄が豊富に含まれている牛肉を使った「牛肉ときのこのクリーム煮」です。
【材料】2人分
-
・牛切り落とし肉 180g
-
・マッシュルーム 5個
-
・しめじ 1/2株
-
・エリンギ 1本
-
・バター 10g
-
・水 100ml
-
・顆粒コンソメ 小さじ1/2
-
・生クリーム 100ml
-
・塩 適量
-
・こしょう 適量
-
・パセリ(みじん切り) 適量
【作り方】
-
1. 牛切り落とし肉は、食べやすい大きさにカットします。
-
2. エリンギは食べやすいサイズに切ってください。マッシュルームは薄切りに、しめじは石突きを取ってほぐします。
-
3. フライパンにバターを入れて熱します。きのこは中火で炒め、しんなりしてきたら牛肉を入れてさらに炒めます。
-
4. 牛切り落とし肉の色が変化したら、水、顆粒コンソメを入れてください。
-
5. 煮立ったら生クリームを入れます。4~5分程度、弱めの中火で煮たら、塩、こしょうを加えて味を調えましょう。
-
6. 器に盛り付け、みじん切りにしたパセリを散らしたらできあがりです。
きのこを炒めるときは、焼き色が付き過ぎないようにするのがポイントです。
ヘム鉄を意識して食生活に取り入れよう
今回は、ヘム鉄の概要や一日の摂取目安量、ヘム鉄を多く含む食品を使ったおすすめレシピを紹介しました。
鉄のうち、赤身肉や魚などに多く含まれているものをヘム鉄といい、タンパク質と結合した状態で存在する成分をいいます。
ヘム鉄は非ヘム鉄に比べて体内での吸収率が高い特徴があり、貧血を予防するために積極的に摂取したい栄養素です。
今回紹介したレシピを参考に、ヘム鉄を効率良く摂取していきましょう。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。
 鉄のうち、赤身肉や魚などに多く含まれているものをヘム鉄といい、タンパク質と結合した状態で存在しています。
鉄のうち、赤身肉や魚などに多く含まれているものをヘム鉄といい、タンパク質と結合した状態で存在しています。

 みなさんは、ヘム鉄と呼ばれる成分を知っていますか?
みなさんは、ヘム鉄と呼ばれる成分を知っていますか? ヘム鉄は、赤身肉や魚に多く含まれます。
ヘム鉄は、赤身肉や魚に多く含まれます。