1.生活習慣病とは
生活習慣病とは、生活習慣が原因となり発症する病気の総称を指します。
かつては「成人病」と呼ばれていましたが、成人でなくとも発症の可能性があるため「生活習慣病」と改称されました。
なお、「成人病」と呼ばれていた疾患と、「生活習慣病」における疾患の多くは重複しています。
しかし、生活習慣病が「生活習慣」に着目した疾患であることに対し、成人病は「加齢」に着目した疾患群であるため、概念的に異なる点に注意が必要です。
生活習慣は、おもに食事や運動・睡眠・喫煙・ストレスなどのことです。生活習慣病には、これらの要素が深く関わっているといわれています。生活習慣病に関しては、生活習慣を改善することで、生活習慣病を予防する一次予防に加え、病気の早期発見や早期治療といった二次予防の2軸で対策することが重要になります。
2.生活習慣病の種類
 生活習慣病のおもな疾患には、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などがあります。最近では、フレイルなども生活習慣病ではないかといわれています。以下で代表的な生活習慣病の特徴を確認してみましょう。
生活習慣病のおもな疾患には、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などがあります。最近では、フレイルなども生活習慣病ではないかといわれています。以下で代表的な生活習慣病の特徴を確認してみましょう。
-
糖尿病
糖尿病は体内に取り込まれたブドウ糖を、エネルギーとして上手く利用できず血糖値が上昇してしまうことを指します。発症する原因としては、過食や運動不足などによりインスリンの作用が低下することとされています。
症状が悪化すると腎臓機能の低下による血液透析が必要になり、眼底出血を引き起こし失明してしまう可能性もあります。
-
高血圧症
生活習慣病の一つである高血圧症は、血管に与える圧力が規定値よりも高くなってしまう症状を指します。血管に高い圧力がかかり続けると、血管壁がダメージを負い循環器疾患を発症してしまう可能性が高まります。
高血圧症の原因としては、肥満や塩分の過剰摂取、喫煙などがあります。
-
脂質異常症
脂質異常症は、血液内の中性脂肪やコレステロールが正常値以上存在している状態を指します。脂質異常症が進行すると、血液の流れが悪くなり最終的に致命的な疾患を患うことに繋がる可能性があります。
脂質異常症は、バターやラードなどに含まれる飽和脂肪酸の過剰摂取や、カロリーの高い食べ物の摂り過ぎ、運動不足などが原因として考えられます。
3.高齢者が特に生活習慣病の予防が大切な理由とは?
 高齢者の生活習慣病は、ADL(日常生活動作)の低下や認知機能の障害などを招くといわれています。そのため、早めの生活習慣病予防が大切といえるでしょう。
高齢者の生活習慣病は、ADL(日常生活動作)の低下や認知機能の障害などを招くといわれています。そのため、早めの生活習慣病予防が大切といえるでしょう。
ここからは、高齢者における生活習慣病予防の重要性について、より詳しく解説します。
3-1.ADL(日常生活動作)低下を防ぐ
老年症候群とは、高齢者に多い医療・看護・介護などを必要とする症状の総称です。
高齢者の生活習慣病は、ADL(日常生活動作)の低下といった老年症候群につながりやすいとされています。
ADLとは、移動・排せつ・食事・入浴・更衣・洗面などの日常生活において必要な動作のことです。
ADLと身体・認知機能、精神、社会環境はお互いに作用し合っているため、一つでも機能が低下するとADLの低下を招く恐れがあります。
特に生活習慣病の一つでもある糖尿病を発症した場合、ADLの低下・フレイル・サルコペニア・転倒・低栄養などの老年症候群を招く確率がおよそ2倍になるといわれています。
3-2.介護者の負担軽減
高齢者の生活習慣病は、食事や薬の服用、注射などのセルフケアが難しいため、介護者が代わりに行なう必要があります。
しかし、介護者の負担が増えれば増えるほど、患者自身の精神状態やQOL(生活の質)の低下にも影響し、治療の継続が困難になりかねません。
このことから、高齢者の生活習慣病の治療においては、血糖値や血圧、脂質のコントロールによる合併症予防に加えて、老年症候群を予防して、患者自身だけでなく介護者の負担を減らすことも重要です。
生活習慣病には早めの対策を心がけましょう
生活習慣病は、食事・運動・睡眠などの生活習慣が原因となる疾患の総称です。具体的な生活習慣病には、肥満や糖尿病・高血圧症・脂質異常症などがあります。
特に高齢者が生活習慣病を発症した場合には、ADL(日常生活動作)の低下などといった老年症候群をきたしやすかったりします。
老年症候群などを患うと介護者の負担も増えてしまい、治療の継続が難しくなるという悪循環に陥る可能性も出てくるでしょう。
そうならないようにするためにも、食事や運動などの生活習慣を見直し、早めに生活習慣病を予防していくことが大切です。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


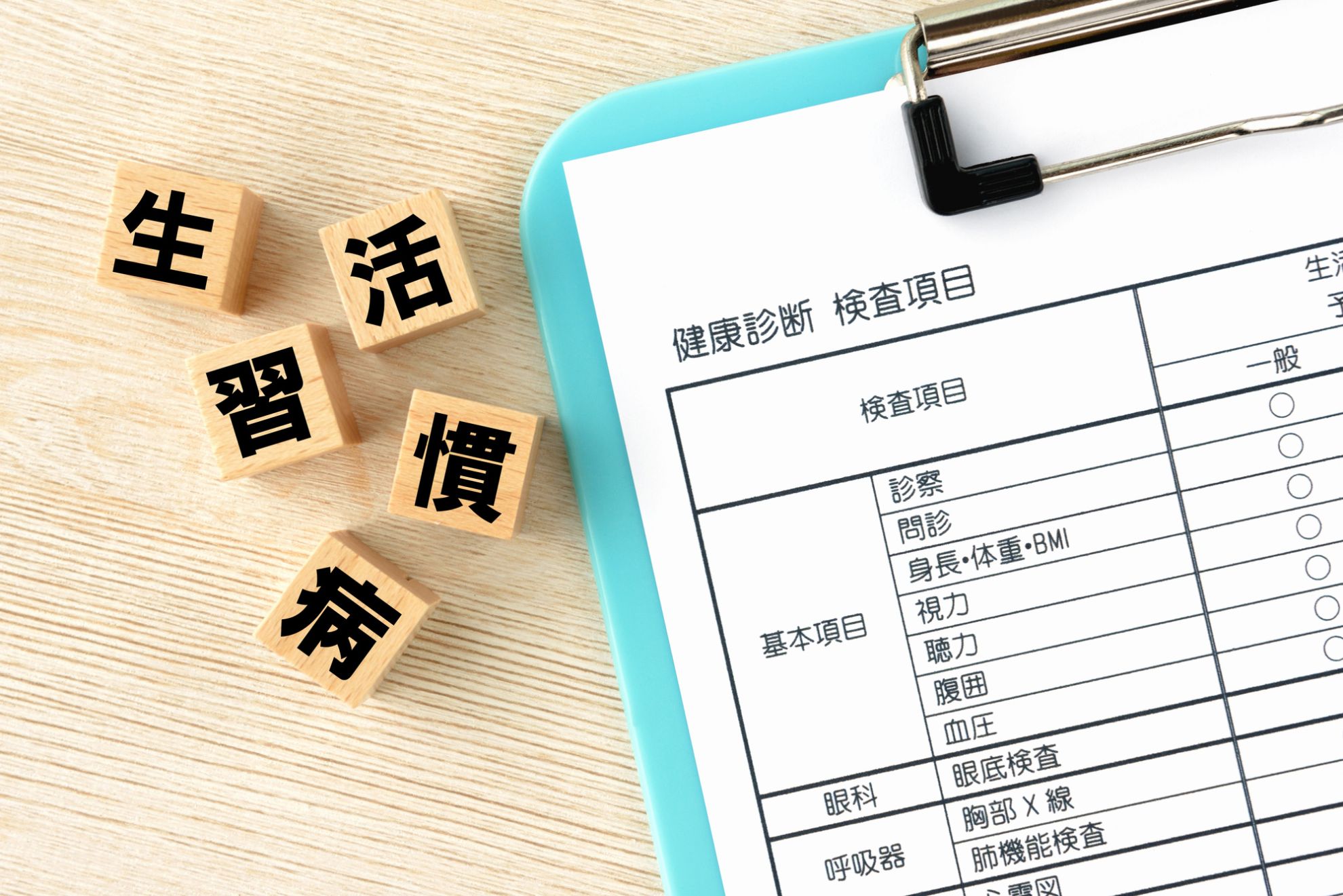 「生活習慣病」はその名のとおり、生活習慣が原因で起こる疾患のことです。
「生活習慣病」はその名のとおり、生活習慣が原因で起こる疾患のことです。 生活習慣病のおもな疾患には、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などがあります。最近では、フレイルなども生活習慣病ではないかといわれています。以下で代表的な生活習慣病の特徴を確認してみましょう。
生活習慣病のおもな疾患には、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などがあります。最近では、フレイルなども生活習慣病ではないかといわれています。以下で代表的な生活習慣病の特徴を確認してみましょう。
 高齢者の生活習慣病は、ADL(日常生活動作)の低下や認知機能の障害などを招くといわれています。そのため、早めの生活習慣病予防が大切といえるでしょう。
高齢者の生活習慣病は、ADL(日常生活動作)の低下や認知機能の障害などを招くといわれています。そのため、早めの生活習慣病予防が大切といえるでしょう。






