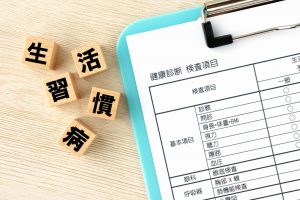1.生活習慣病の予防が大切な理由
 生活習慣病とは、食生活・運動不足・ストレス・喫煙などの生活習慣が要因となって起こる病気の総称です。
生活習慣病とは、食生活・運動不足・ストレス・喫煙などの生活習慣が要因となって起こる病気の総称です。
おもに、肥満症や脂質異常症・糖尿病・高血圧症などが生活習慣病と呼ばれています。これらの生活習慣病が重症化することで、重篤な疾患につながる可能性があります。
生活習慣病は健康長寿を阻害する最も大きな要因となるため、発症や重症化を予防することは極めて重要です。
2.生活習慣病の予防方法
 ここからは生活習慣病の予防について、食事・運動・睡眠それぞれの項目について解説します。
ここからは生活習慣病の予防について、食事・運動・睡眠それぞれの項目について解説します。
2-1.食事
生活習慣病予防のためには、食生活の見直しが重要です。また、高齢者の生活習慣においては、不規則な食生活や偏った過栄養だけでなく、低栄養にも注意しなければなりません。
特に75歳以上の後期高齢者は低栄養をきたしやすく、食事を減らして減量するとタンパク質不足でサルコペニアを招くおそれもあります。
そのため、エネルギー制限よりもバランスのとれた食事を摂ることが大切です。炭水化物・タンパク質・脂質のバランスがとれていて、ビタミン・ミネラル・食物繊維を十分に摂れるような食事を心がけましょう。
特に代謝の補酵素でもあるビタミンB群やビタミンDなどが不足した場合は、サルコペニアやフレイルを引き起こしやすくなるため注意が必要です。
2-2.運動
日頃から運動を行なうことは、生活習慣病の予防につながります。
予防の一環で運動施策を推進する厚生労働省によれば、運動習慣のある人とは「1回あたり30分以上の運動を週2回以上実践し、1年以上継続している者」とされています。
以下で、具体的な運動の種類や効果を見ていきましょう。
-
生活習慣病と運動効果
活動量を増やすことや、ウォーキングやラジオ体操など有酸素運動を取り入れることで、エネルギーが消費されて内臓脂肪が減りやすくなります。
また、運動による効果は肥満の予防・改善だけでなく、血糖値・脂質・血圧の状態が改善されることも期待されています。
運動は身体機能の維持・向上につながるほか、ストレス発散など精神面にも影響するため、積極的に体を動かすとよいでしょう。
-
日常でも効果的な運動習慣をつけるポイント
普段から通勤時や買い物のタイミングなどで、なるべく積極的に歩くことも大切です。
歩くときには大股で早歩きをしたり、家事や仕事の合間にストレッチや筋力トレーニングを行なったりすることも効果的な運動習慣につながるでしょう。
2-3.睡眠
睡眠の質は、生活習慣病の発症にも関係します。
-
睡眠不足と生活習慣病
健康な人でも、睡眠不足(4時間睡眠)を2日間続けると、10時間眠った日に比べて食欲が増大しやすいことがわかっています。
これは、睡眠不足により食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少し、食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌が増えてしまうためです。
実際に慢性的な寝不足状態の人は、糖尿病などの生活習慣病に罹るリスクが高まりやすいことがわかっています。
-
睡眠障害と生活習慣病
睡眠時無呼吸症候群などの「睡眠障害」を持っている人は、生活習慣病のリスクが高まる可能性が示唆されています。
例えば、睡眠時無呼吸症候群の人は、夜間の呼吸が妨げられることで低酸素血症や代謝異常、酸化ストレスや炎症、交感神経の緊張などが起こりやすくなります。その結果として、高血圧などの生活習慣病のリスクも高まってしまうのです。
そのため、生活習慣病の予防のためには睡眠時間を十分に確保することや、質の良い睡眠をとることが重要といえるでしょう。
生活習慣病の予防は早めに行ないましょう
生活習慣病は、場合によっては重篤な疾患を招く可能性があります。
また、健康長寿を阻害する原因にもなるため、生活習慣病を予防することは非常に大切です。
日常生活において適度な運動や、バランスのとれた食事、質の良い睡眠を心がけることで、生活習慣病の予防につながります。
今回お伝えした予防のポイントもぜひ参考にしてみてください。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
 生活習慣病とは、食生活・運動不足・ストレス・喫煙などの生活習慣が要因となって起こる病気の総称です。
生活習慣病とは、食生活・運動不足・ストレス・喫煙などの生活習慣が要因となって起こる病気の総称です。

 健康診断の結果を見て、生活習慣病を身近に感じたことがある方もいるのではないでしょうか。
健康診断の結果を見て、生活習慣病を身近に感じたことがある方もいるのではないでしょうか。 ここからは生活習慣病の予防について、食事・運動・睡眠それぞれの項目について解説します。
ここからは生活習慣病の予防について、食事・運動・睡眠それぞれの項目について解説します。