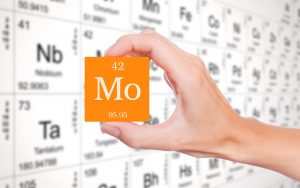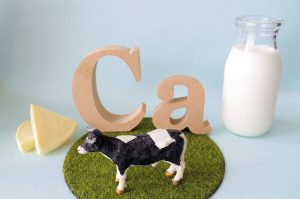1.そもそも食物繊維とは?
食物繊維とは炭水化物の一種です。ご飯やパンなどに多く含まれているデンプンは「消化される炭水化物」ですが、食物繊維は「消化されない炭水化物」にあたります。食物繊維は、人間の体内では消化されずエネルギーにはならないため、あまりカロリーはありません。
エネルギー源にはならない食物繊維ですが、体の調子を整えるために重要な役割を担っています。
まず挙げられるのは整腸作用です。食物繊維の一種であるオリゴ糖は、腸内に存在する善玉菌を増やす作用があります。
次に、便通をスムーズにして便秘を予防します。その他、肥満や高血圧、糖尿病などの予防や改善にも役立ちます。
これらの働きから、食物繊維は「第6の栄養素」とも呼ばれています。
2.食物繊維は水溶性と不溶性に分けられる
 食物繊維には大きく分けて、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。どちらも消化・吸収はされないものの、健康を維持するためには欠かせない栄養素です。
食物繊維には大きく分けて、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。どちらも消化・吸収はされないものの、健康を維持するためには欠かせない栄養素です。
ここでは、それぞれの特徴と多く含まれる食品を紹介します。
2-1.水溶性食物繊維
水溶性食物繊維とは、食物繊維のうち水に溶ける性質があるものを指し、水に溶けるとゼリーのような状態になるのが特徴です。水溶性食物繊維によって、小腸が栄養をゆっくり吸収するようになり、食後に血糖値が急激に上がるのを抑えます。
その他に、コレステロールやナトリウムとくっついて体の外に出すことで、血中コレステロール値の低下や高血圧予防にも役立ちます。低カロリーである食物繊維の積極的な摂取は肥満予防につながるため、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の対策にもつながるでしょう。
おもな水溶性食物繊維の種類はペクチン、アルギン酸、ポリデキストロース、アガロース、アガロペクチン、グルコマンナン、カラギーナンなどです。果物のほか、にんじんやキャベツなどのやわらかい繊維の野菜、コンブやワカメといった海藻類などに多く含まれています。
2-2.不溶性食物繊維
不溶性食物繊維とは、食物繊維のうち水に溶けにくい性質を持つものです。
水分を吸って膨らみ、便のかさが増えることで、内側から大腸を刺激して排便リズムを整えます。さらに、排便時に有害物質を排出して腸が掃除されるため、大腸に関する病気のリスク軽減にもつながります。
おもな不溶性食物繊維の種類はセルロース、キチン、ヘミセルロース、キトサンなどです。不溶性食物繊維をとりたいときは、たけのこなどの固い繊維の野菜や根菜類、きのこ類や豆類を積極的に食事に取り入れるとよいでしょう。
3.食物繊維を摂取しすぎるとどうなる?
 食物繊維をとりすぎると、その性質からミネラルなどの栄養素の吸収を邪魔してしまうことがあります。その他、便がやわらかくなりすぎるケースも考えられます。
食物繊維をとりすぎると、その性質からミネラルなどの栄養素の吸収を邪魔してしまうことがあります。その他、便がやわらかくなりすぎるケースも考えられます。
しかし、近年の日本人における食物繊維の摂取量は減少傾向にあるため、通常の食生活を送っていれば摂取しすぎる心配はほとんどありません。
4.食物繊維が不足した場合は?
食物繊維が不足すると便秘になりやすくなったり、肥満になりやすくなったりします。その他に、糖尿病のリスクを高める可能性もあります。
厚生労働省によると、18~64歳における一日あたりの食物繊維の目標量は、男性で21g以上、女性で18g以上と設定されています。
日本人の多くが食物繊維不足の傾向があるため、現在の食事に一日あたり3~4gの追加摂取を心がけましょう。
食物繊維のとりすぎに注意して適量を心がけよう
消化・吸収されない炭水化物である食物繊維は、整腸作用のほか、便秘や肥満、糖尿病、高血圧を予防するといわれています。食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がありますが、どちらかに偏らずにバランス良くとるのがポイントです。
現代の日本人の食生活では、食物繊維は不足することはあっても、とりすぎるケースはあまりありません。しかし、過剰摂取では、便がやわらかくなるほか、栄養素の吸収率が低下するおそれがあります。
食物繊維は、第6の栄養素とも呼ばれるくらい健康には大切な成分のため、摂取過剰・摂取不足を避け、適量摂取を心がけましょう。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。


 健やかな毎日を送るために、意識したい栄養素の一つが食物繊維です。食物繊維は、とりすぎても少なすぎても体に影響をおよぼすおそれがあります。
健やかな毎日を送るために、意識したい栄養素の一つが食物繊維です。食物繊維は、とりすぎても少なすぎても体に影響をおよぼすおそれがあります。 食物繊維には大きく分けて、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。どちらも消化・吸収はされないものの、健康を維持するためには欠かせない栄養素です。
食物繊維には大きく分けて、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。どちらも消化・吸収はされないものの、健康を維持するためには欠かせない栄養素です。 食物繊維をとりすぎると、その性質からミネラルなどの栄養素の吸収を邪魔してしまうことがあります。その他、便がやわらかくなりすぎるケースも考えられます。
食物繊維をとりすぎると、その性質からミネラルなどの栄養素の吸収を邪魔してしまうことがあります。その他、便がやわらかくなりすぎるケースも考えられます。