目次
1.アナフィラキシーとは?
アナフィラキシーとは、アレルゲン(アレルギーの原因となるもの)などが体内に侵入して起きる、重篤なアレルギー反応のことです。
皮膚や神経、呼吸器・消化器・循環器など複数の臓器のほか、全身にアレルギー症状が現れます。
特に、血圧低下や意識の低下をともなう症状は「アナフィラキシーショック」といい、迅速に医療機関を受診しないと命に関わるおそれがあります。
 アナフィラキシーとは、あらゆるものが要因となり全身性のアレルギー反応が起こる過敏反応のことです。
アナフィラキシーとは、あらゆるものが要因となり全身性のアレルギー反応が起こる過敏反応のことです。
アレルギー反応にはさまざまな種類や要因がありますが、アナフィラキシーの場合は命の危険をともなう可能性もあるため、特に注意が必要です。
今回は、アナフィラキシーのおもな症状や原因、予防するための方法について解説します。
目次
アナフィラキシーとは、アレルゲン(アレルギーの原因となるもの)などが体内に侵入して起きる、重篤なアレルギー反応のことです。
皮膚や神経、呼吸器・消化器・循環器など複数の臓器のほか、全身にアレルギー症状が現れます。
特に、血圧低下や意識の低下をともなう症状は「アナフィラキシーショック」といい、迅速に医療機関を受診しないと命に関わるおそれがあります。
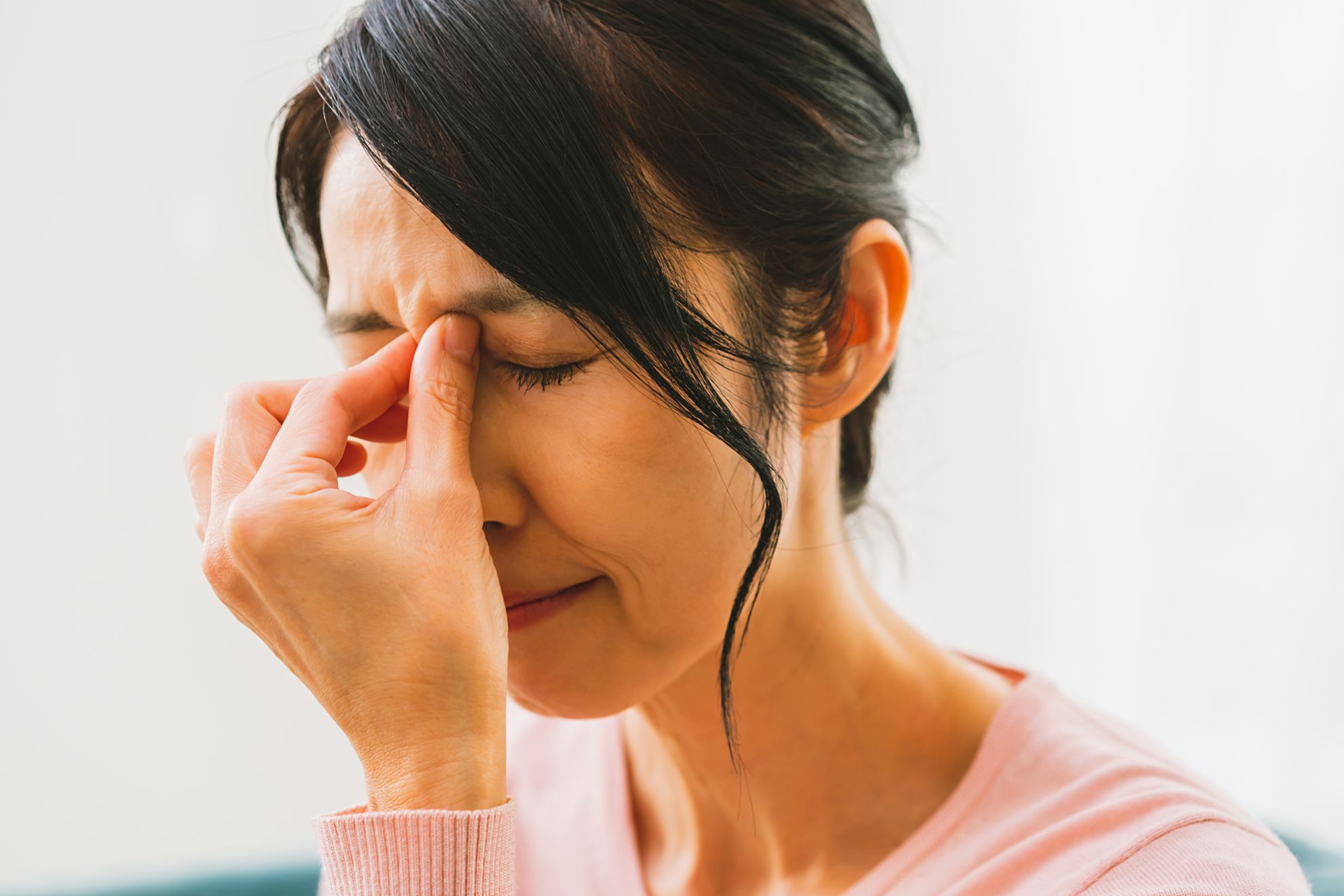 アナフィラキシーになると、どのような症状が起こるのでしょうか。原因についても以下で解説します。
アナフィラキシーになると、どのような症状が起こるのでしょうか。原因についても以下で解説します。
アナフィラキシーの症状には、以下のようなものがあります。
・皮膚:かゆみ、じんましん
・粘膜:結膜の充血、口唇や舌の違和感、のどのかゆみ
・呼吸器:くしゃみ、せき、息苦しさ、声のかすれ
・消化器:腹痛、吐き気
・循環器:血圧の低下、徐脈、頻脈
・神経:頭痛、意識障害
なかでも注意すべきなのは、顔色が悪かったり息苦しさがあったりと、ショック症状がみられる状態です。命の危機があるため、迅速に対応する必要があります。
アナフィラキシーのおもな原因は以下のとおりです。
乳製品、卵、ピーナッツ、小麦、そばによるアレルギーが多く報告されています。また、普段は食べても問題ない食品であっても、疲労や感染症など個人の状態によってはアナフィラキシーが生じるおそれがあります。
アナフィラキシーを起こすことが多い薬剤には、血液製剤、抗菌薬、造影剤、解熱消炎鎮痛薬などが挙げられます。
ハチやアリ、蛾などの昆虫やハウスダストなども要因となり得ます。
 アナフィラキシーは予防できるのでしょうか。種類ごとの予防方法について解説します。
アナフィラキシーは予防できるのでしょうか。種類ごとの予防方法について解説します。
食べ物によるアレルギーの多くは、食べ物に含まれるタンパク質が原因で、皮膚・消化器・呼吸器または全身にアレルギー反応が生じます。特に乳幼児がアナフィラキシーを起こす原因の多くは、食べ物によるアレルギーです。
食物アレルギーを予防するためには、アレルギーを起こす可能性がある食べ物を避けるようにしましょう。
気管支ぜん息とは、ひゅーひゅー、ぜーぜーという音をともなって呼吸困難を繰り返す、発作性の病気です。
ダニやハウスダスト、動物の毛などのアレルゲンに対するアレルギー反応によって気道が炎症を起こし、気道が狭まることで発生しやすくなります。
気管支ぜん息を予防するには、原因となるものを減らすための環境を整えることが重要です。寝具の取り扱いなどに注意しつつ、室内の清掃を十分に行ないましょう。
アトピー性皮膚炎とは、かゆみの強い湿疹ができ、症状の悪化と改善を繰り返すことが特徴の病気です。
悪化する要因としては、ダニやハウスダスト、動物の毛、食べ物、汗、洗剤、生活習慣の乱れ、感染症などさまざまです。アトピー性皮膚炎の多くはさまざまな要因が重なって悪化するため、原因と思われる要素をなるべくなくすことが大切でしょう。
アナフィラキシーは、アレルギー反応のなかでも、命に関わる危険性がある過敏反応です。食べ物や薬剤、昆虫の毒など、日常生活で触れるさまざまなものが要因となります。
なかでも、血圧低下や意識障害をともなう場合は、一刻も早く病院での治療が必要です。疑わしい症状が出たら、すぐに救急搬送を要請しましょう。

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
身体に関するお悩み

体重がそれほど増えたわけではないのに、体がおもい感じがするという経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。
身体に関するお悩み

健康診断で、コレステロールが高めと言われたことはないでしょうか。
身体に関するお悩み

健康な体をつくるには、食事の内容が大きく関わってきます。
身体に関するお悩み

しっかり睡眠時間を確保できない、という悩みも持つ方も多いでしょう。
身体に関するお悩み

居眠り運転や業務効率の低下などにつながる可能性があることから、近年「睡眠時無呼吸症候群」が注目されています。