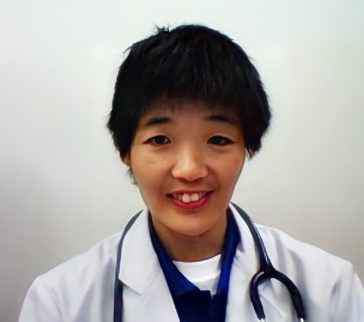1.鉄とは
鉄は、金属元素の一つであり、食品中の鉄は人体に必要なミネラルの一種です。成人の体に存在する量は3~5gで、そのうちの70%は筋肉中のミオグロビンや赤血球のヘモグロビンを構成しています。残りの30%は、筋肉や肝臓、骨髄などに貯蔵されています。
つまり、鉄は、筋肉や赤血球の重要な構成成分であり、人体において必要不可欠なミネラルだといえるでしょう。
2.鉄のおもな働き
血液は血球と血漿に大きく分けられ、血球は血液全体の約45%、残りの55%を血漿が占めています。さらに、血球の約96%が赤血球であり、ヘモグロビンを含んでいます。
ヘモグロビンは、鉄とタンパク質が結び付いた赤色素タンパク質で、血液が赤色である原因です。ヘモグロビンは肺で酸素と結び付き、体内に溜まった二酸化炭素を回収して、酸素を全身に供給する働きを持っています。
また、シトクロムという酵素は構造中に鉄分子を含んでおり、体内で行なわれるさまざまな反応に関わっています。シトクロムは、医薬品の代謝や分解にも関わる酵素でもあるため、体内に取り入れられた医薬品がきちんと効果を発揮するうえでも重要な酵素です。
2-1.鉄不足が身体におよぼす影響
鉄が不足すると、活気がなくなるなど日常生活に悪影響をおよぼすことが知られています。鉄が不足すると赤血球中のヘモグロビンが減少し、ヘモグロビンが減少すると酸素が十分に供給できないため、体調不良につながるなどさまざまな症状が現れます。
3.鉄の1日の摂取目安量
 鉄の必要な摂取量は男女で大きく異なり、月経の有無や妊娠、授乳などが影響します。
鉄の必要な摂取量は男女で大きく異なり、月経の有無や妊娠、授乳などが影響します。
※0~5月は目安量
| 年齢 |
男性 |
女性 |
女性(月経あり) |
| 0~5ヶ月 |
0.5(※) |
0.5(※) |
─ |
| 6~11ヶ月 |
5.0 |
4.5 |
─ |
| 1~2歳 |
4.0 |
4.5 |
─ |
| 3~5歳 |
5.5 |
5.5 |
─ |
| 6~7歳 |
6.5 |
6.5 |
─ |
| 8~9歳 |
8.5 |
8.0 |
─ |
| 10~11歳 |
10.0 |
9.5 |
13.5 |
| 12~14歳 |
11.0 |
10.0 |
14.0 |
| 15~17歳 |
9.5 |
7.0 |
10.5 |
| 18~29歳 |
7.0 |
6.0 |
10.5 |
| 30~49歳 |
7.5 |
6.5 |
11.0 |
| 50~69歳 |
7.5 |
6.5 |
11.0 |
| 70歳以上 |
7.0 |
6.0 |
─ |
| 妊婦 |
─ |
初期+2.5
中期・後期+15.0 |
─ |
| 授乳婦 |
─ |
+2.5 |
─ |
(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに作成)
4.鉄を多く含む食べ物
以下は、鉄を多く含んでいる食品例です。
| ヘム鉄(おもに肉・魚に含まれる鉄) |
| 食品名 |
1食分あたり重量(g) |
鉄含有量(mg) |
| 豚肝臓(レバー) |
50 |
6.5 |
| アサリ(水煮) |
10 |
3.8 |
| かつお |
80 |
1.5 |
| 牛ヒレ肉 |
80 |
2.0 |
| 卵 |
60 |
1.1 |
※豚のお肉やレバーなどの内臓は生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べましょう。
| 非ヘム鉄(おもに野菜などに含まれる鉄) |
| 食品名 |
1食分あたり重量(g) |
鉄含有量(mg) |
| がんもどき |
80 |
2.9 |
| 納豆 |
50 |
1.7 |
| ほうれん草 |
50 |
1.0 |
| プルーン |
100 |
1.0 |
| おから |
30 |
0.4 |
(文部科学省「日本食品標準成分表」をもとに作成)
4-1.ヘム鉄・非ヘム鉄について
食品中に含まれる鉄は、タンパク質と結合した状態のヘム鉄と、タンパク質に結合していない無機鉄の非ヘム鉄に分けられます。ヘム鉄は肉や魚などの動物性食品に含まれていることが多く、非ヘム鉄は野菜や穀類に含まれていることがほとんどです。
体への吸収率は、ヘム鉄が15~20%、非ヘム鉄が2~5%とヘム鉄のほうが高いとされています。鉄分を効率よく補給するためには、吸収率の高いヘム鉄を豊富に含む食品を積極的に摂取するようにしましょう。
5.鉄を摂取する際のポイントと注意点
 非ヘム鉄は、ヘム鉄よりも低い吸収率ではありますが、動物性タンパク質やビタミンCと一緒に摂取することで体内への吸収率が上昇するといわれています。動物性タンパク質は肉類や魚類などに含まれ、ビタミンCは果物類や野菜類に多く含まれているので、これらの食材と鉄分の多い食材を使用した料理を選んで食べてみるようにしましょう。
非ヘム鉄は、ヘム鉄よりも低い吸収率ではありますが、動物性タンパク質やビタミンCと一緒に摂取することで体内への吸収率が上昇するといわれています。動物性タンパク質は肉類や魚類などに含まれ、ビタミンCは果物類や野菜類に多く含まれているので、これらの食材と鉄分の多い食材を使用した料理を選んで食べてみるようにしましょう。
また、鉄の吸収を阻害する成分のタンニンやシュウ酸などには注意が必要です。タンニンは、コーヒーや緑茶、紅茶などに多く含まれ、シュウ酸はほうれん草などに多く含まれています。
せっかく鉄分を多く含む食品を食べても、吸収が阻害されてしまっては何の意味もありません。食事の内容にも注意するようにしましょう。
非ヘム鉄は、ヘム鉄よりも低い吸収率ではありますが、動物性タンパク質やビタミンCと一緒に摂取することで体内への吸収率が上昇するといわれています。動物性タンパク質は肉類や魚類などに含まれ、ビタミンCは果物類や野菜類に多く含まれているので、これらの食材と鉄分の多い食材を使用した料理を選んで食べてみるようにしましょう。
また、鉄の吸収を阻害する成分のタンニンやシュウ酸などには注意が必要です。タンニンは、コーヒーや緑茶、紅茶などに多く含まれ、シュウ酸はほうれん草などに多く含まれています。
せっかく鉄分を多く含む食品を食べても、吸収が阻害されてしまっては何の意味もありません。食事の内容にも注意するようにしましょう。
5-1.鉄過剰症に注意が必要
鉄分が不足しないよう、食事に気を付けることは大切です。食事での補給が難しい場合には、サプリメントでの摂取も選択肢となるでしょう。しかし、サプリメントで鉄を摂取する場合には、鉄過剰症に注意が必要です。
鉄過剰症は、通常の食事ではあまり心配する必要はありませんが、サプリメントを使用する際は体調の変化に気を付け、体調に変化が現れたときは、医療機関を受診するようにしましょう。
ヘム鉄を多く含む食品で鉄不足を解消!
鉄は、赤血球などの材料として、体内で重要な役割を持つミネラルの一種です。鉄が不足すると、赤血球中のヘモグロビンや筋肉中のミオグロビンが不足します。ヘモグロビンが不足すると全身へ酸素がうまく運べなくなるため、さまざまな体調不良を引き起こす可能性があります。また、筋肉中のミオグロビンが不足することもあるので注意が必要です。
鉄は、ヘム鉄と非ヘム鉄に分けられ、ヘム鉄のほうが非ヘム鉄よりも吸収率が高くなっています。効率良く鉄を摂取するために、ヘム鉄を多く含んでいる動物性食品を積極的に摂取したり、鉄の吸収率を高めるビタミンCと一緒に摂取したりするようにしましょう。
鉄をサプリメントで摂取する場合は、鉄過剰症に気を付ける必要があります。鉄を過剰に摂取すると臓器に鉄が沈着し、肝臓や心臓に重大な問題を発生させる可能性があるため、体調に異変を感じた場合には医療機関を受診するようにしましょう。
監修者情報
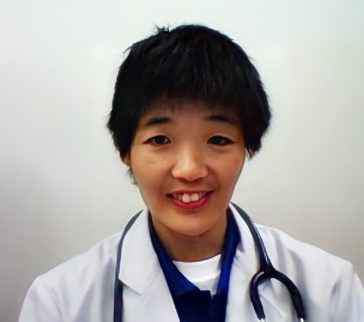
氏名:豊田早苗(とよだ・さなえ)
とよだクリニック院長。鳥取大学医学部卒。精神科・心療内科・内科・神経内科(認知症、物忘れ)の診療を担当している。総合診療医学会、認知症予防学会、精神医学会などに所属。現在は医師業務の傍ら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


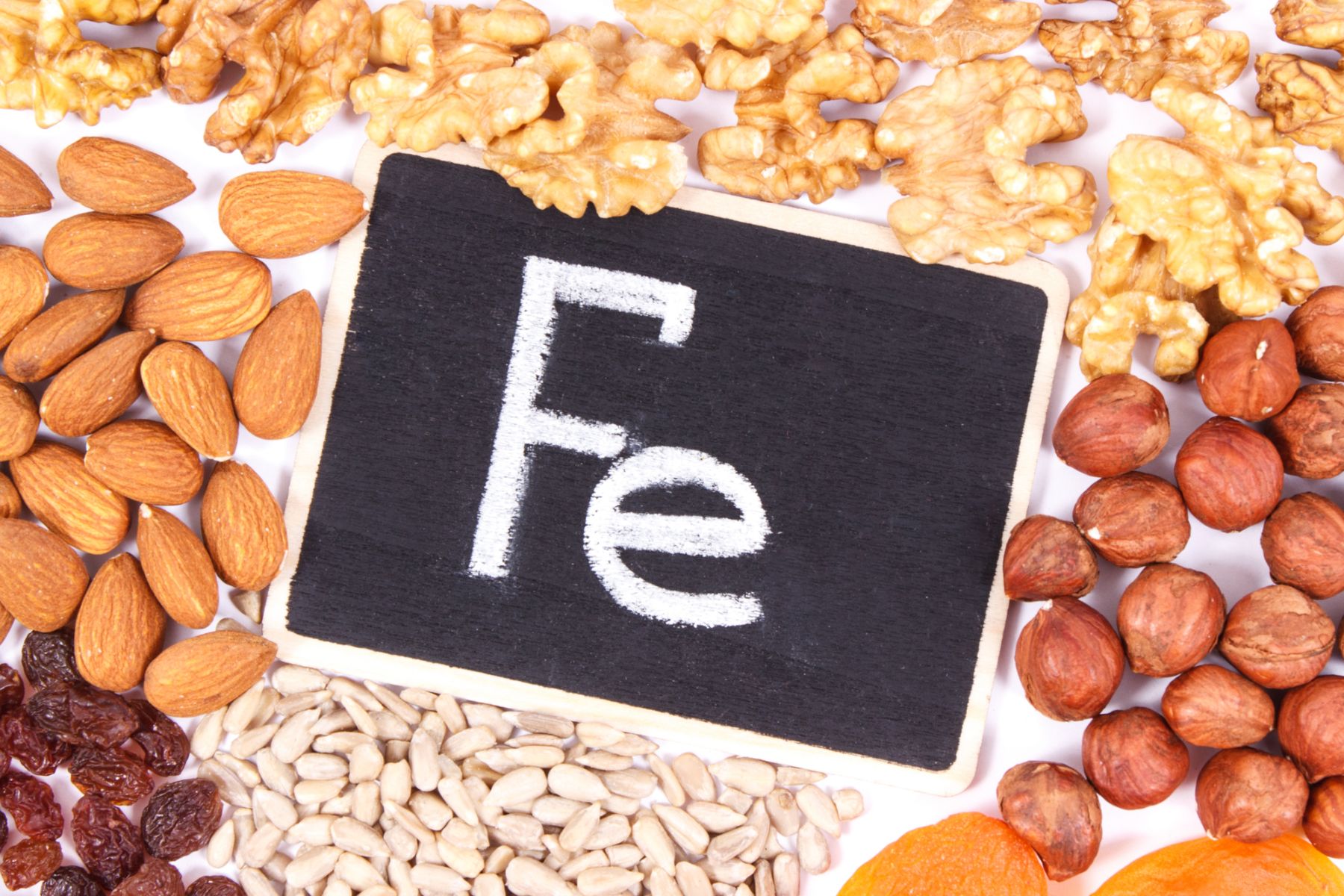 鉄は、健康を維持するうえで重要なミネラルです。鉄が不足すると、健康面にさまざまな悪影響がおよぶ可能性があるため、不足しないように注意しなければなりません。
鉄は、健康を維持するうえで重要なミネラルです。鉄が不足すると、健康面にさまざまな悪影響がおよぶ可能性があるため、不足しないように注意しなければなりません。 鉄の必要な摂取量は男女で大きく異なり、月経の有無や妊娠、授乳などが影響します。
鉄の必要な摂取量は男女で大きく異なり、月経の有無や妊娠、授乳などが影響します。
 非ヘム鉄は、ヘム鉄よりも低い吸収率ではありますが、動物性タンパク質やビタミンCと一緒に摂取することで体内への吸収率が上昇するといわれています。動物性タンパク質は肉類や魚類などに含まれ、ビタミンCは果物類や野菜類に多く含まれているので、これらの食材と鉄分の多い食材を使用した料理を選んで食べてみるようにしましょう。
非ヘム鉄は、ヘム鉄よりも低い吸収率ではありますが、動物性タンパク質やビタミンCと一緒に摂取することで体内への吸収率が上昇するといわれています。動物性タンパク質は肉類や魚類などに含まれ、ビタミンCは果物類や野菜類に多く含まれているので、これらの食材と鉄分の多い食材を使用した料理を選んで食べてみるようにしましょう。