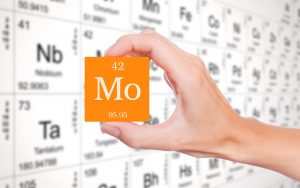1.プリン体とは?
プリン体とは、食べ物に含まれている、おもに「うまみ」の素になる成分です。あらゆる生物の細胞内にある核酸の主成分(アデニン・グアニンなど)として存在しています。そのため、さまざまな食品(肉・魚・穀物・野菜など)に含まれているのです。
私たちの体内に存在するプリン体は、以下の3つのパターンにより増加します。
体内に存在する割合としては、食品由来のプリン体が2割、体内でエネルギーの燃えカスや細胞の老廃物として作られるプリン体が8割を占めています。
2.プリン体を多く含む食品
 プリン体はうまみ成分の一つのため、うまみの強い食品は含有量が多い傾向があります。また、食品の重さに対して細胞の数が多いものほどプリン体の含有量が多いのです。
プリン体はうまみ成分の一つのため、うまみの強い食品は含有量が多い傾向があります。また、食品の重さに対して細胞の数が多いものほどプリン体の含有量が多いのです。
卵を例に挙げると、卵の粒が小さいタラコ100g中には、プリン体がおよそ120㎎含まれているのに対して、鶏卵100g(およそ2個)中にはプリン体がほとんど含まれていません。このように、食品の細胞数に着目してみると、プリン体の多い食品を見分けることができます。
ここでは、魚介類と肉類のプリン体の含有量を紹介します。
2-1.魚介類
プリン体が多く含まれているおもな魚介類は以下のとおりです。
| 食品名 |
食品100g中に含まれるプリン体含有量(㎎) |
| 煮干し |
746.1 |
| カツオ節 |
493.3 |
| 真イワシ |
305.7 |
| 大正エビ |
273.2 |
| 真アジ |
245.8 |
| サンマ |
208.8 |
| カツオ |
211.4 |
参照:帝京大学薬学部物理化学講座「薬品分析学教室」
2-2.肉類
続いて、プリン体が多く含まれているおもな肉類は以下のとおりです。
| 食品名 |
食品100g中に含まれるプリン体含有量(㎎) |
| 鶏肉(ササミ) |
153.9 |
| 鶏肉(手羽) |
137.5 |
| 豚ヒレ肉 |
119.7 |
| 牛モモ肉 |
110.8 |
| 牛スネ肉 |
106.4 |
| 豚タン |
104.0 |
参照:帝京大学薬学部物理化学講座「薬品分析学教室」
ご覧のとおり、うまみが強くおいしい食品には、プリン体が凝縮されています。
3.プリン体と痛風の関係性について
 世間では、「ごちそうを食べ過ぎると痛風になる」といわれますが、プリン体と痛風にはどのような関係があるのでしょうか。
世間では、「ごちそうを食べ過ぎると痛風になる」といわれますが、プリン体と痛風にはどのような関係があるのでしょうか。
通常であれば、プリン体は肝臓で分解されて尿酸に変化し、体外に排出されます。しかし、尿酸量が多くなり過ぎて排出能力を超えると、「痛風」の原因になるのです。
血液中の尿酸が飽和状態になると尿酸が結晶化し、関節に沈着してしまいます。これにより、関節炎を引き起こした状態が「痛風」です。
また、この結晶化した尿酸が腎臓に沈着すると腎臓障害に、尿の通り道に沈着すると尿路結石という病気を引き起こします。
痛風に注意が必要な人は、一日あたりのプリン体の摂取量を400㎎以内に収めましょう。プリン体を減らすには食べる量を控えることも大切ですが、調理法によっても減らすことができます。
プリン体は水に溶ける性質があるため、ゆでる・煮るなどの調理方法がよいでしょう。ただし、ゆで汁・煮汁にはプリン体が溶け込んでいるため、飲まないように注意が必要です。
プリン体を多く含む食品に気を付けて痛風を予防しましょう
プリン体は、うまみ成分の一種です。あらゆる生物の細胞内に存在するため、さまざまな食品に含まれています。特に、煮干しやエビなどうまみの強い食品や、細胞数の多い魚卵などに多い傾向にあります。
また、プリン体は体内で尿酸に変化します。血液のなかに尿酸が増え過ぎると、結晶化して痛風の原因になるのです。
痛風になると、ある日突然、激痛に襲われます。痛風というと、かつては、宴会の席でごちそうを食べる機会が多い中年男性が発症する病気とされていましたが、食生活が豊かになった現在は誰でも発症する可能性があります。
日頃からプリン体の摂り過ぎに気を付けて、痛風を予防しましょう。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。


 かつては中年男性に多かった「痛風」ですが、最近は20~30代といった世代でも目立つようになってきています。
かつては中年男性に多かった「痛風」ですが、最近は20~30代といった世代でも目立つようになってきています。 プリン体はうまみ成分の一つのため、うまみの強い食品は含有量が多い傾向があります。また、食品の重さに対して細胞の数が多いものほどプリン体の含有量が多いのです。
プリン体はうまみ成分の一つのため、うまみの強い食品は含有量が多い傾向があります。また、食品の重さに対して細胞の数が多いものほどプリン体の含有量が多いのです。 世間では、「ごちそうを食べ過ぎると痛風になる」といわれますが、プリン体と痛風にはどのような関係があるのでしょうか。
世間では、「ごちそうを食べ過ぎると痛風になる」といわれますが、プリン体と痛風にはどのような関係があるのでしょうか。