目次
1.ビタミンB12とは
ビタミンB12は、水溶性ビタミンに分類され、コバルトを含んでいるビタミンの総称です。ビタミンB12には、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミン、ヒドロキソコバラミン、シアノコバラミンが存在し、このうちメチルコバラミンとアデノシルコバラミンが、アミノ酸や脂質といった代謝の補酵素として利用されています。
ビタミンB12は、微生物のみが合成でき、植物性食品にはほとんど含まれていません。貝類や魚類、肉類などの動物性食品に含まれています。
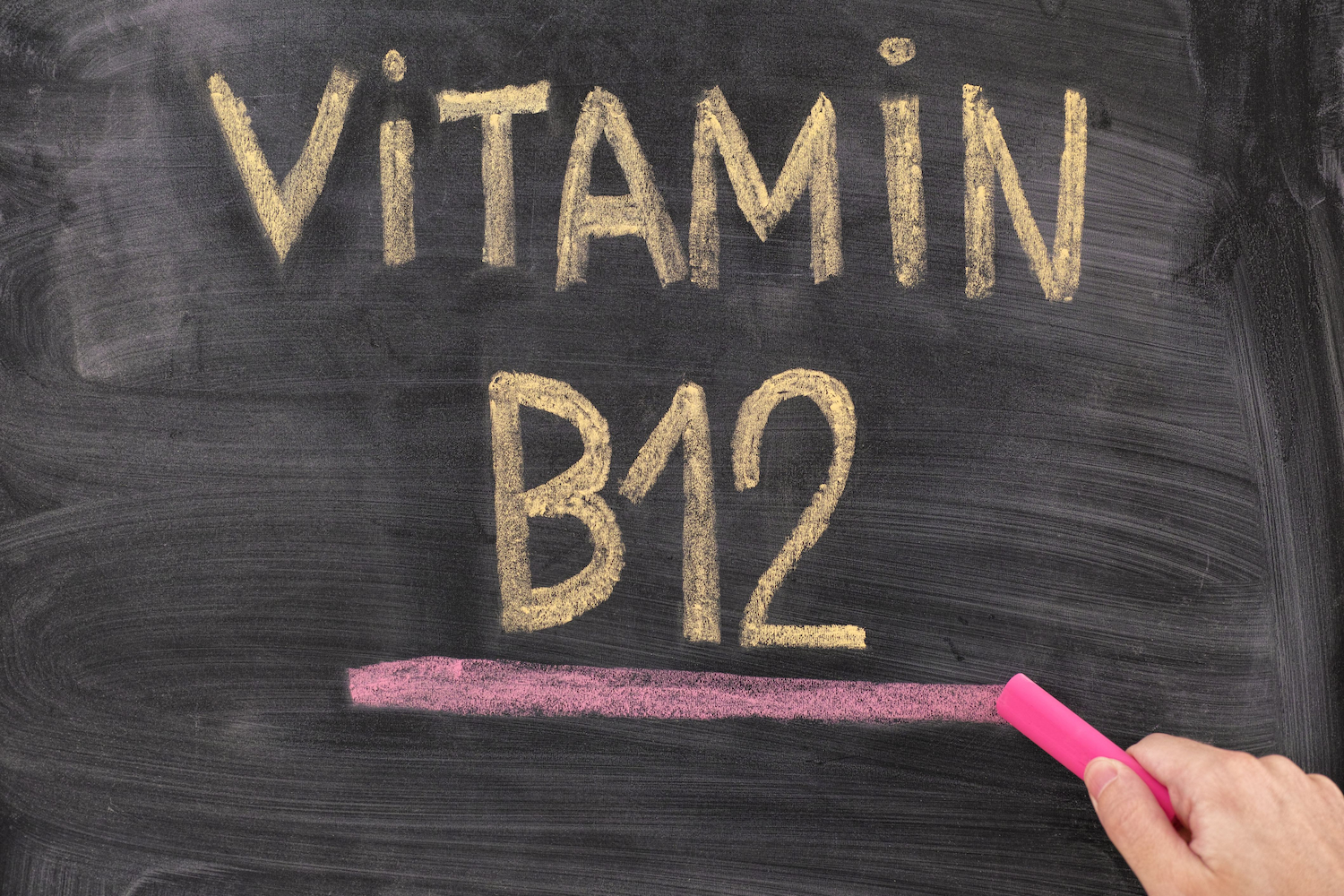 ビタミンB12は人間の体の健康を維持するために重要な栄養素です。ビタミンB12が不足すると、慢性疲労などさまざまな問題の引き金になることもあるので、不足しないように注意しましょう。
ビタミンB12は人間の体の健康を維持するために重要な栄養素です。ビタミンB12が不足すると、慢性疲労などさまざまな問題の引き金になることもあるので、不足しないように注意しましょう。
今回は、ビタミンB12のおもな働きと役割、摂取量の目安について解説します。
目次
ビタミンB12は、水溶性ビタミンに分類され、コバルトを含んでいるビタミンの総称です。ビタミンB12には、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミン、ヒドロキソコバラミン、シアノコバラミンが存在し、このうちメチルコバラミンとアデノシルコバラミンが、アミノ酸や脂質といった代謝の補酵素として利用されています。
ビタミンB12は、微生物のみが合成でき、植物性食品にはほとんど含まれていません。貝類や魚類、肉類などの動物性食品に含まれています。
体内で吸収されたビタミンB12は、メチオニン合成酵素の補酵素として働くほか、奇数鎖脂肪酸の合成の補酵素としても働きます。
メチオニンは、必須アミノ酸の一つで、ホモシステインに変換されます。そのために必要な補酵素が、ビタミンB12の一つであるメチルコバラミンです。
また、奇数鎖脂肪酸や分岐鎖アミノ酸の代謝に関与しているメチルマロニルCoAムターゼの補酵素として、ビタミンB12の一つであるアデノシルコバラミンが利用されています。そのため、ビタミンB12が欠乏するとアミノ酸や脂質の代謝がうまくできなくなる可能性があります。
 ここでは、ビタミンB12が不足することによる影響と不足しやすい人を紹介します。
ここでは、ビタミンB12が不足することによる影響と不足しやすい人を紹介します。
ビタミンB12は血液中に存在する赤血球の細胞骨格を維持するために必要な栄養素であるため、不足すると赤血球を新しく生成できません。赤血球は、酸素を全身に運ぶ役割を持ちます。
赤血球が不足すると体内で十分に酸素を運搬できなくなり、頭痛や息切れ、疲労感などの症状があらわれます。貧血によって運動機能の低下などにもつながるため注意が必要です。
ビタミンB12は動物性食品に多く含まれているため、野菜中心の食品のみを摂取する方は欠乏しやすくなります。また、ビタミンB12は食品中では、タンパク質と結合している状態となっており、胃から分泌される胃酸やペプシンによって分離されます。そのため、胃を切除した方や高齢者などの胃酸分泌能力が低下している方はビタミンB12がうまく分離できず、欠乏する可能性があります。
また、小腸における吸収不全がある場合にもビタミンB12欠乏が生じることがあります。
ビタミンB12は、過剰に摂取しても体内で吸収されずに排泄されます。そのため、ビタミンB12を過剰摂取することによる障害は基本的にありません。サプリメントで補充する場合でも過剰症の心配はありませんが、ビタミンB12の過剰摂取によって体調変化があれば医療機関へ受診してください。
ビタミンB12の1日あたりの食事摂取基準は以下のとおりです。
| 性別 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 年齢 | 推奨量(単位μg/日) | 推奨量(単位μg/日) |
| 0〜5ヵ月※ | 0.4 | 0.4 |
| 6〜11ヵ月※ | 0.5 | 0.5 |
| 1〜2歳 | 0.9 | 0.9 |
| 3〜5歳 | 1.1 | 1.1 |
| 6〜7歳 | 1.3 | 1.3 |
| 8〜9歳 | 1.6 | 1.6 |
| 10〜11歳 | 1.9 | 1.9 |
| 12〜14歳 | 2.4 | 2.4 |
| 15〜17歳 | 2.4 | 2.4 |
| 18〜29歳 | 2.4 | 2.4 |
| 30〜49歳 | 2.4 | 2.4 |
| 50〜64歳 | 2.4 | 2.4 |
| 65〜74歳 | 2.4 | 2.4 |
| 75歳以上 | 2.4 | 2.4 |
| 妊婦(付加量) | ─ | +0.4 |
| 授乳婦(付加量) | ─ | +0.8 |
※1歳未満は目安量
※推奨量:ある性・年齢階級に属する人々のほとんど(97~98%)が1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取量
※目安量:推定平均必要量・推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、ある性・年齢階級に属する人々が、良好な栄養状態を維持するのに十分な量
※上限量:ある性・年齢階級に属するほとんどすべての人々が、過剰摂取による健康障害を起こすことのない栄養素摂取量の最大限の量
引用:厚生労働省「日本人の食事摂取基準」策定検討会「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
なお、2019年の国民健康・栄養調査によると、ビタミンB12の摂取量は、男性が平均6.9μg/日、女性が平均5.7μg/日でした。上表の通り、男性・女性とも推奨量は最大でも2.4μg/日であるため、男女とも大きく推奨量を充たしている人が多いといえます。
 ビタミンB12は、主に動物性食品に多く含まれていますが、焼きのりなど一部の植物性食品にもビタミンB12が含まれています。下表では、ビタミンB12を含む食品と1食あたりに含まれる量をまとめています。
ビタミンB12は、主に動物性食品に多く含まれていますが、焼きのりなど一部の植物性食品にもビタミンB12が含まれています。下表では、ビタミンB12を含む食品と1食あたりに含まれる量をまとめています。
| 食品名 | 1食あたりの重量(g) | 1食あたりのビタミンB12量(μg) |
|---|---|---|
| しじみ(生) | 50 | 34.0 |
| アサリ缶詰(水煮) | 40 | 25.6 |
| さんま(焼き) | 100 | 16.0 |
| サバ缶詰(水煮) | 90 | 10.8 |
| 生牡蠣 | 60 | 13.8 |
| 紅鮭(焼き) | 80 | 3.0 |
| 焼き海苔 | 3 | 1.7 |
| 味付けのり | 3 | 1.7 |
(文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より引用)
ビタミンB12は、コバルトを含む水溶性ビタミンの総称です。ビタミンB12は、アミノ酸や脂質の代謝に重要な働きをしているため、欠乏すると問題が生じることがあります。
ビタミンB12の欠乏症としては、悪性貧血や神経障害などがあり、貧血になると頭痛や息切れ、疲労感などが起こる可能性があるので注意が必要です。
ビタミンB12は、植物性食品にほとんど含まれていません。よって、野菜中心の食品のみを摂取する方は欠乏しやすくなります。また、胃酸の分泌能力が低下している高齢者の方なども欠乏しやすい傾向があります。ビタミンB12が不足しないようにするためにも、栄養バランスの良い食事を摂るように心がけましょう。

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。
成分

脂肪酸は、人体の細胞を作るうえで必要な成分です。
成分

私たちの体の細胞は、増殖と分化を繰り返すことで健康な状態を維持しています。
成分

ビタミンB群の一種である葉酸は、体内のさまざまな反応に関わる必要不可欠な栄養素です。
成分

たんぱく質・糖質・脂質・ビタミン・ミネラルはヒトの体に欠かせない成分であり、5大栄養素と呼ばれます。
成分

脂肪の燃焼を促すことでダイエットに良いといわれているカプサイシン。