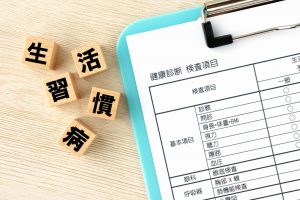1.レム睡眠とノンレム睡眠の違いについて
 睡眠段階には、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」があります。ここでは、両者の特徴や違いを見てみましょう。
睡眠段階には、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」があります。ここでは、両者の特徴や違いを見てみましょう。
1-1.レム睡眠
レム睡眠は、脳は活動している一方で体は休んでいるという、覚醒とノンレム睡眠の中間の睡眠段階です。レム睡眠中は夢を見やすいことも広く知られています。
レム睡眠の特徴として、急速眼球運動の発生と骨格筋活動の低下が起こります。そして、この急速眼球運動(Rapid Eye Movements)の頭文字を取って「レム(REM)」睡眠と呼ばれます。
なお、レム睡眠の割合が少なくなると、脳の機能低下や老化が進むと考えられています。
1-2.ノンレム睡眠
ノンレム睡眠は、脳を休める睡眠段階です。睡眠の深さによって4段階に分けられ、ステージ3とステージ4は「徐波睡眠」と呼ばれます。
一般的に、睡眠は徐波睡眠から始まり、睡眠時間が経過するにつれステージ1・ステージ2の浅いノンレム睡眠が増えていきます。入眠直後の徐波睡眠では、成長ホルモンの分泌が特に多くなるのが特徴です。
1-3.レム睡眠とノンレム睡眠の関係性
ノンレム睡眠とレム睡眠は、90~120分程度ごとに繰り返し出現しますが、このサイクルが進むとノンレム睡眠の持続時間は短くなります。
ただし、ノンレム睡眠とレム睡眠のサイクルがどのように作られるかについては、まだ不明な点が残っています。
2.睡眠のメカニズム
睡眠のメカニズムには、疲労による「睡眠欲求」と、体内時計から発信される「覚醒力」が関係しています。覚醒時間が長くなるほど睡眠欲求が強くなりますが、睡眠欲求に打ち勝つ覚醒力の働きにより、昼過ぎ以降も起きて活動を続けられます。
しかし、夜になると急速に覚醒力が低下するとともに、睡眠の促進作用があるホルモンの「メラトニン」が分泌されることで、眠気を感じ始めるようになります。
また、脳の温度は活動している日中に高くなり、夜になると放熱されて低くなります。寝る前の時間帯に脳が急速に冷やされるのも、入眠が促される理由の一つです。
3.レム睡眠とノンレム睡眠はどちらが起きやすい?
 レム睡眠とノンレム睡眠で目覚めやすいのは、レム睡眠です。
レム睡眠とノンレム睡眠で目覚めやすいのは、レム睡眠です。
レム睡眠は、脳波活動が比較的活発になり、血圧や脈拍も変動するため、覚醒への準備状態といえます。そのため、レム睡眠の割合が多くなると、夜中に目覚めたり、睡眠時間を確保しても寝た気がしなかったりすることがあるのです。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、本来は、夜にかけて徐々に副交感神経が優位になります。しかし、ストレスなどが原因で交感神経が優位の状態が続くと、夜になっても脳が興奮状態となり、レム睡眠の割合が増えます。
また、高齢者が睡眠から目覚めやすくなるのは、深いノンレム睡眠が減り浅いレム睡眠が増えるためです。
睡眠への理解を深め質の良い睡眠を目指しましょう
レム睡眠は、体を休めたり、覚醒の準備をしたりする睡眠段階です。一方のノンレム睡眠は、脳を休めたり、成長ホルモンを分泌したりする睡眠段階を指します。
目覚めやすいのはレム睡眠ですが、単にレム睡眠の割合が多くなると、「夜中に起きてしまう」「しっかり寝ているはずなのに寝た気がしない」といったことが起こるようになります。
大切なのは、レム睡眠とノンレム睡眠の適切なサイクルを維持できるよう、過度なストレスをためずに生活リズムを整えることです。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。
 睡眠段階には、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」があります。ここでは、両者の特徴や違いを見てみましょう。
睡眠段階には、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」があります。ここでは、両者の特徴や違いを見てみましょう。

 私たちの健康には、食事や運動だけでなく「睡眠」も欠かせません。
私たちの健康には、食事や運動だけでなく「睡眠」も欠かせません。 レム睡眠とノンレム睡眠で目覚めやすいのは、レム睡眠です。
レム睡眠とノンレム睡眠で目覚めやすいのは、レム睡眠です。