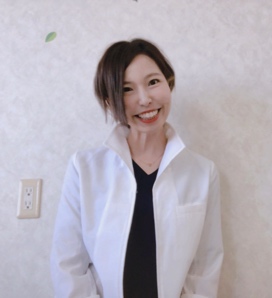1.歯周病とはなにか?
 歯周病は歯周疾患とも呼ばれ、歯を支える歯ぐきや周囲の骨などが歯周病菌によって破壊される疾患のことです。悪化すると歯が抜けてしまうため、むし歯と並んで歯を失う2大原因に数えられています。
歯周病は歯周疾患とも呼ばれ、歯を支える歯ぐきや周囲の骨などが歯周病菌によって破壊される疾患のことです。悪化すると歯が抜けてしまうため、むし歯と並んで歯を失う2大原因に数えられています。
日本人で歯周病にかかっているのは、40歳以上のおよそ8割といわれ、生活習慣病の一つとされています。
歯周病の原因とされているのは、次の3つです。
喫煙やストレス、不規則な生活といった生活習慣が要因となることを環境因子と呼びます。そして細菌要因とは、歯周病菌が潜んでいる歯垢が原因の場合です。
老化や遺伝子的要因では、老化や遺伝のほか、糖尿病や肥満などが歯周病の要因になります。
これらのことから、歯周病を予防するためには、口内環境の改善や規則正しい生活が大切だといえるでしょう。
口内環境の改善において特に重要なのは、歯周病菌が増殖するもとになる歯垢を、ブラッシングでしっかり除去することです。歯と歯ぐきの間や奥歯の溝、歯と歯の間などは、歯垢が溜まりやすい部分であるため、入念に磨きましょう。
歯周病予防のために生活習慣を改善するには、まず喫煙習慣の見直しが大切です。喫煙者の場合、歯に付着したタールが歯周病の原因となるプラークを吸着してしまいます。また、タバコに含まれているニコチンや一酸化炭素は免疫機能を低下させる働きがあり、歯ぐきの炎症が治りにくくなるため、禁煙することをおすすめします。
その他に、食事の栄養バランスを整えることや、ストレスを適度に発散させることなども大切です。
2.歯周病の種類
歯周病と一口にいっても、実は歯肉炎と歯周炎の2種類があります。それぞれ特徴が異なるため、どういった違いがあるのかをここで押さえておきましょう。
2-1.歯肉炎
歯肉炎とは、歯ぐきだけに炎症が起こっている状態で、歯周病の初期段階です。おもな症状は、歯と歯ぐきの境界線の部分が赤くなって腫れたり、歯磨きの際に出血したりします。
歯ぐきが腫れるため、健康な歯よりも歯と歯ぐきの間の隙間が深くなるのが特徴です。この溝は歯肉ポケットと呼ばれます。
この段階であれば、歯と歯ぐきに付着しているプラークをしっかり取ることで、健康な歯ぐきに戻るでしょう。
2-2.歯周炎
歯周炎は、歯肉炎が重症化した状態のことです。歯ぐきの炎症がひどくなり、歯と歯ぐきの境界線がどんどん破壊されます。その結果、歯肉ポケットがさらに深くなります。
歯周ポケットにプラークが入り込むと、歯の根元へとどんどん進み、組織を破壊していきます。歯根膜線維や歯槽骨が壊されると歯を支えるものがなくなるため、歯がぐらつくようになるでしょう。
さらに、次のような症状も併発します。
-
・歯ぐきの腫れ
-
・歯ぐきからの出血
-
・歯周ポケットの化膿
-
・口臭
これらの症状が見られる状態は慢性歯周炎と呼ばれ、症状の重さによって軽度・中等度・重度の3段階に区別されます。歯ぐきが急に炎症を起こした場合は、腫れや痛みがより強く出るケースもあるでしょう。
3.歯周病が疑われる症状
 ここからは、歯周病になった際に現れる症状について解説します。おもな症状は次のとおりです。
ここからは、歯周病になった際に現れる症状について解説します。おもな症状は次のとおりです。
このような症状が3つ以上当てはまった方は、歯周病の疑いがあります。気になる方は、早めに歯科を受診しましょう。
歯周病を早期発見するためには、歯ぐきを日常からしっかり観察することが大切です。例えば、毎日歯磨きをする際に、歯ぐきの腫れや出血がないか確認してみてください。
歯周病は早めに治療しよう
歯周病は、症状の進行度によって歯肉炎と歯周炎の2種類に分けられます。歯周病の初期段階である歯肉炎は、歯と歯ぐき周辺の歯垢をブラッシングで除去すれば、また正常な状態に戻ります。
しかし、歯肉炎が悪化して歯周炎になると、歯の根元の深い部分まで炎症が進み、周辺の組織が破壊されます。歯根膜線維や歯槽骨などの歯を支えている組織が壊されると、歯がぐらつくようにもなるでしょう。
このような状態にならないためにも、定期的に口内の健康をチェックしましょう。
監修者情報
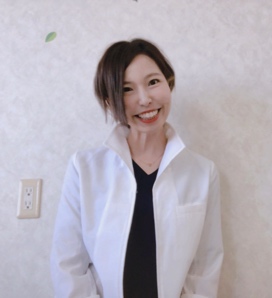
氏名:福田尚美(ふくだ・なおみ)
歯科医師臨床研修終了後、審美歯科・ホワイトニング専門医院に勤務。現在は一般歯科・小児歯科非常勤勤務のかたわら歯科医師としての知識と経験を生かし、歯科医師webライター、歯科企業やオンラインセミナーのサポートなども行なっている。
 歯周病は歯周疾患とも呼ばれ、歯を支える歯ぐきや周囲の骨などが歯周病菌によって破壊される疾患のことです。悪化すると歯が抜けてしまうため、むし歯と並んで歯を失う2大原因に数えられています。
歯周病は歯周疾患とも呼ばれ、歯を支える歯ぐきや周囲の骨などが歯周病菌によって破壊される疾患のことです。悪化すると歯が抜けてしまうため、むし歯と並んで歯を失う2大原因に数えられています。

 歯周病という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。
歯周病という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。 ここからは、歯周病になった際に現れる症状について解説します。おもな症状は次のとおりです。
ここからは、歯周病になった際に現れる症状について解説します。おもな症状は次のとおりです。