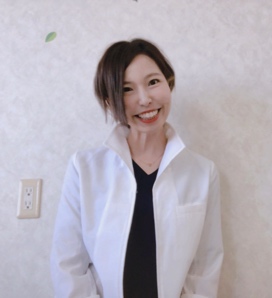1.唾液の働き・作用について
唾液は、ただ口をうるおすためだけに分泌されているものではありません。次のように、実はさまざまな働きをしています。
-
・咀嚼をスムーズにする
-
・発音しやすくする
-
・食べ物を飲み込みやすくする
-
・食べ物を消化する
-
・ばい菌から体を守る
-
・食べ物の味を感じやすくする
-
・虫歯を予防する
唾液は口の中で潤滑油のような働きをしているため、咀嚼や発音をスムーズにする効果があります。口の中がパサつくと喋りづらくなるのは、潤滑油が少なくなるためです。
また、唾液にはアミラーゼという消化酵素が含まれており、食べ物を消化するのにも唾液が必要になります。
このほか、リゾチームなどの抗菌物質も含まれていることから、ばい菌から体を守る働きもあります。虫歯菌が作り出した酸を中性に近づけたり歯の再石灰化を促したりすることから、虫歯の予防にも効果的です。
2.唾液の分泌量低下によるドライマウス(口腔乾燥)について
 唾液は、耳下腺や顎下腺などから分泌されています。分泌量は個人差がありますが、疾病が原因で分泌量が減ることもあるので注意が必要です。
唾液は、耳下腺や顎下腺などから分泌されています。分泌量は個人差がありますが、疾病が原因で分泌量が減ることもあるので注意が必要です。
唾液の分泌量が減少した状態をドライマウスといい、口が渇くだけでなくさまざまな影響をもたらします。
2-1.ドライマウス(口腔乾燥)とは
ドライマウスとは、唾液の分泌量が減って口の中が乾燥している状態です。薬の副作用やストレス、筋力の低下などで起こることがあります。高血糖の状態などほかの病気が原因となることもあるため、ドライマウスが気になる場合は検査を受けたほうが良いケースもあるでしょう。
ドライマウスは特別なものと思われる方もいるかもしれませんが、今や現代病です。原因としては、やわらかい食べ物を好み咀嚼時間が短くなり、唾液を分泌する筋肉が衰えてしまうためです。ドライマウスの患者は増え続けており、虫歯や歯周病を予防するためにも早めに対処しましょう。
2-2.唾液量の減少による影響
唾液の量が減少することで、次のような影響が起こる可能性があります。
-
・虫歯や歯周病になりやすくなる
-
・食べ物が飲み込みづらくなる
-
・発音がしづらくなる
-
・味覚障害が起こる
-
・義歯が合わなくなる
-
・舌苔(ぜったい)が増加する
口腔内が乾燥すると食べかすが長時間とどまることになり、虫歯や歯周病になりやすくなります。舌苔の増加は口臭にもつながるので、注意しましょう。口臭の原因のほとんどは舌苔だといわれています。臭いが気になる方は、唾液が不足しているかもしれません。
3.唾液の分泌量を増やす方法
 唾液の量を増やすためには、次の方法が効果的です。
唾液の量を増やすためには、次の方法が効果的です。
-
・リラックスする時間を作る
-
・口呼吸ではなく鼻呼吸をする
-
・水分をこまめに摂る
-
・よく噛んで食べる
-
・禁煙する
-
・コーヒーや紅茶の飲み過ぎに注意する
薬の副作用で口が渇く場合は、副作用が出にくいものに変更してもらうのもよいでしょう。ストレスや生活習慣のほか、病気が原因で唾液が出づらくなっていることもあるため、気になる方は医療機関の受診も考えてみてください。
唾液が少ない方は対策を始めよう
唾液は口をうるおすだけでなく、咀嚼をスムーズにしたり虫歯を予防したりする働きがあります。食べ物を飲み込みやすくしたり消化したり、体をばい菌から守ったりする働きもあるため、唾液は健康を守るうえでとても大切なものです。
しかし、ストレスや筋力の低下、薬の副作用などが原因となり、唾液の分泌量が減少してしまうことがあります。唾液量の減少が気になる方は、リラックスする時間を作り、よく噛んで食べるようにしましょう。病気が原因のこともあるので、口の乾燥が気になる方は医療機関の受診も検討してみてください。
監修者情報
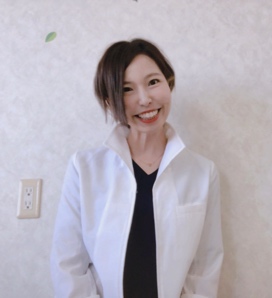
氏名:福田尚美(ふくだ・なおみ)
歯科医師臨床研修終了後、審美歯科・ホワイトニング専門医院に勤務。現在は一般歯科・小児歯科非常勤勤務のかたわら歯科医師としての知識と経験を生かし、歯科医師webライター、歯科企業やオンラインセミナーのサポートなども行なっている。


 普段あまり意識することはないかもしれませんが、成人は一日に1.0~1.5Lとかなりの量の唾液を分泌しています。
普段あまり意識することはないかもしれませんが、成人は一日に1.0~1.5Lとかなりの量の唾液を分泌しています。 唾液は、耳下腺や顎下腺などから分泌されています。分泌量は個人差がありますが、疾病が原因で分泌量が減ることもあるので注意が必要です。
唾液は、耳下腺や顎下腺などから分泌されています。分泌量は個人差がありますが、疾病が原因で分泌量が減ることもあるので注意が必要です。 唾液の量を増やすためには、次の方法が効果的です。
唾液の量を増やすためには、次の方法が効果的です。