1.肥満の判定基準とは?
肥満の判定基準には、BMI(Body Mass Index)の値が使われます。BMIとはボディ・マス指数と呼ばれるもので、体重と身長から肥満や低体重の判定をするために使用されます。BMIの計算式は次のとおりです。
<BMIの求め方>
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)の2乗
例えば、体重55kg、身長が160cm(1.6m)であれば、BMIは約21.5となります。
下表に日本肥満学会によるBMIの数値別の肥満判定を掲載したので見てみましょう。
| BMI |
判定 |
| <18.5 |
低体重 |
| 18.5≦BMI<25.0 |
普通体重 |
| 25.0≦BMI<30.0 |
肥満(1度) |
| 30.0≦BMI<35.0 |
肥満(2度) |
| 35.0≦BMI<40.0 |
肥満(3度) |
| 40.0≦BMI |
肥満(4度) |
上表のとおり、普通体重はBMIが18.5以上25.0未満、BMIが25.0以上になると肥満判定となります。
なお、男女ともBMIは22.0が標準です。BMIが標準であれば、高血圧、脂質異常症、糖尿病といった肥満による発症のリスクが上がる疾患に最もかかりにくいといわれています。
BMIを使用する際に注意したいのは、BMIだけで肥満とは断定できない点です。BMIは、肥満を判定する手段として有効ではあるものの、単純に体重と身長の数字を使って計算しています。そのため、脂肪が多いのか、筋肉が多いのかまでは判断できないのです。
例えば、BMIが普通体重の範囲内であったとしても、筋肉量が少なく脂肪が多い方はいわゆる“隠れ肥満”の可能性があります。
2.肥満とメタボリックシンドロームの違い
 肥満と併せてよく使われる言葉に「メタボリックシンドローム」があります。メタボリックシンドロームとは、腹腔内に内臓脂肪が過剰に蓄積し、その影響で高血圧や高血糖、脂質代謝異常などが組み合わさっている状態です。
肥満と併せてよく使われる言葉に「メタボリックシンドローム」があります。メタボリックシンドロームとは、腹腔内に内臓脂肪が過剰に蓄積し、その影響で高血圧や高血糖、脂質代謝異常などが組み合わさっている状態です。
メタボリックシンドロームは、高血圧や高血糖、脂質代謝異常などの代謝異常が合併した状態であり、ただ単に体重が重かったりお腹が出ていたりするからといってメタボリックシンドロームであるわけではありません。
メタボリックシンドロームの診断基準は国によってさまざまですが、日本では内臓脂肪がどれだけあるか、という判断基準を採用しています。ウエストの周囲径を計測することで診断されます。
日本の場合、おへその高さで計測したウエストの周囲径が男性で85cm以上、女性で90cm以上の人で、血圧や血糖値、脂質のうち2つ以上の値がメタボリックシンドロームの診断基準で定められた基準値を外れていると、メタボリックシンドロームです。
3.肥満はおもに2種類
肥満には、「皮下脂肪型肥満」と「内臓脂肪型肥満」の2種類があります。高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を発症しやすいのは、内臓脂肪型肥満のほうです。どちらも肥満であることに変わりはありませんが、肥満の種類によって疾患を抱えるリスクが異なります。
3-1.皮下脂肪型肥満
皮下脂肪型肥満とは、皮膚の最も内側にある組織である皮下組織に過剰な脂肪が蓄積している状態です。「洋ナシ型肥満」と呼ばれることもあり、お尻や太ももに脂肪が蓄積するタイプの肥満です。男性より女性に多く見られることが特徴です。
メタボリックシンドロームの診断基準は、男性の場合はウエストの周囲径85cm以上であるのに対し、女性は90cm以上と基準がゆるくなっています。これは、女性のほうが男性より皮下脂肪がつきやすいことに関係しています。
3-2.内臓脂肪型肥満
内臓脂肪型肥満とは、腸の周りに脂肪が過剰に蓄積している状態です。女性よりも男性で多く見られます。下半身ではなくお腹周りに脂肪が蓄積することから、「リンゴ型肥満」とも呼ばれます。
4.肥満のおもな原因
肥満の原因としては、おもに次のものが挙げられます。
-
・摂取エネルギーが過剰になっている
-
・間食や節度を超えた飲酒
-
・食事のリズムが不規則
-
・運動不足
間食は気分転換や食事で足りない栄養素を補う役割もはたしていますが、食べ過ぎには注意が必要です。一日に200kcalを目安に摂取するようにしましょう。
5.肥満が健康にもたらす悪影響
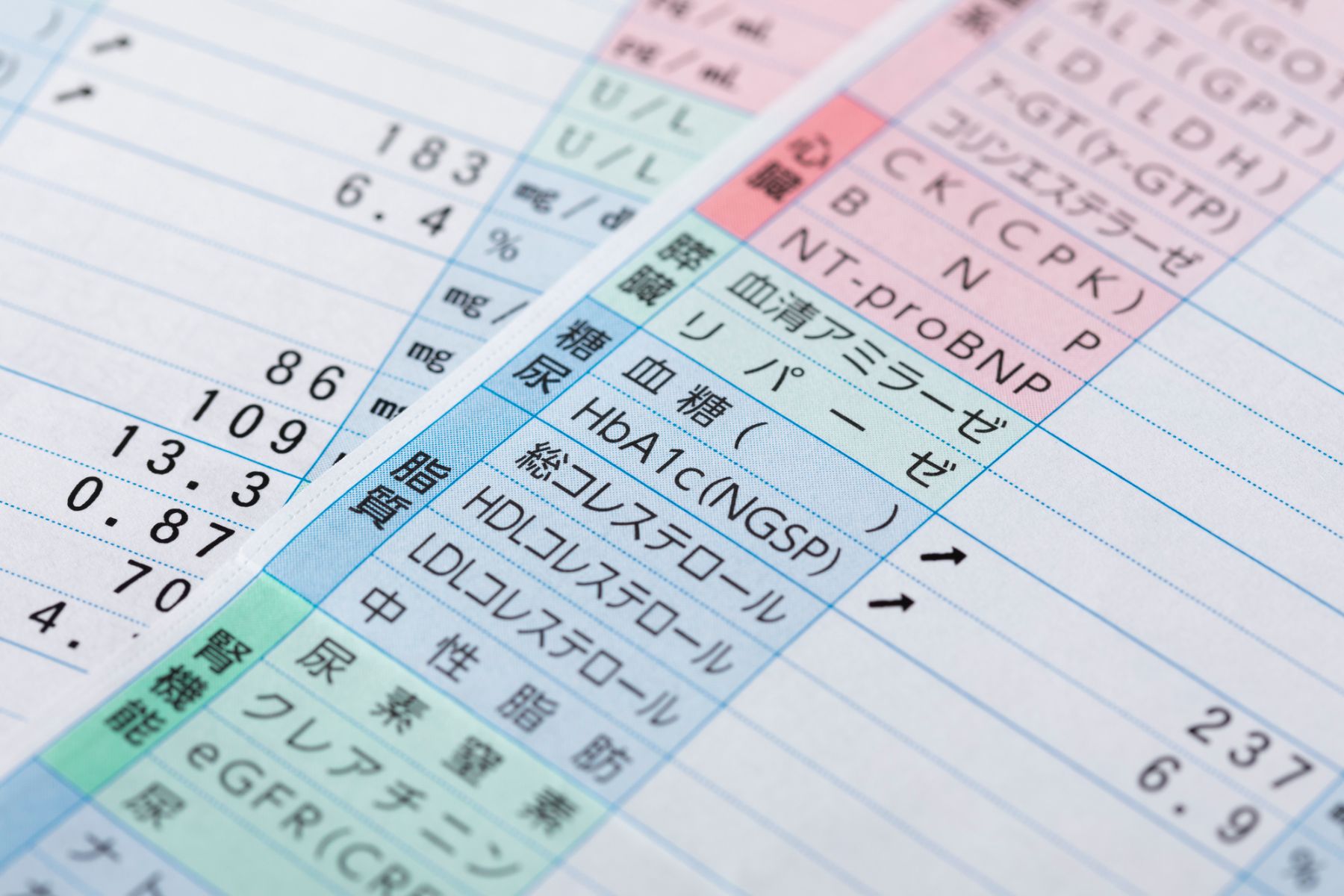 肥満による健康への影響は、皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満で異なります。皮下脂肪型肥満で問題になりやすいのは、睡眠時無呼吸症候群や関節痛、月経異常などです。血管の柔軟性を失うなどのリスクについてはあまり心配ないでしょう。
肥満による健康への影響は、皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満で異なります。皮下脂肪型肥満で問題になりやすいのは、睡眠時無呼吸症候群や関節痛、月経異常などです。血管の柔軟性を失うなどのリスクについてはあまり心配ないでしょう。
一方で内臓脂肪型肥満は、糖尿病や高血圧、脂質異常症などを引き起こしやすいことが知られています。
肥満を改善して生活習慣病を予防しよう
BMIは25.0以上になると肥満判定となります。ただし、BMIのみでは脂肪が多いのか筋肉が多いのかまでは判断できません。あくまで目安の一つとして考えておきましょう。
肥満の代表的な原因は、エネルギーの過剰摂取や運動不足です。特に内臓脂肪型肥満を放っておくと血管の柔軟性が失われるリスクを高めることにもつながるため、日頃から体重管理を心がけましょう。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


 肥満は万病の元といわれており、肥満を改善しないと健康にさまざまな害をもたらす可能性があります。
肥満は万病の元といわれており、肥満を改善しないと健康にさまざまな害をもたらす可能性があります。 肥満と併せてよく使われる言葉に「メタボリックシンドローム」があります。メタボリックシンドロームとは、腹腔内に内臓脂肪が過剰に蓄積し、その影響で高血圧や高血糖、脂質代謝異常などが組み合わさっている状態です。
肥満と併せてよく使われる言葉に「メタボリックシンドローム」があります。メタボリックシンドロームとは、腹腔内に内臓脂肪が過剰に蓄積し、その影響で高血圧や高血糖、脂質代謝異常などが組み合わさっている状態です。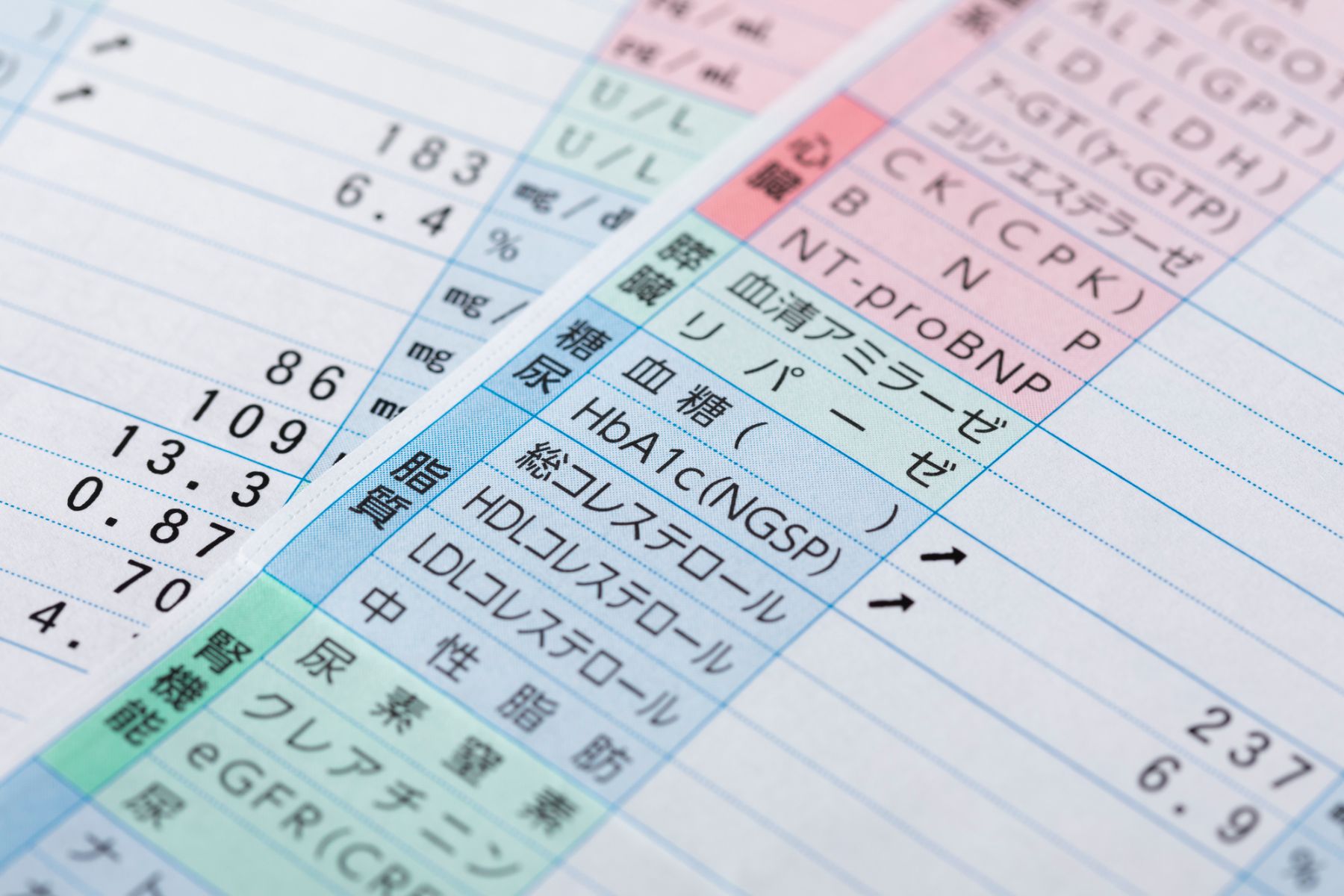 肥満による健康への影響は、皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満で異なります。皮下脂肪型肥満で問題になりやすいのは、睡眠時無呼吸症候群や関節痛、月経異常などです。血管の柔軟性を失うなどのリスクについてはあまり心配ないでしょう。
肥満による健康への影響は、皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満で異なります。皮下脂肪型肥満で問題になりやすいのは、睡眠時無呼吸症候群や関節痛、月経異常などです。血管の柔軟性を失うなどのリスクについてはあまり心配ないでしょう。






