目次
1.活力とは?
「活力がみなぎるように感じる」「活力を得ていきいきとしている」などという言葉があるように、「活力」と聞くと、元気の源のような印象を持っている人が多いのではないでしょうか。
日頃の食事や運動、社会の人とのつながりは活力において大切なこととされています。
特に高齢者においては低栄養状態になると筋肉量の減少につながり、活力低下をまねくため、食事をしっかり摂ることは重要といえるでしょう。
 年齢を重ねてもいつまでも元気で活力のある毎日を送りたいというのは多くの人が願うことでしょう。活力の低下を防ぐためには毎日の食事や運動習慣が大切です。
年齢を重ねてもいつまでも元気で活力のある毎日を送りたいというのは多くの人が願うことでしょう。活力の低下を防ぐためには毎日の食事や運動習慣が大切です。
この記事では活力が低下する要因とその予防策についてお伝えします。高齢期になっても毎日元気に過ごすため、参考にしてみてください。
目次
「活力がみなぎるように感じる」「活力を得ていきいきとしている」などという言葉があるように、「活力」と聞くと、元気の源のような印象を持っている人が多いのではないでしょうか。
日頃の食事や運動、社会の人とのつながりは活力において大切なこととされています。
特に高齢者においては低栄養状態になると筋肉量の減少につながり、活力低下をまねくため、食事をしっかり摂ることは重要といえるでしょう。
 高齢期になってもいつまでも元気に過ごすためには「フレイル」予防が大切です。
高齢期になってもいつまでも元気に過ごすためには「フレイル」予防が大切です。
フレイルとは、「健康な状態」と「介護が必要な状態(要介護)」の中間段階とされ、年齢を重ねて身体能力などが衰え、回復に要する力が低下した状態をいいます。
フレイルは身体的・精神的・社会的の大きく3つに分かれます。
身体的フレイルは、ロコモティブシンドロームやサルコペニアが代表的な例です。
「ロコモティブ」とは筋肉や骨・関節などの体を動かす運動器の総称を指しています。これらの機能に障害をきたし、移動機能が低下することを「ロコモティブシンドローム」と呼び、バランス能力が低下し転倒や骨折をしやすくなり、介護が必要になる危険性が高くなります。
ロコモティブシンドロームの初期症状として多く見られるのがひざ関節の痛みです。加齢によってひざの軟骨が減ってくることで歩いたときに痛みを感じやすくなります。
以前と比べて歩くのが遅くなったり、つまずきやすくなったりなどの変化があったらロコモティブシンドロームが進行している可能性もあるため注意が必要です。
サルコペニアとは、老化や加齢による筋肉量の減少を指します。筋肉量が低下することで握力などが弱くなったり、歩く速度が遅くなったりという変化が現れやすく、ロコモティブシンドロームと同様に転倒や骨折に関わる問題です。
年齢を重ねて仕事の環境が変わること、配偶者を失うことなどで引き起こされる、うつ状態や軽い認知症などを指します。疲れやすくなって何をするのも面倒に感じるという場合は注意が必要です。
加齢にともなって外出の機会が減ったり、家族や友人との付き合いが少なくなったりすることで社会とのつながりが希薄化することによって、経済的に困窮したり独居状態になることを指します。
 いくつになっても活力を維持したいというのは多くの人が望むことでしょう。ここでは活力を支えるための方法を解説します。
いくつになっても活力を維持したいというのは多くの人が望むことでしょう。ここでは活力を支えるための方法を解説します。
フレイル予防のためには、毎日の活力の源である食事を摂ることが大切です。主食(ごはん・パン・麺類)、主菜(肉・魚・卵・大豆製品)、副菜(野菜・海草・きのこ)のそろった栄養バランスのとれた食事を3食しっかり摂りましょう。
加齢にともない食事量が減少し、たんぱく質が不足すると筋肉量も低下しやすくなり、フレイルの要因になります。そのため、高齢期になったら今まで以上にたんぱく質を意識して摂ることが大切です。毎回の料理が大変であれば、市販の総菜や缶詰・レトルト食品・また配食弁当をうまく活用してみましょう。
歩きにくくなったからと動かなくなると、ますます筋肉量が低下しやすい悪循環に陥ってしまいます。
まずはこまめに動くことから始めてみましょう。こまめに家事をする、エスカレーターではなく階段を使うことなどです。歩いているときには最大で体重の1.5倍、ジョギングの場合は体重の約2倍の負担がかかることもわかっています。そのため、久々に運動するという人は、最初から張り切り過ぎず、少しずつ強度を上げましょう。
また、足腰などに痛みがある人は、かかりつけ医や運動指導者に相談してから始めることが大切です。
ウォーキングやストレッチなどで体を動かすことは、筋肉の発達だけでなく精神的な健康にも良い影響をもたらします。今より10分多めに体を動かしてみましょう。
趣味やボランティア、仕事などで外出して人と関わる「社会参加」もフレイル予防に効果的です。また家族や友人と一緒に会話しながらの食事は、食欲を増進させることがわかっています。そのため、できるだけ一人にならず、食事を楽しむことを心がけることも大切です。
加齢とともに運動機能に障害をきたしたり、筋肉量は減少したりしていきます。それをきっかけに骨折などの怪我につながり、介護が必要にもなってしまいかねず、活力に満ちた生活を送るのが困難になってしまうでしょう。
人が活力を維持するには、適切な栄養を摂り、運動習慣を身につけ、社会とのつながりを持つことが大切です。日頃の食事や運動習慣を見直し、筋力の維持を目指すのがおすすめです。
またよく動く人は生活習慣病や認知症にもなりにくいといわれています。日頃からバランスの良い食事や運動習慣を身につけておけば、年齢を重ねても健康的な体を維持することができるでしょう。

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)
外科医として地方中核病院に勤務中。
消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。
資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医
加齢に関するお悩み

年齢とともに「血圧が上がってきたかもしれない」と、気になっている人もいるのではないでしょうか。
加齢に関するお悩み
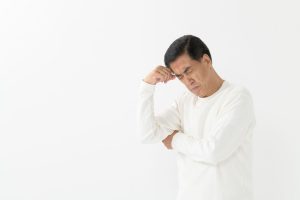
年齢とともに、「人の名前を思い出しにくくなる」「もの忘れがひどくなったりする」といった経験がある方は多いのではないでしょうか。
加齢に関するお悩み

基礎代謝は人間が生命を維持するために絶えず使っているエネルギーですが、年齢を重ねるにつれ徐々に低下するといわれています。
加齢に関するお悩み

日本では高齢者のなかでも「前期高齢者」と「後期高齢者」に年齢ごとで分けられています。
加齢に関するお悩み

高齢になると、若い頃と比べて食が細くなることが多く、体調不良や体重減少のリスクが高くなります。