目次
1.30代は疲れやすい?
働き盛りの30代は、どうしても一日のなかで仕事に関わる時間が多くなり「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」が崩れやすくなります。
厚生労働省が実施している「労働安全衛生調査(実態調査)平成30年」においても「現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある」と回答した労働者の割合は、58.0%となっています。年代別に見ても30代は64.4%の方がそう感じており、調査を行なった全年代のなかで最も多い割合です。
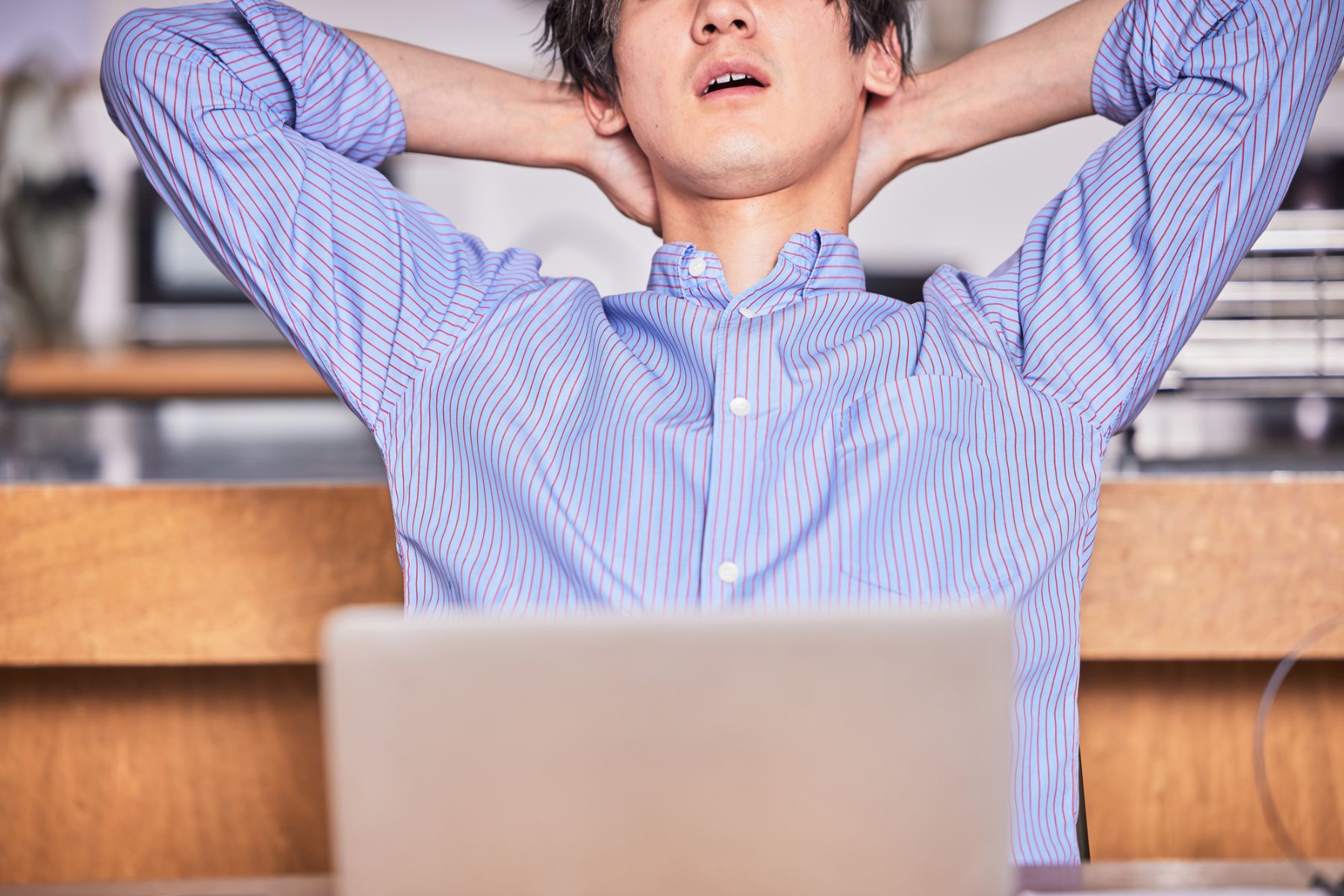 しっかり寝ているのに疲れが取れていないと感じていませんか?
しっかり寝ているのに疲れが取れていないと感じていませんか?
若い頃と比べて体力の衰えを感じても「年齢のせいかな」と放置せずに、原因を知って対策をすることで疲れを軽減することができます。
今回は、疲れの原因や対策法についてご紹介します。
目次
働き盛りの30代は、どうしても一日のなかで仕事に関わる時間が多くなり「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」が崩れやすくなります。
厚生労働省が実施している「労働安全衛生調査(実態調査)平成30年」においても「現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある」と回答した労働者の割合は、58.0%となっています。年代別に見ても30代は64.4%の方がそう感じており、調査を行なった全年代のなかで最も多い割合です。
 仕事の忙しさに関わらず疲れは誰しも経験する悩みです。そのなかでも30代が疲れやすくなる原因として、どのようなことが挙げられるでしょうか。
仕事の忙しさに関わらず疲れは誰しも経験する悩みです。そのなかでも30代が疲れやすくなる原因として、どのようなことが挙げられるでしょうか。
まずは「一時的な疲れ」と「長期的な疲れ」にわけてご説明します。
30代は、国の調査においても週の労働時間が60時間を超えている方が多い傾向にあることが示されています。仕事による長時間の拘束や、家族との時間や趣味の時間を設けることができなくなることからも心身の疲労を感じやすくなるでしょう。
季節の変わり目や、寒暖差が激しくなると体調を崩す方も多いのではないでしょうか。季節が関与する疲労の代表的な例として、夏バテが挙げられます。
夏は外気温が上がることにより体温が上昇し、多量の汗をかいて体温を下げようとします。汗には水分以外に体にとって重要なミネラルも多く含まれているため、それらが排出されてしまうことにより、体内の栄養バランスが崩れて体力の消耗が大きくなりがちです。
慢性的な睡眠不足は疲労などの心身の不調を引き起こすだけでなく、思考能力の低下やさまざまな病気の原因にもなってしまいます。
極端なダイエットなどにより必要なエネルギー不足が続くと、血糖コントロールが乱れてしまいがちです。それにより集中力が欠けたり、イライラしたり、疲れやすくなるなどの症状が現れるでしょう。また栄養バランスが悪くなると、貧血などの症状からも疲れやだるさを引き起こしやすくなります。
疲れは病気からくる場合もありますので、サインを見逃さないようにしましょう。考えられる病気の一例として、以下が挙げられます。
自律神経の働きが不安定になり、立ち上がる際など体勢を変えることで体の不調が起こることを起立性調節障害といいます。起立性調節障害では、疲労感・めまい・立ちくらみなど、さまざまな不調が目立ちます。
慢性疲労症候群はその名が示すように、全身の強い倦怠感をはじめ、頭痛・微熱・睡眠障害などの症状が現れます。休養してもこれらの症状がなかなか回復せず、6カ月以上も続くとされる疾患のため、日常生活に影響が出るケースも少なくありません。
 疲労の原因はさまざまですが、疲れを感じている場合はどのような対策をとれば良いのでしょうか。以下の内容を参考に対処法を見つけて、少しでも解消できるように取り組んでみてください。
疲労の原因はさまざまですが、疲れを感じている場合はどのような対策をとれば良いのでしょうか。以下の内容を参考に対処法を見つけて、少しでも解消できるように取り組んでみてください。
偏りのある食事は栄養バランスを崩し、貧血や血糖コントロールの乱れを引き起こします。疲労感を助長しないためにも、極端な食事量の制限や偏食を避け、適量で栄養バランスの良い食事を心がけましょう
睡眠は脳や体を休める働きがあるとされることから、睡眠不足が続くような生活を送っている場合は習慣を改めましょう。また、自律神経の乱れは疲労感と大きな関わりがあります。質の良い睡眠は自律神経を整える効果を期待できますので、毎日同じ時間に布団に入ることや、入浴は湯船に浸かる習慣をつけるなど、睡眠の質を上げる行動を意識してみてください。
適度な運動習慣は血流を促し、疲れにくい体作りに役立ちます。激しい運動ではなく、汗ばむ程度(目安は心拍数が毎分120~130程度)のジョギングを20~30分程度行なうのが理想です。
長時間労働を避け規則的な休暇を取るなど、健康的な働き方をすることで、疲労と大きく関わるストレスも軽減され生活の質の向上につながります。残業が続いているなど、仕事を多く抱えている場合は上司や会社に相談して働き方を改善しましょう。
趣味の時間や睡眠時間を確保することで、ストレスを回避しやすくなります。心身ともに健康状態を保つためにも休養する時間はしっかりと確保しましょう。
疲労を感じる原因はさまざまですが、しっかりと休養を取り、適度な運動、バランスの良い食事、質の良い睡眠を心がけるなど、日頃から生活習慣を整えることが大切です。
しかし、長期的に疲労を感じている場合、無理は禁物です。何らかの疾患が関与している可能性もあります。その際は、医療機関を受診し、医師の意見を聞くのも疲労感解消の糸口になることも考えられるでしょう。
この機会にご自身の生活習慣を振り返ってみてはいかがでしょうか。

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)
外科医として地方中核病院に勤務中。
消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。
資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医
身体に関するお悩み

吐き気や冷や汗とともにめまいが起こると、「もしかして重い病気かな?」「大丈夫なのかな?」と不安になる方が多いでしょう。
身体に関するお悩み

「うっ血」とは、血液の流れが滞ってしまうことです。
身体に関するお悩み

「飲み込みにくい」「むせる」といった症状がある方は、摂食嚥下障害の可能性があります。
身体に関するお悩み

ある日突然、音が聞こえなくなる突発性難聴。
身体に関するお悩み

痰が赤くなっていると驚いてしまいますよね。