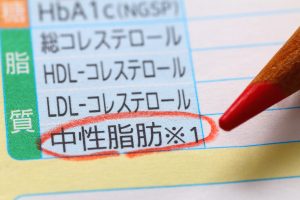1.頭痛や疲れやすいのは体内に鉄などの栄養が不足しているから
頭痛が起こりやすい、疲れやすいという場合には、鉄不足が疑われるでしょう。鉄が不足すると、赤血球の血色素であるヘモグロビンが減少し、全身へ酸素を運搬する能力が低下すると考えられています。
酸素が不足すると、疲れやすい・頭痛・気力の低下・爪の変形・肌荒れ・むくみ・息切れなどさまざまな不調を招くのです。
赤血球中のヘモグロビン濃度が低下した状態を貧血といい、最も多いタイプが「鉄欠乏性貧血」です。
ヘモグロビンは、鉄を含んでいる色素成分「ヘム」とタンパク質が結合することで「ヘムタンパク質」となります。ヘムたんぱく質は酸素と結合して全身へ運ばれるため、鉄は私たちの体調維持にとって欠かせない栄養素といえるでしょう。
2.貧血(頭痛・疲労)予防に必要な栄養素
 貧血予防には、日頃の食事よりしっかりと鉄を補うことが大切です。
貧血予防には、日頃の食事よりしっかりと鉄を補うことが大切です。
成人男性では一日あたり約1mg、成人女性では約0.8mgの鉄が失われます。特に、女性は月経時だと、一日あたり約0.5mgの鉄をさらに失うため、日々の食事から鉄をしっかりと補う必要があるのです。
食事から摂取した鉄は、そのうち15%程度が吸収されるといわれているため、損失量と吸収率を踏まえて日々の摂取量を考える必要があるでしょう。
なお、厚生労働省は成人男性と成人女性に対し、それぞれ以下の量の鉄を日々摂取するよう推奨しています。
-
・成人男性:7.5mg
-
・月経のある女性:10.5mg
-
・月経のない女性:6.5mg
参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
食品に含まれる鉄は、「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2種類です。「ヘム鉄」は、赤みのある肉類や魚類に多く含まれ、吸収率が高く25%といわれています。
一方の「非ヘム鉄」は、野菜や卵、穀物類、豆類、海藻類などに多く含まれます。吸収率はヘム鉄と比べて低く、3~5%ほどです。
さらに、鉄と併せて、ヘモグロビンの材料であるタンパク質や、鉄の吸収を助けるビタミンCも摂取するとよいでしょう。赤血球を作るうえでは、葉酸やビタミンB12もかかせないため、下記の食品を組み合わせて調理することをおすすめします。
-
・鉄とタンパク質を多く含む食品:牛肉、あさり、カツオなどの赤身の魚 など
-
・ビタミンCを多く含む食品:緑黄色野菜、柑きつ類 など
-
・葉酸を多く含む食品:ほうれん草、ブロッコリー、アスパラガス、納豆 など
-
・ビタミンB12を多く含む食品:魚介類、チーズ など
3.その他栄養不足が原因で体におよぼす悪影響
 他の栄養素が不足すると、私たちの体へどのような影響をおよぼすのでしょうか。炭水化物、脂質、ビタミンの3つについて解説します。
他の栄養素が不足すると、私たちの体へどのような影響をおよぼすのでしょうか。炭水化物、脂質、ビタミンの3つについて解説します。
3-1.炭水化物不足
炭水化物とは、エネルギー源として大切な栄養素です。炭水化物には、消化吸収される「糖質」と、消化吸収されない「食物繊維」に分けられ、食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維にさらに分かれます。
糖質が不足すると、エネルギー不足による疲労感や集中力の減少が見られるでしょう。一方で摂取しすぎると中性脂肪として内臓に蓄積され、肥満や生活習慣病の原因となるため注意が必要です。
また、食物繊維が不足すると、便秘などのリスクが増加するといわれています。
3-2.脂質不足
脂質は長時間の運動において、効率の良いエネルギー源として使われる栄養素です。その他、脂溶性ビタミンの吸収をサポートするうえでも欠かせません。
現代の日本人の食生活では、不足することはほとんどないといわれています。とはいえ、極端に脂質の摂取量を減らすと、肌が乾燥したり便が固くなり排泄しにくくなったりするため、注意が必要です。
一方で摂りすぎると、体脂肪として蓄積される可能性があるため、生活習慣病の原因となります。
3-3.ビタミン不足
ビタミンは、体の機能を正常に保つうえで欠かせない栄養素です。体内ではあまり生成されないため、食事から摂取する必要があります。
ビタミン不足による症状は、ビタミンの種類によって異なるため、一つずつ見ていきましょう。
-
ビタミンA
脂溶性ビタミンの一種です。目や皮膚、粘膜の健康維持に大切なビタミンで、感染症予防や免疫力を高めるために必要とされています。
ビタミンA不足になると、神経や骨の発達の不良、感染症にかかりやすくなるなどの症状が現れるため注意しましょう。
-
ビタミンD
ビタミンDも脂溶性ビタミンの一つで、日光を浴びると皮膚で作られます。カルシウムの吸収促進にかかせない栄養素です。
ビタミンD不足になると、カルシウムの吸収が低下して骨が弱くなり、骨折を引き起こしかねないため注意が必要です。
-
ビタミンB1
水溶性ビタミンの一つであり、糖質がエネルギーに変わるのをサポートする栄養素です。
ビタミンB1不足による症状の代表は、足元のふらつきです。その他に、疲れやすくなったり、最大酸素摂取量の低下を招いたりするおそれがあるため注意しましょう。
-
ビタミンB2
糖質だけでなく、脂質やたんぱく質がエネルギーに変わるのをサポートする栄養素で、水溶性ビタミンの一つです。
ビタミンB2が不足すると、肌荒れや口内炎など皮膚への症状が出やすくなり、目の疲れや子どもの成長に影響することもあります。
-
ビタミンC
水溶性ビタミンの一つです。鉄の吸収促進や、抗ストレス・抗酸化作用においても欠かせません。その他、皮膚や軟骨、腱などを構成するコラーゲン合成においても重要な栄養素です。
ビタミンCが不足すると、血管がもろくなり出血しやすくなるおそれがあります。子どもの場合は、骨の発育への影響にも注意しましょう。
栄養不足での頭痛にはバランスの良い食事を心がけましょう
頭痛や疲れやすさの原因として、鉄をはじめとする栄養不足が考えられます。
鉄は日々少しずつ減少するため、毎日補うことが大切です。また、炭水化物や脂質が不足するとエネルギー不足、ビタミンが不足するとさまざまな身体機能への不調などが現れやすくなります。
日頃からバランスの良い食事で栄養を補い、健やかな日々を送れるよう体調管理を心がけましょう。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


 日々の食事から、しっかりと栄養素を摂ることは大切です。とはいえ、バランスの良い食事を毎回とることは難しい、という方もいるかもしれません。
日々の食事から、しっかりと栄養素を摂ることは大切です。とはいえ、バランスの良い食事を毎回とることは難しい、という方もいるかもしれません。 貧血予防には、日頃の食事よりしっかりと鉄を補うことが大切です。
貧血予防には、日頃の食事よりしっかりと鉄を補うことが大切です。 他の栄養素が不足すると、私たちの体へどのような影響をおよぼすのでしょうか。炭水化物、脂質、ビタミンの3つについて解説します。
他の栄養素が不足すると、私たちの体へどのような影響をおよぼすのでしょうか。炭水化物、脂質、ビタミンの3つについて解説します。