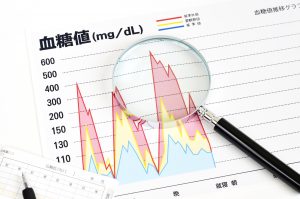1.ADLとは?
ADLはActivities of Daily Livingの略で、日常生活を送るために最低限行なう必要がある「起きあがる動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」という日常的動作を指す言葉です。
介護やリハビリテーションの現場において、ADLは高齢者や障がい者の身体能力や日常生活レベルを測るための重要な指標として用いられています。
ADLは身体機能・認知機能・精神面・社会環境と関係し合っており、このなかの一つでも機能の低下が認められると、ADLの低下につながってしまうため注意してください。
2.ADLの種類
 ADLには2つの種類があり、日常生活で行なう動作を基本的な動作と複雑な動作に分けて考える必要があります。
ADLには2つの種類があり、日常生活で行なう動作を基本的な動作と複雑な動作に分けて考える必要があります。
どのような種類があるのか見ていきましょう。
2-1.BADL(Basic ADL)
BADLは基本的日常生活動作といわれ、一般的には日常生活動作(ADL)のことを指します。具体的には、「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」などの動作のことです。
2-2.IADL(Instrumental ADL)
IADLは手段的日常生活動作といわれ、BADLの次の段階の動作を指します。
具体的には、「掃除・料理・洗濯・家事・買い物・交通機関の利用・コミュニケーション・金銭管理」などの、BADLよりも複雑な動作のことです。
3.ADLの低下が日常生活に与える影響
 ADLが低下すると起こりうるのが、活動性の低下による社会参加の機会の減少です。
ADLが低下すると起こりうるのが、活動性の低下による社会参加の機会の減少です。
例えば、体力・筋力・筋肉量・高密度・内臓機能などの身体機能が低下すると、歩行障害や易疲労性、食欲低下などが起こり、動作がしにくくなったり、ふらつきや転倒をしやすくなったりします。
また、認知機能が低下すると、もの忘れや記憶障害、自分がいる場所や時間、誰と何をしているのかが理解できなくなる見当識障害、順序立てて物事を考えることが困難になる遂行機能障害、判断力・コミュニケーション能力の低下なども懸念されます。
その結果、人や物の名前などの情報が思い出せない、道に迷う、料理の手順がわからなくなるなどの症状が見られるようになるのです。
日常での活動性が低下することで、精神的にも塞ぎ込んでしまい、自立度が下がって介護が必要となり、寝たきりとなってしまうケースもあります。
活動性を維持してADL低下を予防しよう
今回は、ADLの種類やADLの低下が日常生活に与える影響について紹介しました。
ADL低下の予防をするためには、運動をして栄養をとり、家事や趣味などの活動を含めて日常生活を送ること自体が効果的です。
家から社会に出てコミュニケーションの機会を作ったり、社会的な役割を担ったりして生活の幅が広がることが、ADLにおいて大きな意味をなします。
現状の能力を活かせる手段を探索することや、日々の活動性を維持できるような行動を意識して生活するようにしましょう。
監修者情報

氏名:井林雄太(いばやし・ゆうた)
総合病院勤務。大分大学医学部卒。
日本内科学会認定内科医、日本内分泌内科専門医、日本糖尿病内科専門医の資格を保有。現在は医師業務のかたわら、正しい医療情報を伝える啓発活動も市民公開講座など通して積極的に行なっている。


 みなさんはADLという言葉を耳にしたことはありますか?
みなさんはADLという言葉を耳にしたことはありますか? ADLには2つの種類があり、日常生活で行なう動作を基本的な動作と複雑な動作に分けて考える必要があります。
ADLには2つの種類があり、日常生活で行なう動作を基本的な動作と複雑な動作に分けて考える必要があります。 ADLが低下すると起こりうるのが、活動性の低下による社会参加の機会の減少です。
ADLが低下すると起こりうるのが、活動性の低下による社会参加の機会の減少です。