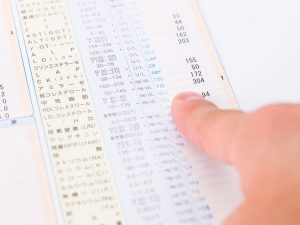1.低血糖について
低血糖の概要とおもな症状を解説します。
1-1.低血糖とは
低血糖とは、血中のブドウ糖濃度が低くなる状態のことです。血糖値は通常は一定範囲内(空腹時70~110mg/dL)で推移していますが、その範囲を下回ると低血糖となります。
糖尿病の治療のために薬を使用しているなど特定の人を除けば、血糖値が70mg/dLより低下することはまれです。しかし、激しい運動を長時間続けたり、炭水化物の摂取を過剰に避けたりした場合にも低血糖を起こす可能性があります。低血糖は早朝の空腹時や毎食前、就寝時などに起こりやすく、食事のタイミングがいつもより遅れたときに出現しやすいです。
1-2.低血糖が引き起こすおもな症状
血糖値が60~70mg/dL未満になると、冷や汗や動悸、頭痛、寒気、悪心、脱力感などが出現します。強烈な空腹感を覚えたり、気持ち悪くなったりするのも代表的な症状です。手足の震えや目のちらつきを自覚することもあります。これらの症状は、下がりすぎた血糖を上げるために、グルカゴンやアドレナリンといったホルモンが分泌されて起こります。
さらに低下して血糖値が50mg/dL未満に至ると脳の機能が低下して、意識がぼんやりしたり、うとうとしたり、目の前が暗くなって倒れそうになったりします。また、ろれつが回らなくなったり、支離滅裂な発言や異常行動を起こしたりする場合もあります。重篤な症状として、意識を失う、けいれんを起こすなどがあり、これらの症状を「中枢神経症状」といいます。
低血糖はすぐにブドウ糖を補給すれば回復しますが、中枢神経症状が数時間続くと脳の損傷など致命的な事態になるケースもあるため、適切に対応する必要です。
2.低血糖の原因
 低血糖のおもな原因は、薬の副作用と生活習慣です。低血糖を起こしやすい薬として、糖尿病治療薬や抗生物質などが挙げられます。生活習慣としては、炭水化物(糖質)を過度に制限する食生活を送ったり、運動量が多すぎたりすると低血糖が起こりやすいです。
低血糖のおもな原因は、薬の副作用と生活習慣です。低血糖を起こしやすい薬として、糖尿病治療薬や抗生物質などが挙げられます。生活習慣としては、炭水化物(糖質)を過度に制限する食生活を送ったり、運動量が多すぎたりすると低血糖が起こりやすいです。
なお、高齢者や乳幼児では低血糖の自覚症状が現れない場合も多く、発見が遅れて症状が悪化してしまう可能性があります。高齢者は、特に注意しましょう。
3.低血糖を予防する方法
 低血糖を予防するためには、極端な糖質制限を行なわず、日頃から適量の糖質を摂るようにすることが大切です。空腹時の運動は低血糖を起こしやすいので、激しい運動を行なうときは途中でできるだけ糖分を補給し、長時間連続にならないように気をつけましょう。
低血糖を予防するためには、極端な糖質制限を行なわず、日頃から適量の糖質を摂るようにすることが大切です。空腹時の運動は低血糖を起こしやすいので、激しい運動を行なうときは途中でできるだけ糖分を補給し、長時間連続にならないように気をつけましょう。
糖尿病の薬を飲んでいる人は、自己判断で食事制限や運動などを行なうと低血糖を起こす危険があります。食事や薬、生活面の疑問点は、必ず医師や栄養士などに相談してください。糖尿病薬の種類によっては、低血糖のリスクに違いがあったり、低血糖時に砂糖を補給しても低血糖が解消されず、必ずブドウ糖を投与しなければならなかったりと、注意点が異なるケースもあります。自分の服用薬の特性を知り、不明点は医師や薬剤師に確認しましょう。
食事は毎日同じくらいの時間帯でとり、糖尿病薬の服用前後の食事は必ず決められたタイミングで摂るといった工夫も大切です。
低血糖を予防して健やかな毎日を送ろう
低血糖は血液中のブドウ糖濃度下がりすぎている状態です。血糖値が70mg/dLを下回ると冷や汗や寒気、動悸などの症状が起こります。さらに深刻な低血糖では、意識障害やけいれんなどのリスクがあります。
低血糖は糖尿病薬などの医薬品を服用している人に多く見られますが、過度の糖質制限や激しい運動などでも起こる可能性があります。
適量の糖質を摂取して適切な血糖値を保ち、全身にエネルギーを補給しましょう。
監修者情報

氏名:高橋健太郎(たかはし・けんたろう)
循環器内科医として臨床に関わりながら、心血管疾患のメカニズムを解明するために基礎研究に従事。現在はアメリカで生活習慣病が心血管疾患の発症に及ぼす影響や心血管疾患の新しい治療法の開発に取り組んでいる。国内・海外での学会発表や論文報告は多数。
日本内科学会認定内科医、日本循環器学会所属。


 「食事が遅れたら、ふらふらして気持ち悪くなってきた」
「食事が遅れたら、ふらふらして気持ち悪くなってきた」 低血糖のおもな原因は、薬の副作用と生活習慣です。低血糖を起こしやすい薬として、糖尿病治療薬や抗生物質などが挙げられます。生活習慣としては、炭水化物(糖質)を過度に制限する食生活を送ったり、運動量が多すぎたりすると低血糖が起こりやすいです。
低血糖のおもな原因は、薬の副作用と生活習慣です。低血糖を起こしやすい薬として、糖尿病治療薬や抗生物質などが挙げられます。生活習慣としては、炭水化物(糖質)を過度に制限する食生活を送ったり、運動量が多すぎたりすると低血糖が起こりやすいです。 低血糖を予防するためには、極端な糖質制限を行なわず、日頃から適量の糖質を摂るようにすることが大切です。空腹時の運動は低血糖を起こしやすいので、激しい運動を行なうときは途中でできるだけ糖分を補給し、長時間連続にならないように気をつけましょう。
低血糖を予防するためには、極端な糖質制限を行なわず、日頃から適量の糖質を摂るようにすることが大切です。空腹時の運動は低血糖を起こしやすいので、激しい運動を行なうときは途中でできるだけ糖分を補給し、長時間連続にならないように気をつけましょう。