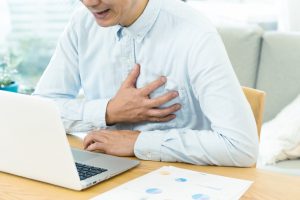1.夏バテのおもな症状と原因
 まずは、夏バテのおもな症状や原因を見ていきましょう。
まずは、夏バテのおもな症状や原因を見ていきましょう。
1-1.ミネラル・水分の欠乏による脱水症状
夏の暑さによって汗をたくさんかくと、体内のミネラルと水分が欠乏し、脱水症状を引き起こします。その結果、食欲不振やめまいといった症状が現れかねないので、注意が必要です。
1-2.食欲低下による栄養不足
暑さにより食欲が低下し、冷たいものをたくさん飲食すると、栄養が偏って栄養不足に陥りやすくなります。それにより、だるさや疲れを感じやすくなるでしょう。
1-3.室内外の温度差による自律神経の乱れ
夏は、非常に暑い室外に対して室内はクーラーで冷えているため、室内外の温度差が大きくなりがちです。そういった環境を行き来することによって、自律神経のバランスが乱れやすくなります。
自律神経は、体内のすべての臓器とつながり、全身を調整するシステムです。そのため、自律神経が乱れると、だるさを感じたり疲れがとれにくくなったりします。
夏バテによって体調不良に陥ると、感染症などさらなる症状を招きやすくなるため、対策することが大切です。
2.日常生活でできる夏バテ対策
 夏の暑さに負けない体をつくるには、日常生活を整えることが必要です。ぜひ、次のポイントを意識してみてください。
夏の暑さに負けない体をつくるには、日常生活を整えることが必要です。ぜひ、次のポイントを意識してみてください。
2-1.きちんと水分補給を行なう
まずは、脱水症状を起こさないために、きちんと水分補給を行ないましょう。
ヒトは暑さやのどの渇きを感じていなくても、汗や尿などによって一日2.5Lもの水分を失っています。そのため、特に夏は意識して水分補給をすることが大切です。
ただし、水分補給の際に冷たい飲み物を選ぶのはなるべく避けましょう。冷たい飲み物は内臓の働きを弱めてしまいやすいので、温かい飲み物か常温の飲み物をおすすめします。
2-2.きちんと食事をとる
暑くて食欲がわかないときも、栄養バランスを意識してきちんと食事をしましょう。特に、ビタミンB1、ビタミンC、タンパク質は不足しやすいため、積極的に摂取することをおすすめします。
-
ビタミンB1
ビタミンB1は、疲労を回復する働きがある栄養素です。汗によって体外に出やすく、夏は特に不足しやすくなるため、意識的に摂取しましょう。
ビタミンB1は、豚肉や大豆、枝豆、ブロッコリー、玄米などに多く含まれています。
-
ビタミンC
ビタミンCは、病気やストレスへの抵抗力を高める作用などが期待できます。ビタミンCは、ヒトの体でつくり出すことができないため、食事でしっかり摂取することが大切です。
ビタミンCは焼きのりやブロッコリー、ピーマン、キウイフルーツ、レモンなど野菜・果物に多く含まれています。
-
タンパク質
タンパク質は、体をつくる基となるほか、体内の機能調整を行なう働きがあります。生成に必要なアミノ酸が足りていなければ、体内でタンパク質を十分につくれないため、食事から意識的に摂取するようにしましょう。
タンパク質は、魚介類や肉類、大豆製品、乳製品、卵などに多く含まれています。
2-3.部屋を冷やしすぎないようにする
室内外の気温差が大きいと、自律神経の乱れにつながります。そのため、エアコンの温度は28度ほどに設定し、外との気温差が5度以上にならないようにしましょう。
2-4.十分な睡眠をとる
暑さによる疲れを癒したり、自律神経を整えたりするうえで、睡眠は大切です。
その際、エアコンをつけたまま寝ると体調不良の原因になりかねないため、エアコンのタイマー設定を上手に利用しましょう。
2-5.運動習慣をつける
私たちの体は、体温調節をする際に汗をかいて体内の熱を逃がす機能がありますが、この機能は室内外の気温差によって乱れがちです。暑い時期に習慣的に運動して汗をかくと暑さに対して強い体になり、体温の調節機能を改善しやすくなります。
夏バテの症状を把握しイキイキとした日常を過ごしましょう
夏バテの原因はいくつかありますが、いずれも日々の過ごし方に気を付けることで防ぎやすくなるでしょう。
夏バテを防ぐためには、水分補給をきちんと行なうこと、毎日バランスの良い食事をとること、部屋を冷やしすぎないこと、十分な睡眠をとることが大切です。また、習慣的に運動して汗をかき、暑さに対して強い体をつくることも重要となります。
ぜひ、夏をイキイキと過ごせるように、自分の生活習慣を見つめ直してみてください。
監修者情報

氏名:梅村 将成(うめむら・まさなり)
外科医として地方中核病院に勤務中。
消化器外科のみならず総合診療医として、がん治療(手術・抗がん剤・緩和治療/看取り)を中心に、幅広く内科疾患・救急疾患の診療を行なっている。
資格:医師免許・外科専門医・腹部救急認定医
 まずは、夏バテのおもな症状や原因を見ていきましょう。
まずは、夏バテのおもな症状や原因を見ていきましょう。


 暑さが厳しい夏は、食欲がわかず疲れがとれにくい、という人が多いのではないでしょうか。病気になっていないにも関わらず、体の不調を感じるのは夏バテが疑われます。
暑さが厳しい夏は、食欲がわかず疲れがとれにくい、という人が多いのではないでしょうか。病気になっていないにも関わらず、体の不調を感じるのは夏バテが疑われます。 夏の暑さに負けない体をつくるには、日常生活を整えることが必要です。ぜひ、次のポイントを意識してみてください。
夏の暑さに負けない体をつくるには、日常生活を整えることが必要です。ぜひ、次のポイントを意識してみてください。