1.アラキドン酸(ARA)とは
アラキドン酸(ARA)とは、n-6系の多価不飽和脂肪酸の一種です。多価不飽和脂肪酸は、肝臓、皮膚、脳など、人間の身体のさまざまな組織を構成する主要な成分とされています。
n-6系不飽和脂肪酸とは、メチル基側の炭素から6つ目に不飽和結合があることに由来しています。
アラキドン酸(ARA)はおもに食事から摂取するリノール酸から合成されるもので、必須脂肪酸に分類されています。必須脂肪酸は代謝に関与しており、不足すると体調不良を起こす原因になると考えられているのです。
また、必須脂肪酸は人間の身体のなかで合成できないことから、食事から摂らなければならない脂肪酸です。アラキドン酸(ARA)が多く含まれる食品はおもに魚、肉、卵ですが、詳細は3章にて解説することとします。
2.アラキドン酸(ARA)のおもな働き
 アラキドン酸(ARA)は「n-6系脂肪酸」「必須脂肪酸」などに分類されます。
先述したように、n-6系脂肪酸は多価不飽和脂肪酸の一種です。多価不飽和脂肪酸は肝臓、皮膚、脳など、身体のさまざまな組織を構成する主要な成分です。
アラキドン酸(ARA)は「n-6系脂肪酸」「必須脂肪酸」などに分類されます。
先述したように、n-6系脂肪酸は多価不飽和脂肪酸の一種です。多価不飽和脂肪酸は肝臓、皮膚、脳など、身体のさまざまな組織を構成する主要な成分です。
アラキドン酸(ARA)自体においては、血圧をコントロールする働きや、コレステロールの低下作用や血栓を防ぐなど、人体においてさまざまな働きを担っています。
そのほかに、以下に説明する働きもあるとされています。
2-1.高齢者にとっての“脳の栄養素”として注目
近年、アラキドン酸(ARA)が高齢者の脳の働きにも重要な役割を果たすことがわかり、“脳の栄養素”として注目されるようになりました。
かねてから、加齢とともに血中のアラキドン酸(ARA)が減少することが確認されていました。しかし、さらなる研究の結果、加齢によってアラキドン酸(ARA)の生成能力自体も低下することも判明し、それが血中のアラキドン酸(ARA)量が減少する原因ではないかと考えられています。
アラキドン酸(ARA)を生成する酵素は、人間の脳にとって重要なDHA・EPAとも共通していることから、DHAやEPAも加齢にともなう生成能力の低下が推測されます。脳の働きを維持するためにも、食事からアラキドン酸(ARA)やDHA・EPAを摂取するように心がけましょう。
2-2.母乳にも含まれており、乳幼児の発育には欠かせない栄養素
赤ちゃんの発育や発達にとって重要な栄養源である母乳には、アラキドン酸(ARA)をはじめ、リノール酸、α-リノレン酸などが豊富に含まれているという報告もあります。
また、アラキドン酸(ARA)は胎児期から乳児期において、網膜や脳神経細胞に急速に蓄積される脂肪酸だといわれています。
そのことからも、アラキドン酸(ARA)は赤ちゃんの発達や成長について欠かすことのできない脂肪酸と考えられているのです。
魚に含まれる脂肪酸として知られるDHAも、アラキドン酸(ARA)と同様の重要性を担いますが、両者の摂取はバランスよく行なう必要があります。DHAのほうが特に多く摂取された場合、相対的にアラキドン酸(ARA)の利用が減少することが懸念されているためです。
その懸念については、いくつかの臨床試験の結果から、2007年7月に開催されたCODEX総会(国連の食品規格委員会) にて、「乳児用調整乳にDHAを配合する場合には同量以上のARA(アラキドン酸)を配合する」という規格案が合意されました。
3.アラキドン酸(ARA)が含まれているおもな食べ物
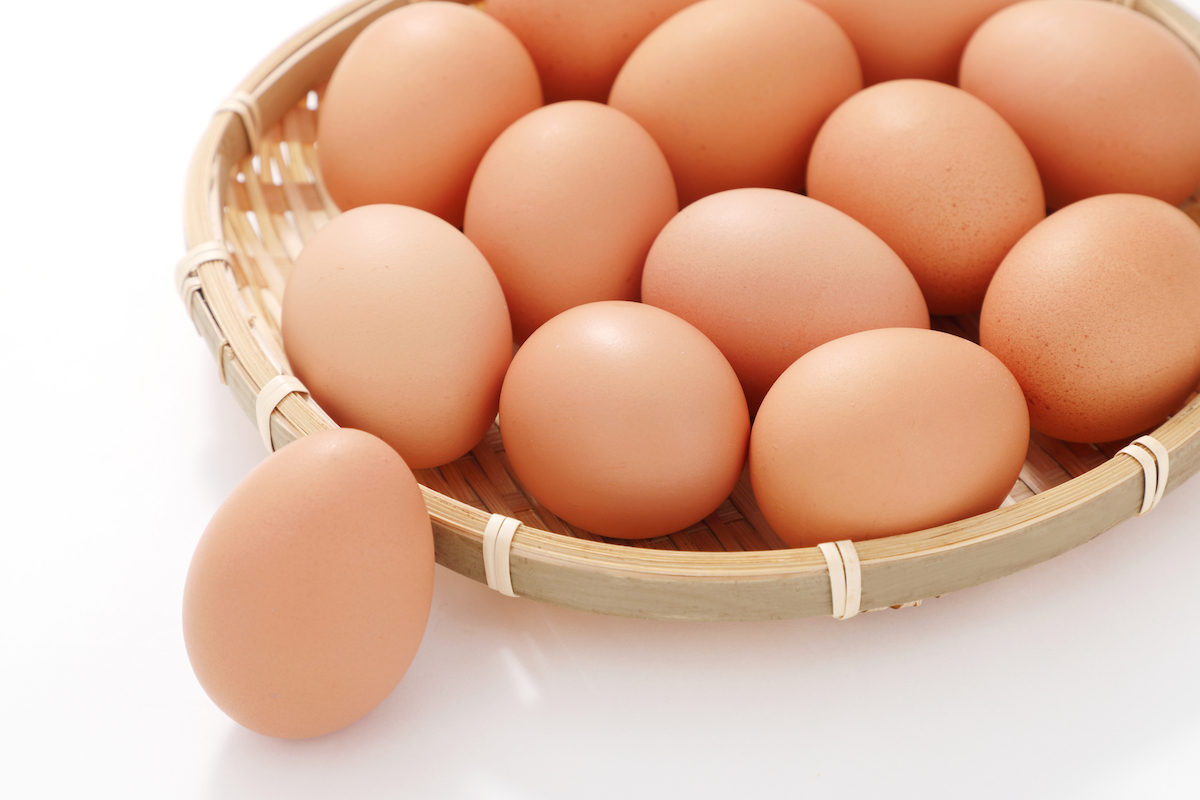 アラキドン酸(ARA)は、卵や肉類、魚類などに多く含まれています。代表的な食べ物は、以下のとおりです。
アラキドン酸(ARA)は、卵や肉類、魚類などに多く含まれています。代表的な食べ物は、以下のとおりです。
・鶏卵
・マグロ(みなみまぐろトロ)
・真鯛
・サザエ
必須脂肪酸であるアラキドン酸(ARA)は、酸化されやすいため、ドレッシングなどの高温で調理しない形での摂取が向いています。
3-1.アラキドン酸(ARA)の1日あたりの摂取目安量
食事から摂る脂質量は、健康を保つうえでは多すぎても少なすぎても良くないとされています。そのことから、日本人の食事摂取基準(脂質に関する部分)では、複数ある脂質のうち、それぞれの摂取目標量や目安量を、以下のように設定しています。
|
性別 |
男性 |
女性 |
| 年齢 |
18-29歳 |
30-49歳 |
50-64歳 |
65-74歳 |
75歳以上 |
18-29歳 |
30-49歳 |
50-64歳 |
65-74歳 |
75歳以上 |
| 脂質(エネルギー比率) |
目標量 |
20%以上30%未満 |
20%以上30%未満 |
| 飽和脂肪酸(エネルギー比率) |
目標量 |
7%以下 |
7%以下 |
| n-6脂肪酸(g/日) |
目標量 |
11g |
10g |
9g |
8g |
8g |
7g |
| 妊婦9g
授乳婦10g |
| n-3脂肪酸(g/日) |
目標量 |
2.0g |
2.2g |
2.1g |
1.6g |
1.9g |
2.0g |
1.8g |
| 妊婦1.6g
授乳婦1.8g |
(農林水産省 日本人の食事摂取基準(脂質に関する部分)を元に作成)
また、上記にて示す表は成人における摂取基準ですが、n-6系脂肪酸における、乳児からの摂取量を以下に示します。
| n-6系脂肪酸の摂取量(中央値:g/日) |
| 年齢 |
男性 |
女性 |
| 1~2(歳) |
4.30 |
4.48 |
| 3~5(歳) |
6.29 |
6.20 |
| 6~7(歳) |
8.06 |
7.24 |
| 8~9(歳) |
8.15 |
7.36 |
| 10~11(歳) |
10.12 |
8.45 |
| 12~14(歳) |
10.73 |
9.17 |
| 15~17(歳) |
12.62 |
9.13 |
| 18~29(歳) |
10.67 |
8.43 |
| 30~49(歳) |
10.44 |
8.57 |
| 50~64(歳) |
10.53 |
8.64 |
| 65~74(歳) |
9.46 |
8.21 |
| 75以上(歳) |
8.25 |
7.23 |
| 妊婦 |
─ |
9.13 |
| 授乳婦 |
─ |
10.17 |
(厚生労働省:平成 28 年国民健康・栄養調査をもとに作成)
n-6系脂肪酸は、慢性炎症の関係により、単独で摂取するよりもn-3系脂肪酸であるDHA、EPAなどの脂肪酸と組み合わせて、バランスよく取り入れることが望まれています。
必須脂肪酸のアラキドン酸(ARA)は食事などから積極的に摂取しよう
アラキドン酸(ARA)は、体内を構成する主要な成分であるにもかかわらず、体内で合成できない必須脂肪酸であるため、食事などから取り入れる必要があります。必須脂肪酸は、不足したり種類のバランスが悪かったりすると、体調を崩す原因にもなりえるものです。
アラキドン酸(ARA)は、赤ちゃんや高齢者の脳の働きにおいても重要な役割をもっている反面、加齢にともなってその生成能力は下がっていくといわれています。
それらのことから、食事などからの積極的な摂取が望まれます。
日々バランスのとれた食事を意識し、継続的に取り入れていきましょう。
監修者情報

氏名:河村優子(かわむら・ゆうこ)
アンチエイジングをコンセプトに体の中と外から痩身、美容皮膚科をはじめとする様々な治療に取り組む医師。海外の再生医療を積極的に取り入れて、肌質改善などの治療を行ってきたことから、対症療法にとどまらない先端の統合医療を提供している。


 脂質は、糖質やたんぱく質と比較して、1gあたり2倍以上のエネルギー価をもつといわれ、人間のエネルギー産生にとって主要な物質です。この脂質を構成する成分の一つに脂肪酸があります。
脂質は、糖質やたんぱく質と比較して、1gあたり2倍以上のエネルギー価をもつといわれ、人間のエネルギー産生にとって主要な物質です。この脂質を構成する成分の一つに脂肪酸があります。
 アラキドン酸(ARA)は「n-6系脂肪酸」「必須脂肪酸」などに分類されます。
先述したように、n-6系脂肪酸は多価不飽和脂肪酸の一種です。多価不飽和脂肪酸は肝臓、皮膚、脳など、身体のさまざまな組織を構成する主要な成分です。
アラキドン酸(ARA)は「n-6系脂肪酸」「必須脂肪酸」などに分類されます。
先述したように、n-6系脂肪酸は多価不飽和脂肪酸の一種です。多価不飽和脂肪酸は肝臓、皮膚、脳など、身体のさまざまな組織を構成する主要な成分です。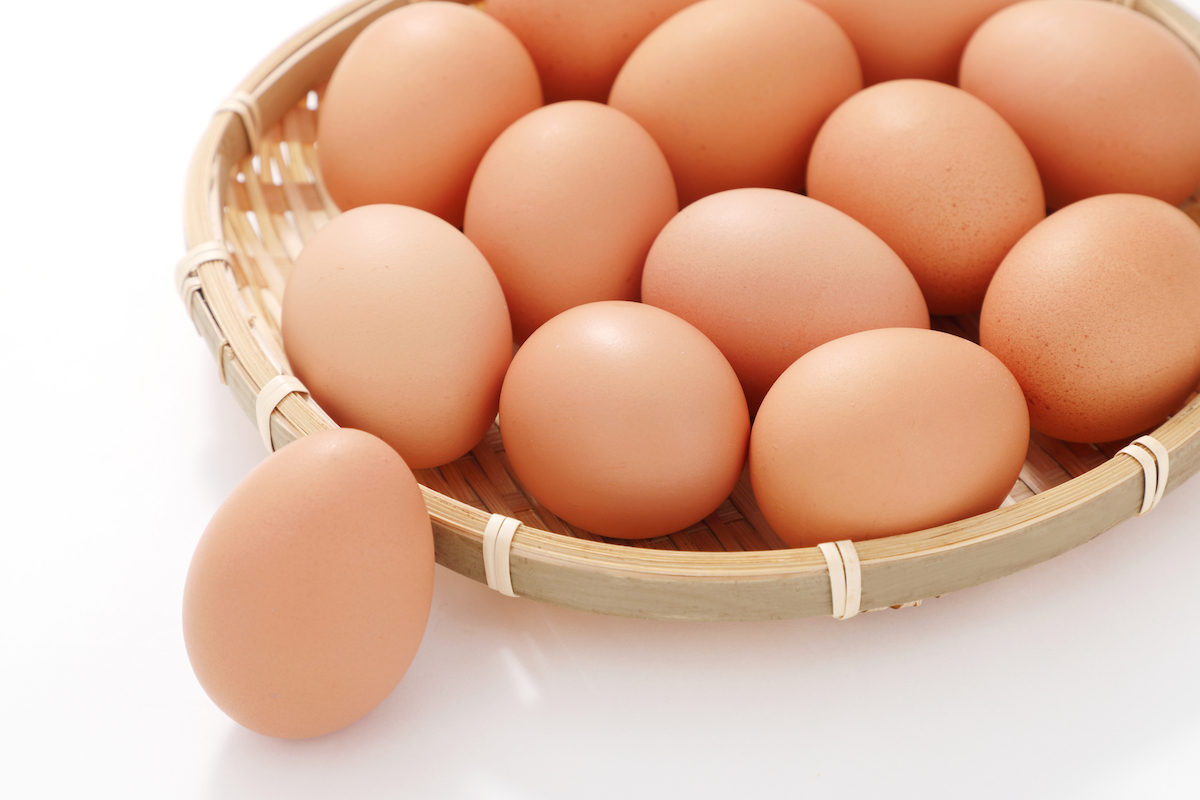 アラキドン酸(ARA)は、卵や肉類、魚類などに多く含まれています。代表的な食べ物は、以下のとおりです。
アラキドン酸(ARA)は、卵や肉類、魚類などに多く含まれています。代表的な食べ物は、以下のとおりです。






