目次
1.痰が出る原因について
 痰が出る原因には、環境や病気などさまざまな要因があります。また、痰が常にたまっていると、呼吸のしにくさや咳などに悩まれることもあるでしょう。
痰が出る原因には、環境や病気などさまざまな要因があります。また、痰が常にたまっていると、呼吸のしにくさや咳などに悩まれることもあるでしょう。
ここでは、痰が出る原因や痰がたまった場合に、どのようなことが起こるのかについて詳しく解説します。
1-1.痰が出る原因
痰は肺のなかの分泌物や吸い込んだ空気中に含まれていた異物が、気道の粘液とともに出されたものです。気道の中を潤している粘液は、免疫機能を果たしており、外部から侵入してきたものをキャッチして健康的な体を保っています。
このように異物を体内に入れないようにすることで、肺の中を清潔に保っているのです。気道は常に粘液が出ていますが、健康的な方であれば、喉まで運ばれる分泌液は少量のため、自然と飲み込まれます。そのため、粘液が痰として出ることはほとんどありません。
痰が出る場合は、感染症や炎症などを起こしている可能性があります。適切な治療が必要なケースもあるため、気になる場合は医師に相談してみてください。
原因を突き止めるためには、症状の経過や痰の色など、さまざまな情報が大切です。病院を受診する際は、それまでの状況を細かく記録して、医師に話せるように準備しましょう。
また、禁煙によって咳や痰が治まるケースもあります。本人が喫煙者ではなくても、身近に喫煙者がいる環境でも同様です。
1-2.痰がたまるとどうなる?
痰がしっかり排出できずに気道にたまると、さまざまな症状が引き起こされます。例えば、たまった痰が気道を狭くするため、息切れや呼吸のしにくさを感じるでしょう。ひどくなると空気が肺の中に入らなくなり、酸素濃度が低下します。
また、痰を体外に出そうとして激しく咳き込むこともあるでしょう。さらに細菌に感染しやすくなり、肺の病気になるリスクも高まります。その他に、痰を出すために咳が頻繁に出るため、咳による不眠や疲労も起こるでしょう。このような状態が続くと、生活の質が落ちてしまいます。
しかし、咳は痰を体の外に出す重要な働きをしているため、薬による咳止めには注意が必要です。咳止め薬を服用する場合は、医師と相談することをおすすめします。
高齢者の場合、加齢によって咳をする機能が低下して、痰が出にくくなることもあるでしょう。そうなると誤嚥によって肺の病気を引き起こす可能性があるため、あえて咳を出す薬が処方されることもあります。


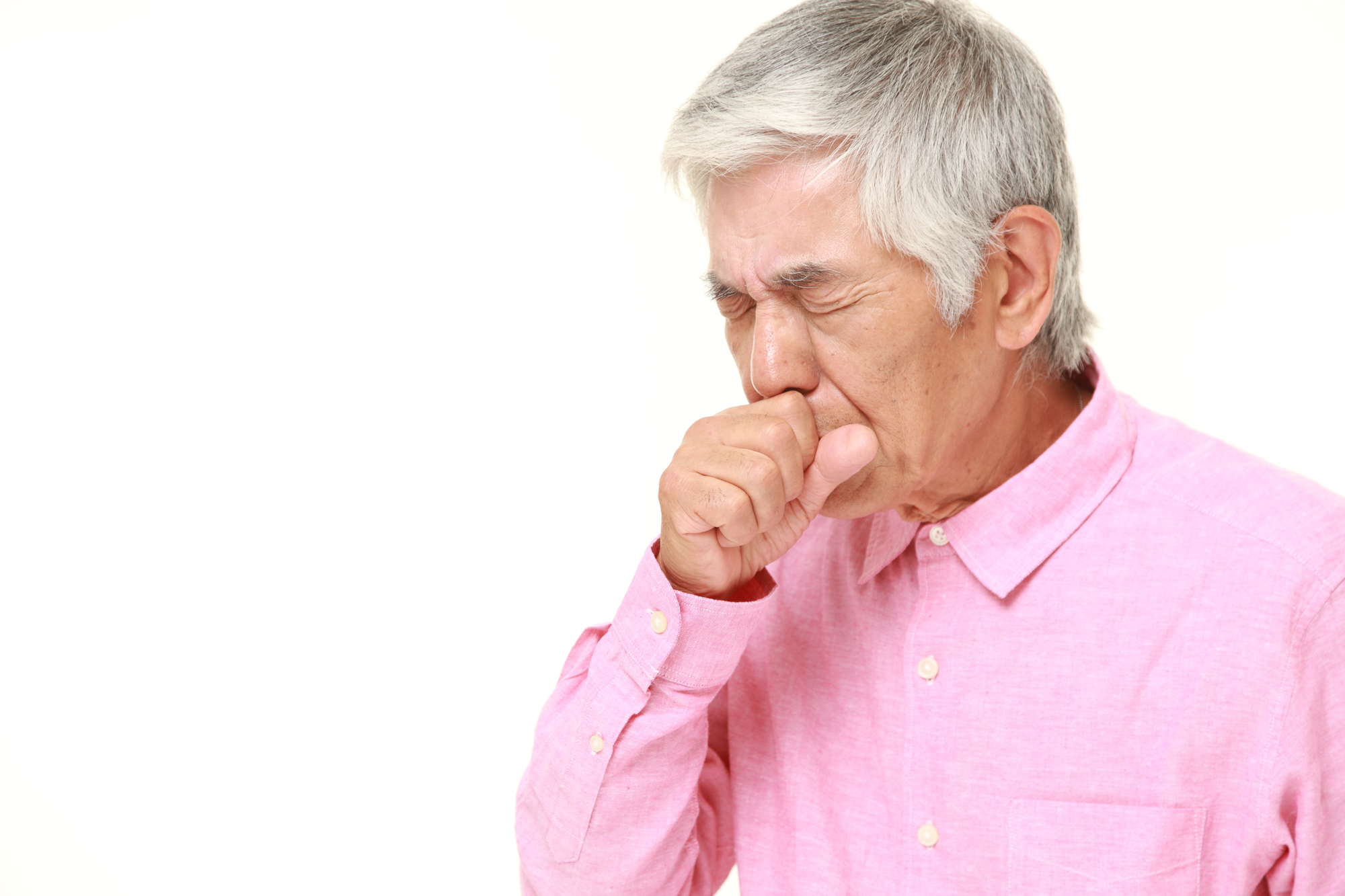 風邪をひいたとき、咳や痰に困った経験のある方もいるでしょう。実は、痰の色や量は、体の状態を教えてくれる重要なサインです。しっかり観察することで、感染の状態を知ることができます。
風邪をひいたとき、咳や痰に困った経験のある方もいるでしょう。実は、痰の色や量は、体の状態を教えてくれる重要なサインです。しっかり観察することで、感染の状態を知ることができます。 痰の色は、感染状況や健康状態によって異なります。そのため、痰が出たときにはしっかり観察することが大切です。ここでは、痰の色からわかる体の状態について解説します。ご自身に当てはまるものがないか、以下のリストを確認してみてください。
痰の色は、感染状況や健康状態によって異なります。そのため、痰が出たときにはしっかり観察することが大切です。ここでは、痰の色からわかる体の状態について解説します。ご自身に当てはまるものがないか、以下のリストを確認してみてください。







