ひざのストレッチで健康維持!
寝ながら・座りながらの簡単セルフケアを紹介
ひざの健康維持は、日常生活を快適に送るために大切なポイントです。加齢によりひざ周りの筋肉が硬くなると、階段の上り下りや立ち座りなどの動作が困難になることがあります。
この記事では、ひざの構造や仕組みを理解したうえで、日常生活に取り入れやすいストレッチ方法をご紹介します。
寝たままや座ったままでできる「ながら」ストレッチを通じて、ひざ周りの筋肉を柔軟に保つ方法や、不調の部位に応じたアプローチ法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
※本記事は医師が特定の商品を推奨するものではありません。

目次
1. ひざの不調予防・軽減にはストレッチを取り入れよう
ひざの不調を感じても「そのうち良くなる」と放置していると、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
ひざ関節は大腿骨、脛骨、膝蓋骨(しつがいこつ)から構成され、周囲の筋肉や腱、靭帯によって安定性を保っている繊細な構造の部位です。特に重要なのがひざ関節軟骨で、一度すり減ってしまうと再生しにくいといわれています。
加齢によりひざ周りの筋力が低下すると、軟骨の摩耗が早まり不調の原因となってしまいます。そのため、適切なストレッチを取り入れてひざ周りの筋肉をケアすることが重要です。
1-1. ひざ周りの筋肉を鍛えることでひざの負担が軽減する
ひざ周りの筋肉が弱くなると、体重を支えるひざ関節に過剰な負担がかかってしまいます。
ひざ周りの筋肉のうち、特に重要なのは、大腿四頭筋、前脛骨筋、腓腹筋の3つです。大腿四頭筋は太ももの前側にあり、ひざの曲げ伸ばしをサポートする役割を担います。前脛骨筋は立位や歩行中のバランスを取るのに大切な筋肉です。腓腹筋はふくらはぎの筋肉で、足首とひざの動きを安定させています。
これらの筋肉を適切なストレッチで鍛えることで、関節の安定性が向上し、ひざへの負担が軽減されるのです。
1-2. 筋力トレーニングの前準備としても大切
筋力が低下した状態で急に激しいトレーニングを始めると、ひざに過度な負担がかかり、逆効果になる恐れがあります。
ストレッチは硬くなった筋肉を徐々にやわらかくし、関節の可動域を広げるため、筋力トレーニングの前段階として最適です。筋肉が柔軟な状態になることで、トレーニング中の怪我のリスクも減少するでしょう。
まずは無理のないストレッチから始め、筋肉の柔軟性が高まったら少しずつトレーニングも取り入れていくことが重要です。この流れを守ることで、ひざの不調軽減につながる好循環を生むことができます。
2. 「ながら」でできる!おすすめのひざストレッチ
ひざの負担を和らげるには、日常生活に取り入れられるストレッチが効果的です。
寝ている時間や座っている時間を活用すれば、特別な時間を設けなくてもひざのケアがしやすくなります。テレビを見ているときや読書中、就寝前のリラックスタイムなど、既存の生活リズムに組み込むことで継続しやすくなるでしょう。
ここでは、生活の「ながら」時間を有効活用できる、簡単でありながら効果的なひざストレッチをご紹介します。

2-1. 寝ながらできるストレッチ
寝ながらできるひざのストレッチを2種類ご紹介します。
横になった状態で行なうことで、体重による関節への圧力が軽減され、より安全に筋肉を伸ばすことができるというメリットがあります。
2-1-1. ひざの可動域を広げるストレッチ
ひざへの負担を最小限に抑えながら可動域を広げる効果が期待できるストレッチです。特にひざの曲げ伸ばしに困難を感じる人や正座ができない人に適しています。
1. 仰向けに寝た状態で片方のひざを曲げ、ゆっくりと胸の方向へ引き寄せる
2. ひざの不調を感じる手前で止める(無理に引っ張ると逆効果)
3. その姿勢を10秒間キープし、3〜5回を1セットとして左右それぞれ3セット行なう
必要に応じてバスタオルを使うと、足を引き寄せる際の補助になります。毎日継続することで、徐々にひざの可動域が広がっていくでしょう。
2-1-2. 大腿四頭筋を柔軟にするストレッチ
大腿四頭筋は太ももの前側にある筋肉で、歩行や立ち上がりなど、ひざを動かすあらゆる動作に関わっています。この筋肉が硬くなるとひざの動きが制限され、不調の原因となることがあるため、柔軟性を保つことが重要です。
1. 横向きに寝て上側の足首を手で持ち、かかとをお尻に近づけるようひざをゆっくり曲げる
2. 太ももの前側が伸びているのを感じながら20〜60秒キープ
3. 同じ動作を2〜3回繰り返す
ストレッチ中は腰が反らないよう注意し、体幹を安定させることがポイントです。特にランニングやジャンプなどひざに負担がかかるスポーツをする人には、日常的に習慣として取り入れることをおすすめします。
2-2. 座りながらできるストレッチ
座りながらできるストレッチを2種類ご紹介します。
椅子に座ったまま行なえるため、テレビを見る時間や仕事の休憩時間など、日常生活の合間にも気軽に取り入れやすいです。高齢者にとっても、立ち上がる必要がないため安全性が高く、体力に不安のある人でも無理なく続けられます。
2-2-1. ひざのお皿をなめらかにするストレッチ
ひざのお皿(膝蓋骨)は本来なめらかに動く構造になっていますが、加齢によって硬くなり動きが悪くなると、ひざの曲げ伸ばしがスムーズにできなくなります。最初は動きにくくても、毎日続けることで次第になめらかに動くようになっていくでしょう。
1. 椅子に座り、ひざをリラックスさせた状態で両手の親指と人差し指でひざのお皿の周りをやさしくつかむ
2. 指で軽く押さえながら、上下左右に、そして円を描くように動かす
このとき、ひざの力を抜いて行なうことがポイントです。無理に動かそうとせず、脱力を意識し負担のない範囲で少しずつ行なうことが大切です。
2-2-2. ハムストリングスをやわらかくするストレッチ
ハムストリングスは太ももの裏側にある重要な筋肉群で、ひざを曲げる動作を担っています。特にデスクワークなど長時間座っている人は、この筋肉が硬くなりやすく、ひざの不調を招きやすいため注意が必要です。
1. 椅子に浅く腰かける
2. 片方の足を前に伸ばし、つま先を天井に向けてかかとは床につけたままにする
3. 背筋を伸ばした状態で上体をゆっくりと前に倒していき、太ももの裏側に心地いい伸びを感じるところで20〜40秒キープ
4. 同じ動作を2〜3回繰り返し、反対の足も同様に行なう
大腿四頭筋のストレッチと合わせて行なうことで、ひざの曲げ伸ばしをよりなめらかにする効果が期待できます。
3. 悩み別におすすめのひざストレッチ
ひざの不調は発生する部位によって原因が異なるため、適切なアプローチが必要です。日常的にストレッチを行なうことで、筋肉の柔軟性を高め、ひざ関節への負担を軽減しましょう。
| 不調の部位 | おすすめストレッチ | やり方 |
| ひざ裏 | 腓腹筋ストレッチ | 段差の外にかかとを出して、かかとを下げてふくらはぎを伸ばし、20~40秒程度キープ |
| 大腿二頭筋マッサージ | テニスボールをひざ裏の外側に置き、かかとを軸につま先を左右に動かす | |
| ひざの内側 | ハムストリングスストレッチ | 床に座り片足を伸ばして前屈し、太ももの裏を伸ばして30秒程度キープ |
| 内転筋ストレッチ | あぐらの姿勢でひざを軽く押しながら、内ももを伸ばして30秒程度キープ | |
| ひざの外側 | 足首の屈伸ストレッチ | 床に座り両足を伸ばし、つま先を遠くに伸ばす・手前に引き寄せる動作を繰り返す |
4. ひざの不調を感じるときに控えるべき運動
ひざの不調を感じるときは、悪化を防ぐためにいくつかの動作や活動を控えるべきです。
急な動きや急停止をともなうサッカー、テニス、ジョギングなどのスポーツはひざに大きな負担をかけるため注意しましょう。代わりにウォーキングなど低負荷の運動を選ぶことで、適度な運動習慣を維持しながらひざを保護できます。
また、正座、和式トイレの使用、床での生活などのひざを深く曲げる動作も、痛みや違和感が生じる間は避けることが大切です。日常生活では椅子やソファー、洋式トイレ、ベッドを使用するとひざへの負担を軽減できます。
さらに、重い物の持ち上げや不適切な靴の使用も、ひざの状態を悪化させる原因となることがあるため、生活習慣の見直しも重要です。
5. サントリーウエルネスの「ロコモア」はひざの健康をサポート!
ストレッチでひざのケアをするだけでなく、内側からもサポートしたい人におすすめなのが、サントリーの機能性表示食品「ロコモア」です。
ケルセチン配糖体(ケルセチンプラス)とアンセリンを含む独自の4成分が配合され、ひざ関節と脚の筋肉にダブルでアプローチします。また、グルコサミンとコンドロイチンのダブル軟骨成分が、ひざ関節のスムーズさを支えます。
臨床試験では8週目でひざ関節を使った動きの改善、16週目で歩行速度の維持が確認されています※1。
さらに、ケルセチンプラスを軽い運動と組み合わせることで、脚の筋肉の柔軟性の向上に役立つことが日本で初めて確認されました※1※2。
さらに、ロコモアに含まれる「ケルセチンプラス」は筋脂肪化抑制作用により、脚の筋力に働きかけるため、日常のストレッチなど軽い運動との併用で、より効果的にひざの健康をサポートできると報告されています。
※1 本データは最終製品を用いた試験のデータではなく、4成分の組み合わせでのデータです。
※2 ケルセチン配糖体が、軽い運動との併用で、筋肉の柔軟性(ひざ関節を完全に曲げた状態)の向上に役立つことが報告された機能性表示食品はサントリーウエルネスが日本初(当社調べ)
6. ひざのストレッチで不調を予防・改善しよう
ひざの不調を予防・改善するためのストレッチ方法をご紹介しました。ひざ関節の健康維持には、周囲の筋肉を柔軟に保つことが重要であり、日常的なケアが欠かせません。
寝ながらできるひざの可動域を広げるストレッチや座りながらできるひざのお皿ストレッチなど、日常生活に取り入れやすい方法を実践してみてください。
ひざに負担をかける急な動きや深く曲げる動作は避け、適切なケアを心がけることが大切です。継続的なストレッチと内側からのサポートで、元気なひざで歩く・動くことを楽しめる毎日を、これからも目指しましょう。
監修者情報

川上 洋平(かわかみ ようへい)
神戸大学医学部卒業。
米国ピッツバーグ大学に留学し、膝関節外科、再生医療、スポーツ医学を学び、神戸大学病院、新須磨病院勤務を経て、患者さんにやさしく分かりやすい医療を提供することを目的に、かわかみ整形外科クリニック(神戸市)を開業。
日本整形外科学会専門医。
https://kawakamiseikei.jp/
- #運動
- #筋トレ

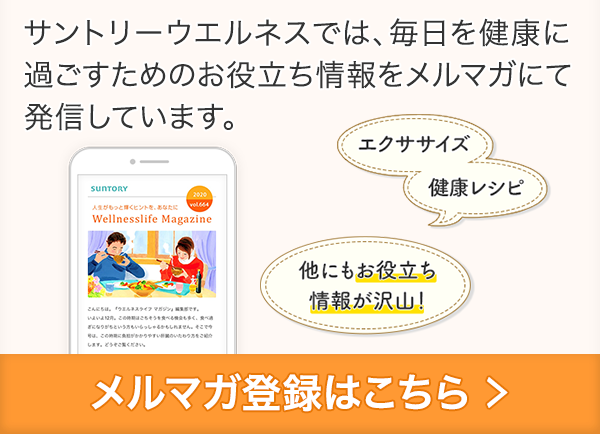



































![TADAS[タダス]](/Content/common/img/43379.webp?20260127)







![Pet Health[ペットヘルス] グルコサミン プラス](/Content/common/img/91006.webp?20260127)




![Pet Health[ペットヘルス] セサミンE](/Content/common/img/91000.webp?20260127)

![Pet Health[ペットヘルス] ARA+DHA](/Content/common/img/91005.webp?20260127)







![VARON[ヴァロン]オールインワンセラム](/Content/common/img/55010.webp?20260127)
![VARON[ヴァロン]オールインワンセラム ギフトセット](/Content/common/img/55030.webp?20260127)
![VARON[ヴァロン]フェイスウォッシュ](/Content/common/img/55050.webp?20260127)
![VARON[ヴァロン] ボディソープ*](/Content/common/img/55044.webp?20260127)
![VARON[ヴァロン] マスターズブレンド](/Content/common/img/55055.webp?20260127)























![conoha[コノハ] スキンケア ソープ チャコール・クレイ](/Content/common/img/51101.webp?20260127)
![conoha[コノハ] スキンケア ソープ マリンコラーゲン](/Content/common/img/51100.webp?20260127)




















![Milcolla[ミルコラ]](/Content/common/img/43370.webp?20260127)


![Liftage[リフタージュ]](/Content/common/img/43384.webp?20260127)



