
社員の健康管理は、業務の生産性に直結するため企業にとって重要な取り組みです。
経済産業省が掲げるヘルスケア産業政策の一つとして2016年にスタートした「健康経営優良法人」の認定制度は、多くの企業から注目され、2022年には「大規模法人部門」に2,299法人、「中小規模法人部門」に12,255法人が認定されています。
今回は、北海道でいち早く「健康経営優良法人」の認定を取得したIT企業、北都システム株式会社の総務部長/健康経営エキスパートアドバイザー 城内 克典さんと、総務人事グループ/保健師 丸田 絵夢さんにお話を伺いました。
北海道に本社を置く独立系IT企業として初の「健康優良法人 大規模法人部門認定」

ーー本日はよろしくお願いします。まずは御社について教えてください。
城内さん:当社は、1994年設立の設立から今年で28年目となるIT企業です。
国内メーカーの携帯電話開発を中心に事業拡大し、その開発経験を活かして現在では、自動車関連ソリューション、医療系ソリューションを主軸とした受託開発事業と多店舗業務支援システム「店舗Linkle」をはじめとする自社サービスのプロダクト事業と両輪で事業展開をしております。
健康経営優良法人の認定を取得してからは、自社で、健康経営に取り組む企業向けのシステム「座りっぱなしモニター」や「みまもりモニター」といったサービスを提供しています。
ーー健康経営に取り組みはじめたきっかけを教えてください。
城内さん:「健康経営」が注目される前から、当社では人間ドックや婦人科検診の費用補助(法定項目以上の定期健診)を実施していました。
健康経営優良法人の認定取得の取り組みを始める前から、比較的、社員の健康に関する制度は手厚いほうだったと思っています。
あるとき、健康経営優良法人認定制度があることを知り、「自社の制度は当たり前のことと思っていたが、意外と健康経営に取り組めているほうなのでは?」「社員にとっても、対外的にも、認定取得はPR効果があるのでは?」と考えたことがきっかけです。
2020年3月に初めて大規模法人部門での認定を取得し、3年継続するに至ります。
北海道に本社を置く独立系IT企業としては、初の大規模法人部門認定でした。
現在でも、大規模法人部門で認定を取得しているIT企業は道内で3社しかありません。
社外に向けてのPRや人材採用において、道内でもいち早く認定を取得することのメリットは大きいと感じており意欲的に取り組むことができています。
ーー「健康経営優良法人」の認定取得において、大変だったことはありますか?
城内さん:もともと医療情報システムに携わるなど、健康管理が当社の事業と近しいところにあったからなのか、皆さん健康診断もきちんと受けてくれますし、大変だったり、障壁を感じたりしたことはあまりありません。
ただ、会社の取り組みとして社員に健康経営を押し付けてしまったり、名ばかりの認定になって中身が伴わないものになったりしないように、という点は意識していました。
「会社はあくまでサポート役。取り組みは各自の責任で。~健康の押し売りはいたしません~」をスローガンに掲げているのですが、社員各自が必要だと感じたときに、充実した制度が整備されている状態が理想ですね。
社員が気軽に健康相談をできるように、常勤の保健師を正社員として雇用

ーーありがとうございます。実際に取り組んだ施策について詳しく教えてください。
城内さん:当社の健康診断ですと、各種がん検診をはじめ、全年齢における婦人科健診や50歳以上の脳ドックの受診まで費用は全額会社負担としています。
社員一人ひとりが、各自のタイミングで必要な検診を受けられるように、健康診断のオプション検査は全額会社負担のスタンスを続けています。
インフルエンザ予防接種やオンライン禁煙プログラムの全額会社負担、無添加・減塩・国産食材にこだわった「置き型社食サービス」の設置にも取り組んでいます。
また、産業保健師を常勤の正社員として迎えたことも、健康経営の取り組みがきっかけです。
ーー丸田さんのことですね。産業保健師として、どのようなことに取り組んでいるのでしょうか。
丸田さん:産業保健師として、社員の健康相談、健康診断受診後のフォローや、健康経営の啓蒙・推進、社内各部署に向けて必要なヘルスケアの講座を実施しています。
企業で働く保健師は、全国でも4,000名程度といわれていますが、当社のように社員数200名ほどの規模で保健師が常勤している企業は珍しいのではないでしょうか。
城内さん:常勤保健師として、社内に健康に関する相談窓口ができたことは、社員の意識改善にとても役立っているように感じます。
丸田さん:そうですね。いろいろな部署から健康に関する相談を受けることが増えました。健康相談をきっかけに、社内向けのセミナーを企画することもあります。
また、入職してすぐの頃はコロナ禍で、札幌市内の医療機関が逼迫している状況でした。
正社員として常勤する傍ら、札幌市の保健所の健康観察業務にも参加していました。
コロナ陽性と診断され、自宅療養をしている方に対して体調の変化がないか聞き取りをしたり、入院調整が必要かどうかを検討したり……といった支援業務です。
通常の業務もありましたが、道内の感染者が増え続けるなかで、保健師としてできることはないかと上長の城内に相談したところ、毎週金曜日に支援参加を認めてもらいました。土曜日も自主的に参加していたので、実際には週2回ですね。
当社の健康や福祉に理解のある風土が、私個人の保健師としての活動をあと押ししてくれたようなかたちです。
ーー城内さんは「健康経営エキスパートアドバイザー」の資格もお持ちとのことですが、どのような活動をされているのでしょうか?
城内さん:健康経営アドバイザーは、東京商工会議所が取り組んでいる認定制度です。
なかでも、健康経営エキスパートアドバイザーは保健師や中小企業診断士といった公的な資格を持っているエキスパートな方々が取得する資格なのですが、「実務経験者でも可」とあったので、どうせ取るなら狭き門を……と思って今年の2月に取得しました。
健康経営の啓蒙のための情報発信を期待される認定制度なので、おもに社外に向けたセミナーや講演会への登壇や、Webメディアでの情報発信の際の肩書きとしても役立っています。
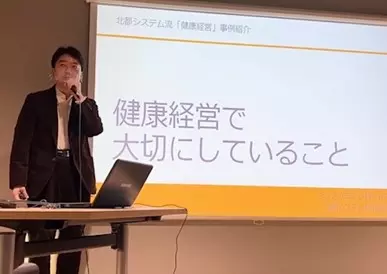
今後はメンタルヘルスケアの充実を目指した健康経営を
ーー今後、健康経営に関してさらに取り組んでいきたいことはありますか?
丸田さん:どうしてもIT企業など情報通信業は、メンタルの不調から休職になってしまうケースが多いので、そこを改善するためにメンタルヘルス関係の教育や啓蒙を充実させたいと思っています。
組織の階層別に設計した社内のメンタルヘルス研修など、取り組んでいきたいですね。
城内さん:個人の健康状態に、会社がどこまで踏み込むべきなのか、悩ましくはありますが、職場のストレスは会社でなんとかできると思っています。
心身ともに、健康に働いてもらうために会社としてできることはまだまだあるのかなと。
メンタルヘルスの問題では、早期発見・早期治療も大事ですが、ストレス要因を低減できるような環境面のアプローチなどにも力を入れていきたいと思っています。
あとは、道内で先駆けて健康経営に取り組むIT企業として、札幌市立大学の保健師実習生を受け入れることにしました。
丸田さん:もともと産業保健実習を予定していた実習先で、コロナ禍を理由に受け入れを断られてしまい、実習先がなく困っているという話を聞いて。
まだ数の少ない産業保健師の後進を育てることにも貢献できたらと思い、城内に相談したところ、受け入れを快諾してくれました。
私が学生の頃は、企業での実習はなかったのですが、社会的な需要の高まりを感じます。
学生の方も、保健師としての就職先や活躍の幅が広がるので良い機会ですし、実習では企業で働く方に向けた情報発信などを学んでもらおうと計画中です。
ーーでは、最後に読者に向けてのメッセージをお願いします。
城内さん:国が健康経営を政策的に強化してきたこともあって、ここ数年で企業のヘルスケアへの関心が高まり、産業医や産業保健師の需要が大きくなっていることを感じています。
健康経営に関心のある企業の担当者さんがいらっしゃったら「会社に保健師がいてくれること」の良さをぜひお伝えしたいと思います。
今後も、長く健康に働ける職場づくりに取り組んでいきたいですね。
丸田さん:職場の人間関係においては、体調のことなど個人的なことを、周りに相談しても良いのか、相談するべきなのかに悩み、個人で抱え込んでしまう方も少なからずいらっしゃると思います。
健康に関してフラットに相談できる立場として、保健師が少しでも役に立てたらと。
保健師として勤務するようになって、徐々に社内の管理職の意識も変わってきたように感じます。
社員の退職は、どこかで仕方ないものととらえていた管理職の方から、ヘルスケアの取り組みで、少しでもケアができたらと相談にきてくれることが増えました。
城内さん:今まで散々提言してきたのに何もしなかった人が、丸田さんのいうことはすんなり聞き入れる……ということがよくありますね。(笑)
企業規模に関わらず、すべての企業において、保健師さんが常駐していることは健康経営に大きく貢献してくれるということを強く実感しています。
ーー本日はありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:北都システム株式会社
インタビュアー:朝本麻衣子
サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら








