
広島電鉄株式会社は、大正時代から広島県の公共交通・街の発展を支えてきた老舗企業です。社員の多くが電車とバスの運行業務にあたる同社では、定期的な脳疾患・心疾患検診を設けるなど、社員の健康管理に力を入れています。
今回は人事部課長として健康管理・安全衛生部門と福利厚生部門を担当されている船本 剛志さんにお話を伺いました。
安全運行が不可欠。人々の移動を支える広島電鉄株式会社
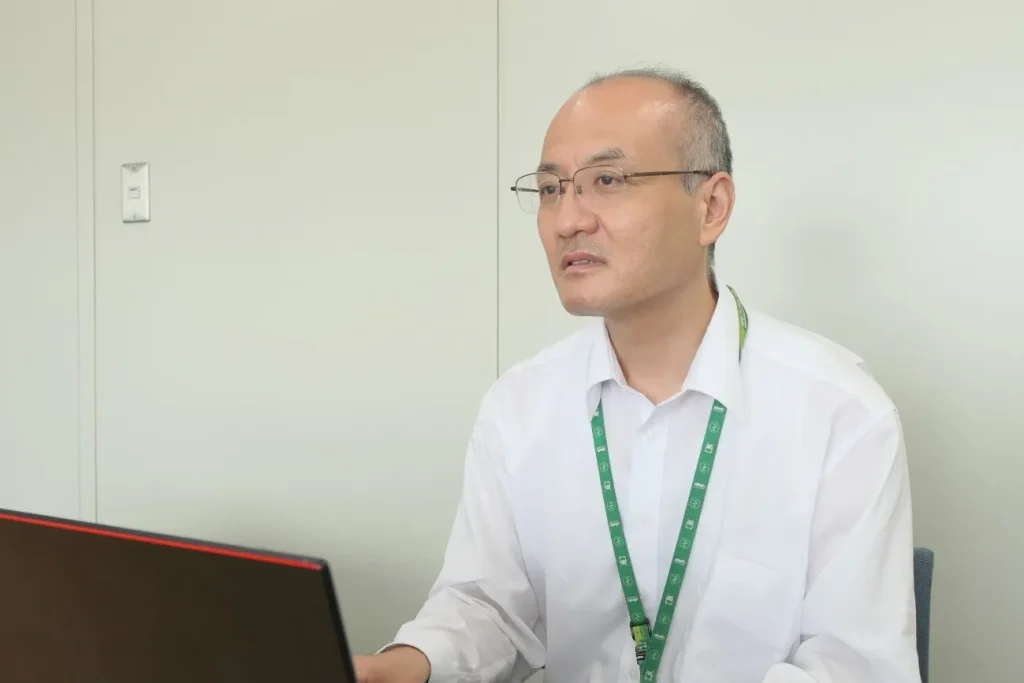
ーー本日はよろしくお願いします。まずは御社の事業内容を教えてください。
1912年に広島で路面電車の事業を開業し、今年で創業110周年を迎えます。現在は電車・バスといった公共交通事業だけでなく、不動産事業や街づくりも展開しており、移動の「手段」だけではなく移動の「目的」の創出に積極的に取り組んでいます。
ーーありがとうございます。健康経営に注目されたのは何がきっかけだったのでしょうか。
当社は社員の約7割が電車運転士や車掌、バス運転士なので、安全な運行を確保するためには健康管理が必須です。特に脳疾患や心疾患は運転中の事故リスクに直接つながりますので、少しでもそのリスクを下げる必要があります。
ただ、電車やバスの乗務にあたる社員は、ダイヤに沿ったシフト勤務になるので、生活が不規則になりやすく、平均年齢も50代近くと高めですので、健康診断の有所見率が高い傾向にありました。社員1人ひとりが生活習慣を見直して元気に働くために、健康経営は非常に重要な取り組みと考えています。
休暇付きの「人間ドック」及び「終夜睡眠ポリグラフ検査」を導入
ーー具体的な施策についてお聞かせください。
平成27年から、全従業員を対象とした人間ドックに加え、運転士を対象に脳疾患検査、心疾患検査を行っております。
実施頻度は、運転士以外の事務系社員では40歳・50歳・60歳・65歳のタイミングで受診しますが、電車・バス運転士は、35歳~65歳にかけて5歳ごとの年齢と67歳・69歳のタイミングといったように、頻度を増やして実施しております。
また、睡眠時無呼吸症候群(睡眠中に呼吸が浅くなったり何度も止まったりすることで低酸素状態になり日中の強い眠気や高血圧を引き起こす病気)の簡易検査を3年に1度行なっておりましたが、検査の結果、精密検査が必要と判定された方に1泊2日の「終夜睡眠ポリグラフ検査」という検査も行なったのも、この年からです。
これらの検査について休暇を与えて行なったことが当社にとって大きな変化でした。
メンタルヘルスケアに関しては、臨床心理士によるカウンセリングや社外のカウンセリングルームの活用、産業医・保健師といった産業保健スタッフによるサポートを行なっています。
特に新入社員や昇職した社員、部署異動をした社員は、悩みの有無に関わらずカウンセリングを受ける機会を設けています。もし悩みがあれば、どのような状態なのか関係者で情報連携をして改善に向けてサポートをしています。
1人ひとりに合った働き方をつくる「短時間正社員制度」

ーー御社では「短時間正社員制度」という制度も設けていらっしゃいます。どのような制度なのでしょうか?
短時間正社員制度は、多様な働き方を実現し、優秀な人材の安定的な確保のために平成29年9月から導入しています。健康上の理由や家庭の事情など理由は問わず、正社員でありながら週3日勤務や一日5時間勤務にするといったように、本人の希望に沿って働き方を自由に設定できる制度です。
家族の介護をするため、自身の持病の治療と両立するためといったさまざまな理由で活用されています。私の部下も実際にこの制度を活用していますし、今は使っていない社員にも制度自体は認知されている状況です。
子育てや介護など家庭の事情、自身の健康上の理由をはじめ、「柔軟な働き方が必要になったらいつでも活用できる」という認識はもってもらえていると思います。
ーーライフステージや自身の健康状況が変化しても心強い制度ですね。一方で、公共交通サービスを提供されている御社でこの制度を導入することに難しさはなかったのでしょうか?
やはり電車やバスの乗務職場では、勤務シフトを組むうえで一定の苦労があると思います。ただ女性ドライバーやシニアドライバーも含めて、全社員が無理のない方法で働けるようにする必要がありますし、こうした取り組みは、運転士の採用を増やすためにも必要だと感じています。
ちなみに、65歳の定年退職後も再雇用して70歳まで働ける制度も整えていますので、65歳以降も引き続き当社で勤務している運転士もいます。そのなかには「フルタイムで働きたいから勤務日は週2日」といった働き方をしている社員もおり、体力やライフスタイルに合わせた働き方が可能になっていると感じますね。
「健康経営」を1人ひとりが意識することが重要
ーー健康経営に取り組む上での課題、難しさはありますでしょうか。
なかなか効果が数字に出にくいことです。即効性がある施策ばかりではないので、地道な努力が必要だと感じています。また、年齢が上がるとどうしても健康診断の有所見率も上がりますので、それを踏まえたうえでの取り組みが必要ですね。
施策を打ち出すのは人事部ですが、最終的には社員1人ひとりが健康意識をもつことが不可欠です。健康の大切さに気付いてもらえるように働きかけていくのが私たちの仕事だと考えています。
ーー特にどのような点で個人の意識が重要だと思いますか?
おもに高血圧、高脂血などいわゆる生活習慣によるものと喫煙ですね。当社は喫煙率が高い傾向にあるので、先日、産業医によるオンラインでの禁煙セミナーなどを行いましたが、この他にも生活習慣改善に向けての取組について検討しています。
ーー反対に、健康経営に取り組んだことで起きた効果・変化があれば教えてください。
最初にお話したように人間ドック・脳疾患・心疾患の検査に力を入れたことで、社員の検査結果に対する意識が変わりました。特に運転業務にあたる社員の検査結果について、現場監督者とよく確認しており、有所見が出た場合は社内ですぐに連携を図っています。
産業医からも気になる項目があった社員に働きかけて、健康状態や治療状況を確認するなど、常にコミュニケーションをとっています。
ーー社員の方からは、取り組みに対してどのような反応があったでしょうか。
健康経営優良法人に認定されたことで、「健康」を経営目線でとらえる社員が増えていると感じます。企業としての方針があらためて認知されたと思いますし、ある銀行融資の申し込みに際し、当社の健康経営の取り組みを評価していただいたことがありました。
今後も施策を続けたり、社内でPRしたりする必要はありますが、認定を受けたことは社員の健康意識を高める一助になっていると思います。
自覚と行動のきっかけづくりを続けたい

ーー今後の展望がありましたらお聞かせください。
生活習慣を改善する要素のうち、特に運動習慣の定着に力を入れていきたいと考えています。私は健康保険組合の業務にも携わっていますが、これまで保健事業として行なっているウォーキングイベントに加えて、個人の健康づくりにつながるような取り組みを検討しています。
また昨年から期間限定で、広島県による健康経営増進に向けた実証実験にも参加しています。これはAI技術で生活習慣病の発症リスクを可視化し、生活習慣の改善提案を行なうというものです。
広島県内に事業所がある企業や団体が協力しており、当社の希望者も歩数や食事習慣、睡眠時間などのデータを、スマートフォンアプリへの記録を通して提供しています。
自分の生活習慣に関する数値をしっかりと記録すること、健康状態を自覚することは健康意識を高めるのに役立つと思います。こうした取り組みも今後の施策を考えるうえで参考にしながら、少しでも健康的に長く働くための仕掛けづくりやサポートを続けていきたいですね。
ーー最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
健康な生活を送るために必要なことは、やはり自分自身の生活習慣を自覚することではないでしょうか。そして「少しでも歩く」「少し間食を減らす」「煙草を1本減らす」といった小さな改善をすること、一歩でも動き出すことが大事だと思います。
私自身も、体重が増えたことに気付いてウォーキングを始めました。「自覚をもつこと」と「一歩踏み出すこと」が大切だという経験を踏まえ、今後も健康増進のきっかけづくりを社内で担っていきたいと思います。
ーー本日はお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:広島電鉄株式会社
インタビュアー:青柳和香子





