
株式会社サイバーリンクスは、食品流通業や官公庁などに高機能クラウドサービスを提供するIT企業です。
企業認知度を上げる取り組みの一環として開始した「健康経営」を部署横断的に進め、経済産業省と日本健康会議による「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」に認定されました。
今回は同社で健康経営の推進を担う総合管理部 部長の鳥居孝行さん、総務企画課 課長の上本賀代さん、人事課主任の中谷裕介さんにお話を伺いました。
認定のためだけでなく、本気で取り組むほうがおもしろい
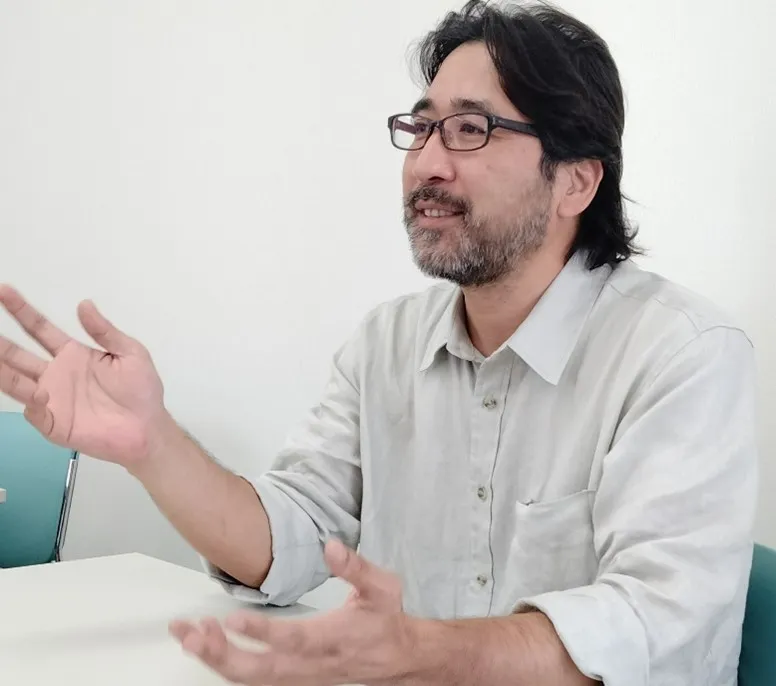
ーー本日はよろしくお願いします。まずは御社の事業について教えてください。
中谷さん(以下、中谷):当社は1956年に創業し、和歌山県に本社を置くIT企業です。食品流通業や官公庁、学校教育機関向けのクラウドサービスの開発・提供を行なっています。
また和歌山県内でドコモショップを運営するほか、2021年度からは電子契約や電子委任状サービスを行なうトラスト事業を開始しました。
ーーありがとうございます。健康経営について、皆さんそれぞれのご担当内容も教えていただけますか?
鳥居さん(以下、鳥居):健康経営は、管理部門内のプロジェクトチームで推進しています。人事課で、調査や従業員へのアンケートをもとに具体的な人事制度や施策を検討することが多いですが、プロジェクトメンバーで検討することもあります。皆のアイデアを提案資料に取りまとめ、経営会議で施策を提案するという流れで進めています。
上本さん(以下、上本):総務企画課は、おもに広報を担当しています。健康経営をはじめとする当社の取り組みについて、社内外に幅広く伝えて、会社のことを知っていただく業務です。
最近では、「サステナビリティ」や「人的資本経営」にも関心が高まっていますので、当社でも会社Webサイトに健康経営を含むサステナビリティに関する情報を公開したり、人材に関するサステナビリティデータを開示したりするなど、試行錯誤しながら活動しています。 また、社内向けの情報発信として「Web社内報」を運営しています。
中谷:人事課では、産業医や協会けんぽと連携し健康経営を推進しています。人事課では健康経営や、働きやすい職場づくりに関する具体的な施策を打ち出して、社内への導入・浸透を行なっています。
ーー健康経営に取り組み始めたきっかけは何だったのでしょうか。
鳥居:もともとは当社の認知度を高めるプロジェクトの一環で立ち上げた取り組みで、「健康経営優良法人」の認定を取ることを目標に掲げて動き始めました。
実際に健康経営度調査の回答を作成していくなかで、健康増進に関して、できていることもあれば課題もあるとわかってきました。そして「認定を取るためだけでなく、会社をあげて本気で健康経営に取り組みたい」という考えに変わっていったんです。
そのほうが取り組みを推進する我々もおもしろいですし、従業員にとっても良いプロジェクトになるだろうと考え、経営陣の理解も得ながら開始できました。
ーー具体的にはどのような課題があったのでしょうか。
鳥居:例えば、健康診断の結果を可視化し、ヘルスリテラシーを向上させる取り組みが課題に挙げられました。従業員が常に健康を意識しながら健康増進に取り組めるように、健康診断結果をデータ化して日常生活に生かせるツールの導入検討を進めています。
その他、従業員の食生活の改善、運動機会の増進、喫煙率の低下に向けた取り組みも行ないたいと思っています。
また、コロナ禍によりテレワークをするスタッフが大幅に増えました。柔軟に働くことができ、通勤ストレスから解放されるといったメリットがある一方で、コミュニケーションに関して悩んだり体調を崩したりしているスタッフも少なからずいますので、テレワークの環境下でもできる健康増進の取り組みを考えていく必要があります。
テレワーク増でメンタルヘルスケアが重要に

ーー実際のお取り組みについて教えてください。
中谷:最近の例でいうと、禁煙のサポートプログラムを導入しました。具体的には、禁煙外来に通って禁煙を達成した場合や、禁煙体験サービスを利用した場合に、費用を一部補助するものです。
また、テレワークの浸透により、従業員同士がリアルに顔を合わせることなく業務を進めることが多くなってきています。新たに入社した従業員が、直接顔を合わせたことがないメンバーと連携して業務を行なうことも少なくありません。
従業員のコミュニケーションを促進し、早く職場に慣れるきっかけとなるよう、社内報で従業員の紹介を行なう「サイバーな人々」というシリーズ企画を行っています。
メンタルヘルスケアでは、すでに悩みのある従業員に関しては定期的な面談を行なっています。また、定期的なアンケート実施時に仕事の環境や家庭の状況に関して、まだ上司に言えていない悩みを書いてくれる従業員がいるので、個別で面談をしたり、必要に応じて上司や同僚に情報を共有したりしながら不調を事前に防ぐよう対応しています。
また、長期内部戦略目標(一人ひとりが主役)達成のためのテーマとして掲げている、「働きがいのある職場をつくる」の達成のため、2021年度からワーク・エンゲイジメント調査を始めました。
本人も家族も安心して休めるように。長期療養時の所得補償制度を導入
ーー2022年5月に団体長期障害所得補償制度(GLTD)を導入されたそうですが、どのような制度なのでしょうか。
鳥居:病気や怪我により、従業員が長期間仕事に復帰できなくなった場合に、月収相当額の一定割合を補償する制度です。長期療養で働けない状態が180日を超えた場合に補償が開始され、最長で65歳の誕生日まで継続します。
この制度を導入した背景として、実際に長期療養を必要とする従業員が出てきたことがあります。本人が治療に専念できてご家族も安心できるような制度をつくりたいという、社長である村上の思いがありました。
そこで村上個人の財産を拠出して財団法人を設立し、グループ会社の役職員全員を対象とした所得補償保険を採用しました。もちろんこの保険が適用される従業員が出ないのがベストではありますが、万が一のために従業員が安心して働ける環境作りは必要ですね。
従業員の声から時間休や健康休暇を整備

ーーほかにはどのようなお取り組みをされていますか?
上本:ここ数年、柔軟な働き方の推進に力を入れて取り組んでいます。例えば1時間単位の有給休暇取得や時差出勤ができるようになったので、朝少しだけどこかに寄ってから出社する、1時間だけ休みを取って早く帰るといった無理なく働ける環境が整ってきました。
ご家庭があると、なかなか休みの日に自分の時間が取れないこともあると思います。私自身も活用していますし、「半日休みにすることもないけど、ちょっとした用件を済ませたい」というときに、とてもありがたい制度だと思っています。実際に、社内にとても浸透していますね。
中谷:「健康休暇」という制度も用意しています。年次有給休暇を使い切ってしまった後でも、自分自身や家族の健康に関する理由で休みを取りたい場合に、年次有給休暇とは別に有給で休暇が取れるというものです。
1年で5日付与されて、最大40日まで積み立てができます。長く休んだり入院したりしないといけないときにも、年次有給休暇のあとに健康休暇を取ることができ、万が一のことがあっても焦らず休める環境づくりに貢献しているのではないかと感じています。また、さらに長期化する場合は先ほどのGLTDを利用することが可能です。
形骸化せず実際に活用される制度とするため、検討・立案する際には従業員の声を反映することを大切にしています。
健康経営の取組を開始する前には、「より多様な働き方が認められる制度を検討してほしい」との声を受け、時差出勤制度と、介護や育児などの事情がある従業員向けのテレワーク制度を導入しました。その後コロナ禍を受けて、テレワーク制度は対象者と勤務可能場所を拡大し現在の形となりました。
健康経営の取組開始後には、年次有給休暇の取得率向上に向けたアンケートを実施し、その内容を受けて時間単位年休制度と先述の健康休暇制度を整えました。
今は「働きやすい」という声をもらっているので、取り組みの効果が従業員に届いているんだなと感じています。
鳥居:従業員の考えをしっかりとらえて、制度に生かすということを大切にしているのは当社の特徴かもしれません。我々管理部門だけが考えるのではなく、従業員にアンケートをとるなど、従業員の生の声を吸い上げてより良い制度をつくる工夫は頻繁に行なっています。
経営陣も提言を前向きに受け止めていただける社風があるように思います。週に1回経営会議があるためいつでも提言できる機会がありますし、ちょっとした思いつきからいろいろと考えが膨らみ、「もっとこうしたらいいんじゃないか」と形にしていくんです。それを頭から否定されてしまうことはまずないので、提言をすることに対してプレッシャーもありません。
いいなと思ったことを少し形になるまで検討したら、すぐに会議で取り上げています。
「価値観や生活はそれぞれ違う」ことを理解し合う職場にしたい

ーー健康経営に取り組むなかで、苦労されていることや難しさを感じることはありますか?
中谷:全員が喜んでくれる施策はないということに難しさを感じますね。従業員1人ひとり、価値観や生活スタイル、ご家庭の状況も違いますので、全員に100%フィットする効果的な施策を打ち出すのは難しいと感じています。
でも、だからこそ人事や管理部門がさまざまな制度をつくり、従業員それぞれが自分に適した制度を使えるようにする姿勢を示し続けることで、メンバー同士もお互いを理解して働きやすい職場をつくれるのではないでしょうか。
良いと思った制度は前向きに考え、情報を積極的に発信して文化面もできるだけ良い方向に動かしていきたいと考えています。
別の課題として、食事と運動に関する大規模な施策が打ち出しにくくなっている点があります。この数年でテレワークをしやすい環境は整備できたものの、従業員同士が離れて働いていることで、食堂や運動施設を設けるといった方法が難しくなりました。
上本:提携しているスポーツジムの詳しい利用案内などは社内報で届けており、アクセス数も高かったので、利用してもらえていたらいいなと思いますね。
健康診断の結果が返ってきて健康意識が高いタイミングを狙って健康に関する情報発信を行なうことで、従業員一人ひとりが、ご自身の健康について意識するきっかけになればいいなと思います。
人それぞれの「働きやすさ」が活気ある職場、社会をつくる

ーー今後の展望があればお聞かせください。
鳥居:いかに働きやすく、ストレスなく働いてもらえるかが個人の健康につながっていくと思っています。例えばテレワークのほうが働きやすい人もいれば、そうでない人もいますので、中谷たちを中心に今後も柔軟な働き方制度を検討・導入していくことになりそうです。
中谷:引き続きアンケートをもとにしながら、今後はよりきめ細かな施策を検討していきたいですね。継続して取り組んでいるうちに当社特有の問題も見えてくると思うので、それに対し前例にとらわれない柔軟な対応を行いたいと考えています。
上本:たくさん施策を用意して、アラカルトで自分に合ったものを選んでもらうスタイルになっていくのではないかと思います。
事業所は北海道から九州まであり、出社必須の人もいれば完全テレワークのスタッフもいるので、それぞれの方にフィットするような施策をその時々の自分のステージに応じて活用していくイメージです。
ーー最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
鳥居:まだ始めて数年ですが、健康経営に取り組んでよかったなあと思います。やはりみんな健康で生き生きと働いている会社が将来伸びていくと思いますし、自分自身もそういう会社で働きたいですから。
従業員みんなが少しでも健康になってくれたらいい会社に近づけるのではないかと思いますし、取り組んでまったく損はないので、ほかの企業の方にもおすすめしたいですね。
上本:当社の経営方針に「1人ひとりが主役」というキーワードがあり、1人ひとりの興味ややる気が、会社の成長の原動力になると考えています。
体と心の健康は密接に関連しているので、体が不調なときは仕事もプライベートも崩れてしまいかねません。健康経営は当社の経営方針に基づく、考え方の支柱になっていくのではないかと思います。
中谷:この仕事をやっていて感じるのは、1人ひとりが健康に対して関心をもつことが、長い目で見ると全員にとっていいことばかりだということです。本人が毎日健やかに過ごせるだけでなく、会社にとっても生産性向上や活気につながりますし、社会全体にも反映されると思います。
健康に関心を持って身近な人と話す、自分なりの考えをもつことを意識してみていただけたらうれしいです。
ーー本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。
今回お話を伺った企業はこちら:株式会社サイバーリンクス
インタビュアー:青柳和香子
サントリーウエルネスのおすすめ商品はこちら








